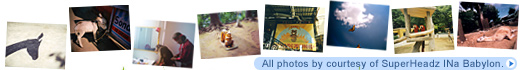2021年7月30日
「フィルターバブルの進行する中で ―― 情報の多様性確保と主体性の回復」
弁護士 二関辰郎 (骨董通り法律事務所 for the Arts)
同じ経験をしても人によって感じ方は異なる。同じ情報に接しても人によって受け止め方は異なる。よくあることだが、本コラムで取り扱うのはそういうことではなく、他の人と同じだと思っていた情報が、実は各人向けに加工(パーソナライズ)されていて、そもそも接する情報が人によって異なるという話だ。
テレビ、ラジオ、新聞、雑誌では、他の人と自分が見る情報は、地域や版による違いなどを別とすれば同じである。しかし、インターネット上ではそうではない現象が進行している。そういった現象を指す言葉に、フィルターバブルとかエコーチェンバーがある。本コラムでは、割と多方面に話が及び多数の用語に触れることや、わかりやすさ重視の風潮への疑義に後で少し触れることもあり、用語の説明は最小限にとどめようと考えている。とはいえ、これらは本コラムの中心的なキーワードなので説明しておくと――
「フィルターバブル」とは、アルゴリズムがネット利用者個人の検索履歴やクリック履歴を分析し学習することで、個々のユーザーが見たいであろうと推測される情報が優先的に表示され、利用者の観点に合わないと推測される情報から隔離され、自身の考え方や価値観の「バブル(泡)」の中に孤立する情報環境を指す。
「エコーチェンバー」とは、ソーシャルメディアを利用する際、自分と似た興味関心をもつユーザーをフォローする結果、意見をSNSで発信すると自分と似た意見が返ってくる状況を、閉じた小部屋で音が反響する物理現象にたとえたものを意味する。
(各用語の定義は総務省情報通信白書を若干改変)
ネットの世界では多くの新語が生まれては消えていくが、これらの言葉には結構歴史がある。エコーチェンバーは2001年から(キャス・サンスティーン『インターネットは民主主義の敵か』)、フィルターバブルは2012年から(イーライ・パリサー『閉じこもるインターネット グーグル・パーソナライズ・民主主義』)の言葉だ。「バブル」と聞くと、すぐに弾けていたり、すでに割れている方式を連想するかもしれない(私はそうだ)。しかし、フィルターバブルでいう「バブル」は、見えずに割れない泡の一つ一つに各人が包まれており、外から入ってくる情報に、知らぬうちにフィルター(フィルタリング)がかかっているイメージだ。
閲覧履歴や検索用語などに基づいて分析したその人の興味関心に基づくパーソナルな情報の提供は、ネット広告にとどまらず、検索エンジンを使った際の検索結果の画面や、ネット上のニュースなど、さまざまなコンテンツに及んでいる。検索エンジンでは、同一用語で検索した場合でも、表示される結果は人によって異なる可能性がある。
ただでさえ情報過多の時代なので、自分に興味関心のある情報にあらかじめ絞ってくれるのは便利で良いという受け止め方もあるかもしれない。しかし、接することのできる情報が限られることで、多様な情報や視点、考え方を新たに獲得する機会の減少・喪失につながる。「パーソナライズされた環境は自分が抱いている疑問の解答を探すのには便利だが、視野にはいってもいない疑問や課題を提示してはくれない」のだ(パリサー『フィルターバブル インターネットが隠していること』)。フィルターバブルやエコーチェンバーがあると、新しい学びや視野の獲得にはつながりにくい。
表現の自由の世界では、伝統的に「思想の自由市場」(米国連邦最高裁ホームズ裁判官反対意見 Abrams v. United States, 250 U.S. 616(1919))とか、”more speech”(同ブランダイス裁判官 Whitney v. California, 274 U.S. 357(1927))といった考え方がとられてきた。誤った事実や考えは他の表現からの批判に晒されて淘汰されるため、より多くの表現を流通させることによって真実に到達できるという考え方である。「思想の自由市場」という考えについてはさまざまな議論がなされてきたが、フィルターバブルやエコーチェンバーと言われる状況が広がると、そもそも異なった考えに接する機会自体が減少あるいは消失してしまう。思想の自由市場あるいは”more speech”の前提を欠くことにつながる。
フィルターバブルやエコーチェンバーを可能あるいは深化させている仕組みとして、クッキーなどのオンライン識別子を利用した閲覧履歴等の収集やプロファイリングがある。
2020年の個人情報保護法改正によって、日本でもいよいよクッキーなどのオンライン識別子が法律の射程に入るようになった。もっとも、この法改正は、クッキーなどを個人情報や個人データの定義に含めて全面的に法律の規制を及ぼすようにしたわけではない。クッキーは、特定の個人の識別にはつながらないことを前提に、新たに設けられた「個人関連情報」(改正法26条の2)という定義に含まれることとした。それが第三者に提供され第三者の下で特定性を有する場合を念頭において規制する建て付けだ。
かつて本サイトのコラム(「ライフログ・行動ターゲティング広告とプライバシー(1)」)で指摘したが、事業者は、ネット上の閲覧履歴の収集にあたり、その閲覧がどこの誰によるものかという情報を必ずしも要しない。ターゲティング広告を行う事業者からすれば、その人が何に興味関心をもっているかを把握し、その興味関心に合わせた広告を届けられるかが肝心だ。そのためには興味関心を示すデータの集積点としてクッキー等のオンライン識別子があればよく、それが具体的にどこの誰であるかは関係ない。
個人情報保護法が新たに取り入れた「個人関連情報」の概念と規制は、すでに述べたとおり、第三者に提供することで、特定の個人が提供元では識別されなかったが、提供先で識別される場合を念頭においている。この規制は、リクナビ事件などを受けてのことで、それはそれで重要な意義を有する。しかし、事業者側のニーズとして、特定の個人が識別されないままの利用でも目的が達成される。さらに、それら事業者同士がデータを共有することで、その人(オーディエンス)向けに情報をより洗練させるオーディエンス・ターゲティングと言われる手法も進展している。そういった利用行為が、特定の個人が識別されないままであれば規制対象にしなくてよいのかという問題は残る。
プロファイリングは、アルゴリズムを用いた個人データの自動処理によって、その個人の業務遂行能力、経済状態、健康、個人的嗜好、興味関心、信頼性、行動、位置および移動を分析または予測することを意味する。プロファイリング技術を用いて各人に表示される情報が選別されると、各人が興味関心を持ちそうな情報がアルゴリズムによって予測され、その人が見る情報の範囲が決められることになる。人はアルゴリズムに従属し、主体性を失うことになりかねない。データ分析により人々の投票行動に影響を与えようとしたケンブリッジ・アナリティカ事件なども想起される。
2020年の個人情報保護法改正の立法過程では、このプロファイリングを保有個人データに関する事項の公表等の対象に含め、プライバシー影響評価の対象とすることも検討されていたが、検討途中でその案は消えたようだ。
GDPRでは、クッキー等のオンライン識別子は個人データに含まれるし、プロファイリングも一定の規制下にある。EUではフィルターバブルやエコーチェンバーが起こっていないかと言うとおそらくそうではないだろう。GDPRでも報道について日本と同様に適用除外規定もある。それゆえ、法規制が根本的な解決になるわけではなさそうだ。とはいえ、少なくとも、GDPRでは、プロファイリングがどのように使われているかをデータ主体に対して明確かつ平易に説明すべきことになっているし、情報開示請求権や異議の申し立て権なども認められている。日本法とは大きな違いがある*。
ネットをとりまくフィルターバブルやエコーチェンバーという状況下で、情報に関する主体性を個人が回復するためにはどうすればよいか。良い処方箋が直ちに思いつくわけではないが、さしあたり、提供される情報については、情報の内容および入手経路の多様性を確保すること、情報の受け手側の問題としては、一人一人がリテラシーを高めることが肝要であろう。
情報内容の多様性確保としては、出所の確かな情報が広く流通するようにする基盤整備が重要だ。そのために有効な方法の一つは、立法、行政、司法に関連する情報の保存や公表、公開を進めていくことだ。たとえば、行政が自ら発表する情報のみ増やすことを意図しているのではなく、行政が意思形成過程で作成又は取得した情報や、発表の基礎となったデータなどを保存し、広く公表・公開すること(それらの情報やデータに対する第三者による検証可能性を確保すること)を念頭においている。
最近の「表現の自由」関連の判決として、映画「宮本から君へ」の助成金不交付に関連して出された東京地裁判決があった。判決文を読みたいと思ってネットで探したが、少なくとも本コラム執筆時では見当たらなかった。米国であればPACERにより、当事者が出した書面や証拠も含めて裁判資料を簡単に読むことができる。日本の司法関連の情報の取扱いは、裁判資料の保存から始まり、民事・刑事の各記録の公開に関して不十分であり、いろいろと問題を抱えている。
情報の入手経路の多様性確保としては、ネット以外における情報源の多様性確保が必須だろう。この点では既存メディアへの期待が大きい。これは、既存メディアが改善されることを含めての期待だ。速報性では新聞・雑誌はネットにかなわないので、調査報道などで存在意義を示していくことが求められるだろう。あらかじめ決まっている質問と回答をやりとりする記者クラブでの会見などは早く卒業し、意味のある情報をより多く発信してもらいたい。
上記に関連する公文書管理法のことやメディアへの期待については、「忘れないための覚書」というコラムでも昨年書いた。「宮本から君へ」に関連しては、福井健策弁護士のコラム「不祥事×作品封印論 ~犯罪・スキャンダルと公開中止を考える」もある。
市民による意見表明の場の確保も重要だ。この点に関するものとして、最近の「表現の不自由展」問題がある。大阪での会場利用をめぐって裁判になったが、裁判所の立場は明確だ。地方自治法244条2項が「正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない」と規定していることを受け、最高裁は、「主催者が集会を平穏に行おうとしているのに、その集会の目的や主催者の思想、信条等に反対する者らが、これを実力で阻止し、妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒むことができるのは、...公の施設の利用関係の性質に照らせば、警察の警備等によってもなお混乱を防止することができないなど特別な事情がある場合に限られる」と判示している(最判H8.3.15・上尾市福祉会館使用不許可事件)。今回の訴訟でも、裁判所は素早く対応した。
ここに関連するコラムとして、福井健策弁護士の「著しく不完全な『表現の自由』論争史~公開中止・会場使用許可・公金支出を中心に」がある。
情報の受け手側のリテラシーとしては、多くの人が、フィルターバブルなどがネットで進行していることを認識し、自分に示されている情報は歪みをもっている可能性があると自覚することが、まずはスタートだろう。その意味では、上述したクッキーやプロファイリングの仕組みの公表等を義務づける法制度の導入が有意義と思われる。とはいえ、具体的にどのような情報が欠落しているのかを知るのは不可能ないし困難である。事業者の自主的取り組みとして、たとえば、パーソナライズされていない場合にどのような情報が表示されるのか、モード選択で確認できる仕組みを提供してくれるウエブサイトなど現れないものかと思う。
一般的なリテラシーの向上としては、各人がクリティカルシンキングを持つことが必要であろう。この点に関して、耳が痛いがそのとおりという良記事に接した。今年2月のデービッド・アトキンソン氏による「『世界一寛容な日本』願望に近い」という記事だ(2021年2月23日朝日新聞朝刊)。クリティカルシンキング゙に関するくだりの一部は次のようなもの。
この記事はオリンピックに関する記述(日本では期待している人が多いが、オリンピックに経済効果は期待できないことなど)が中心だったため、掲載箇所はスポーツ欄だった。普段はあまりスポーツ欄を読まないが、新聞のページをめくっていてたまたま目に入った。そういったことが起こるのも、よく指摘されることだが紙媒体ならではのメリットだ。
NHK「100分de名著」が1953年の著作であるレイ・ブラッドベリ『華氏451度』の回で指摘していたが、「マスメディアの発展、社会のスピードアップ、内容の単純化、知性の衰退、学校教育の崩壊、人生そのものの単純化(仕事と消費)など、さまざまな要因が絡み合って」、ひとびとが知性を失い、本が読まれなくなる状況が進行する(同テキスト64頁)。これはディストピアを扱った小説だが、社会のスピ―ドアップ、わかりやすさが何よりも重視される風潮、リベラルアーツが軽視される大学教育など、いまの現実は、ここで指摘されている状況に近づいているように思える(『華氏451度』が著された当時の「マスメディアの発展」は、現代でも当てはまる部分もあるし、現代では「ネットやSNSの発展」をそこに加えることができるだろう)。
主体性をもって多様な情報に接し、そのうえで考えを巡らせるためには時間が必要となる(「知る権利」の前提となる「知る時間」だ)。人新世とも言われる時代である。あくせく働いたあげく、結果的に気候変動を助長することになる場合もあるだろう。それよりは皆でペースを落とし、時間や気持ちにゆとりのある暮らしに切り替えることも大切ではないか。そのうえで、ネットに向かう時間を少しでも別のことにあてる。たとえば、「今の世の中で正気を保つため」に文学を読むとかだ(平野啓一郎「文学は何の役に立つのか?」)。
以上
■ 弁護士 二関辰郎のコラム一覧
■ 関連記事
「ライフログ・行動ターゲティング広告とプライバシー(1)」
2010年2月 1日 弁護士 二関辰郎(骨董通り法律事務所 for the Arts)「著しく不完全な『表現の自由』論争史
~公開中止・会場使用許可・公金支出を中心に」
2019年10月18日 弁護士
福井健策(骨董通り法律事務所 for the Arts)「『ムーンショット目標1』達成の鍵を握る、サイバネティック・アバターの魅力と課題
~後編:空間・時間の制約から解放された場合 & サイボーグ技術~」
2022年2月28日 弁護士
出井甫(骨董通り法律事務所 for the Arts)
法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
※文章内容には適宜訂正や追加がおこなわれることがあります。