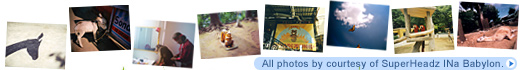2025年7月11日
「動きはじめた米国AI著作権判決と、
控えめにいって大騒動な米国AI著作権法論議の記録帳」(2025/11/19追記)
弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts)
米国で、AI学習と著作権をめぐる議論が一気に動き出しましたね。現在、30以上のAIと著作権をめぐる裁判が進行中ともいわれ、現時点で既に連邦地裁の判決が3つと、連邦著作権局の報告書(いわく付き)が出ています。
訴訟の焦点は多数ですが、最大のものはやはり「フェアユース」でしょう。事案によって、また裁判官の発想によって、現時点ではかなり揺れも見られ、人生論みたいな言い訳あり、2日前の同僚の判決を批判する乱闘ありと、そろそろメモがないとわかりづらい。自分が。
という訳で、これは単にTwitterでつぶやいたり取材に答えたりした内容の、記録帳です。自分のための。各判決の精緻な分析は、すぐれた論考が既に出ていたり今後(きっと)出されると思うので、そちらをご参照いただければ。
なお、これは私の、私による、私のための記録帳なので、万一誤りやアップデート漏れなどを発見した場合は、静かに私だけに耳打ちしてくださるのが大人の対応として推奨されています。私により。
① 2025年2月 ウェストロー訴訟(Thomson Reuters v. Ross Intelligence、2025年2月11日デラウェア連邦地裁)
2月、デラウェアの連邦地裁は、AIの学習データとして著作物を利用することの是非に関する初の判断(略式判決)をくだし、フェアユース(公正利用)を否定して著作権侵害を認めました。
原告は、我々にはなじみが深い判例検索サービス「Westlaw」を運営するトムソン・ロイター。被告はRoss Intelligenceという会社で、法律検索ツールを提供するため、Westlawの判例要旨を第三者経由で入手し、自社AIの学習データとして利用していました。なお、Rossのツールは新たな文章などは生成しないため、これはあくまで検索という、「非生成AIサービス」のための学習についての判断となります。
「フェアユース」とはざっくり言うと、4つの要素で著作物の利用が「公正」と判断されれば著作権者の許可がなくてもおこなえるという、米国の著作権法の特徴的な例外規定です。一部で誤解されるような「何でもあり」の規定とは違いますが、そのある種の柔軟さが、米国テック企業の1990年代以来の躍進の原動力のひとつとも指摘されます。
さて、フェアユースの4要素とは、①利用の目的と性格、②著作物の性質、③利用された量と重要性、④オリジナル作品の市場への影響、の4つです。このうち①については、対象となる利用が変容的(transformative)であるか否かが重視されています。
デラウェアの裁判所はこの点、RossのAIはWestlawの競合サービスであり、目的が同じであるから変容的とは言えないとしました。またこの際、トムソンの判例要旨はAI学習の過程で数値に変換されて内部的に利用されたに過ぎず(中間的利用)、Rossの出力には含まれていないというRossの反論も、上記結論を覆さないと退けています。
その上で、特に重要とされた④について、RossのAIがWestlawの市場での代替物になり得るという競合性を重視して、フェアユースを否定しました。またこの際、いまだにトムソンがおこなっていない、「AI学習用データのライセンス」という潜在的な市場への悪影響も考慮した点が特徴的です。
命令文:https://www.ded.uscourts.gov/sites/ded/files/opinions/20-613_5.pdf
本判決については、既に精緻な評釈が複数出ておりますので、詳細な検討はそちらに譲ります¹。まだ一例にしか過ぎないとはいえ、この裁判例は相当なインパクトがありました。なぜなら競合サービスに利用されることをほとんど決定打として、学習元の表現が(多少の類似物さえ)出力されないような無断のAI学習においても、フェアユースが広く否定され侵害とされる可能性を示したからです。
とはいえ、あくまで各判断はケースごとの解決であり、かつ、その後このフェアユースに関する判示部分などは部分控訴され、連邦控訴裁の受理判断待ちです(25年7月初旬現在)。
② 2025年5月 連邦著作権局の生成AIに関する報告書(プレ公開版)
2025年5月、米国の著作権行政を統括する議会著作権局は、「Copyright and Artificial Intelligence」という一連の報告書の第3部、「生成AI学習編」のプレ公開版(pre-publication version)を公表しました。そこでは、生成AIの学習過程における著作権問題、とりわけ著作物の利用やフェアユース適用の可能性、ライセンスの実務的課題などを包括的に分析しています。
報告書は113ページに及ぶ詳細な検討で、AIの訓練における著作物の様々な利用は、変容的(transformative)である場合が多いとはしつつ、学習自体は中間的利用なので許容されるという論には、それは最終的な出力目的しだいだとして否定的です。例えば、ニュース記事など取得した著作物の要約や短縮版を生成することを目的とするいわゆるRAGは、変容的とは言い難いと述べています(47頁)。
その上で、フェアユースゆえ適法といえるかどうかは、市場への影響に関わる他の要素の考慮が重要だとします。例えば、AIモデルが分析や研究目的で使用される場合、その出力は訓練に用いられた表現作品の代替とはならない可能性がある一方、商業的な目的で、大量の著作物を用いて、それらと競合する表現コンテンツを生み出す場合、とりわけ違法なアクセスによってそれが実現された場合には、フェアユースの既存の範囲を超え侵害になると明言しています。
特に、報告書が第4の要素「市場での影響」において持ち出した、「市場の希釈化(market dilution)」の論理(64頁以下)には、大きなインパクトがありました。報告書はここで、「原作の潜在的市場への影響」は狭く解釈すべきではないとして、AIがコンテンツを生成するスピードと規模は、学習されたものと同種の作品の市場を希薄化させる深刻なリスクをもたらすと明言しました。
その上で、例えばAIモデルが恋愛小説を学習し、その後、何千冊ものAI生成の恋愛小説が市場に出回れば、AIが学習に使った人間作の恋愛小説の販売数は減少するだろう、と警告しています。つまり、単なる盗作だけでなく、生成AIによる同一ジャンル・テイストでの膨大な作品の増加によってクリエイターが市場から締め出される恐れ、に言及したことになります。
報告書が、フェアユースに該当しない可能性のある利用に対しては、AI訓練用のライセンス契約などに期待したのも、大きく踏み込んだ点でしょう。現時点で政府による介入は時期尚早であるとしつつ、仮に学習用のライセンス契約などの実務が広がらない場合は、市場の失敗に対応するため、いわゆる拡大集中許諾(extended collective licensing=ECL)のようなアプローチを検討すべきと結論しました。
「拡大集中許諾」とは、特定の分野を代表する集中管理団体が、彼らに作品を委託などしていない権利の著作物についても許可を出し、使用料を徴収して分配する仕組みをいいます。
つまり、単に「許可を取れば良い」では現実のAI学習にとって非現実的であることは理解した上で(恐らく誰よりも理解した上で)、政府の関与により、大量の作品を公正な対価のもとで学習利用できる、仕組み作りに踏み出そうとする方向ですね。
なお、一連の報告書のこの部分はいわゆるプレ公開版であり、その直後に、何とトップであるシーラ・パールマター著作権局長はトランプ政権によって解任されています²。この点、政権の推して来たAI産業にとって、商用目的でのAI学習に許諾が必要とする報告書の内容は相当なブレーキですから、著作権局長の解任は明らかにそれと関連している、という受け止めと批判は少なくありません³。
2025年7月初旬現在、今もって報告書この部分の正式版は公開されておらず、正式な後任の著作権局長も確定しておらず、それ以前にパールマター氏は自身の解任の無効を訴えて米政府を提訴しており、先行きは控えめに言って不透明です。もっとも、トランプ政権下の米国政策で、不透明でないものが果たしてあるかは疑問ですが。
③ 2025年6月 アンソロピック訴訟(Bartz et al v. Anthropic、2025年6月23日北カリフォルニア連邦地裁)
上の①②が矢継ぎ早に出てフェアユース否定の流れが強まるかと思われた6月、AI企業のお膝元である、北カルフォルニアの連邦地裁は一見して真逆の判決を出しました。生成AI企業「アンソロピック」による書籍の学習の違法性が問われた裁判で、初めて、生成AIの生成物の著作権侵害性を判断した略式判決であり(ウェストロー判決は非生成系)、初めてフェアユースを認めた判決ともなりました。
また、この裁判にはややトリッキーな部分があり、AI学習じたいは変容的でフェアユースと認める一方、アンソロピックが学習のために700万冊以上の書籍をストレージしたことは侵害としています。その結果、12月の審理によって同社は高額の賠償額を命じられる可能性があります。
このケースでは、①内部ライブラリーを構築するために、700万冊以上の海賊版書籍をダウンロードしたことと、数百万冊の古書を購入後にデジタル化したことがフェアユース(合法)か、②そのライブラリーから書籍データをセレクトし加工して学習用データセットを作成し学習させたことがフェアユース(合法)か、が問われました。
Alsup判事は、①の「保存」のうち海賊版書籍のダウンロードは、フェアユースに該当せず違法、購入書籍のデジタル化は、データが外部提供されず原書籍も廃棄されたことなどを理由にフェアユースに該当する、と判断。違法部分は、保存が汎用目的だったことが重視されていますね。恒久的保存であったことも考慮はしていますが、判決全体を読むと汎用目的であることがより重視された印象か。
他方、②の「学習」については、学習によって誕生する生成AI「Claude」は、学習された文章を模倣するような生成はおこなわないこと等から変容的であり、彼らのAI生成物は市場で原書籍に代替しないことからフェアユースである、と適法判断。
侵害と判断された700万冊超の海賊版ダウンロードについては、今後12月に賠償金の審理がされるとの報道ですが、法定賠償金といって1作品最大15万ドルで裁判所が認定する賠償金額が命じられます。最大だと700万冊×15万ドル=1兆500億ドルなので、潜在的な最高額は150兆円を超えますか。まあそんなことにはなりませんが、この1作品の賠償金額も注目でしょう。
海賊版からのAI学習は相当に多い可能性があり、私も委員で加わった文化審議会「AIと著作権に関する考え方」報告書でも「厳に慎むべき」とされた点と関連しますね⁴。では、適法にアップロードされた作品を単に無許可でダウンロードした場合や、AI学習した後ですぐにデータを廃棄した場合は侵害なのかフェアユースなのかといえば、それは他のケースに委ねられるか。
いずれにしても、学習用データについて一定の拘束をかけようとした点、類似した表現を出力することを目的としていない以上は「変容的」であり市場での打撃はないとして、ウェストロー裁判や著作権局報告書が否定した「中間的利用は許される」論に近い立場をとった点などは重要で、まだまだ米国裁判例の方向は決定づけられていないことを示しました。
判決文: https://cases.justia.com/federal/district-courts/california/candce/3:2024cv05417/434709/231/0.pdf
④ 2025年6月 Meta訴訟(Kadrey v. Meta Platforms 北カリフォルニア連邦地裁、2025年6月25日)
生成AIの学習にフェアユースを認めたアンソロピック判決のわずか2日後、同じ北カリフォルニア連邦地裁の別な判事は、Metaの生成AI「Llama」の著作権訴訟でやはり結論としてはフェアユースを肯定する略式判決を出しました。
ただ、ざっくり読むとこれは・・・すでに解説を書いた方もいるかもしれませんが、一部報道されたようなフェアユース肯定の2つめの判決、とは本質が違いますね。むしろ真逆に近い部分がありそうです。
まず、判決の冒頭5ページで、このChhbria判事は基本的な立場を明確にしています。以下のような理由により、「著作物を著作権者の許可を得ることなく、また報酬を支払うことなくAIモデルに投入することは、大多数の場合は違法である」と。
・フェアユースは、著作権者が作品から利益を得る能力を著しく損なうような行為には通常適用されない
・たとえ変容的であっても、原作品の市場に深刻な打撃を与え、人間の創作インセンティブを損なう製品を生み出すために作品が学習されるケースはあり得るとして、(②の著作権局報告書と同様の)恋愛小説やスパイ小説を例示
・アンソロピック判決がいう「書籍を用いて子どもたちに文章を教えること」と、「一個人が無限に競合作品を瞬時に生み出せる製品を作ること」という例はたがいに全く異なり、並べるのは本質的に見当違い(!)
・仮に著作権で保護された作品を訓練に使うことが企業にとって本当に不可欠であるならば、彼らは必ず著作権者に対価を支払う方法を見出すので開発は害されない
その上で、以下のように本件の個別判断を展開します。
・フェアユースの最も重要な判断要素は原作品の市場がいかに損なわれるかであるところ、原告は2つのみ主張した:①Llamaが彼らの書籍の断片を再現する能力を持つ点、②著者が自らの作品をAI訓練用データとしてライセンス提供する能力が損なわれた点。そして、いずれも立証に失敗した
・勝つ可能性のあった主張は、Metaが原告作品を学習して、似た作品で市場をあふれさせる製品を作ったため市場が希釈されたという点にあるが、原告はこの点をほとんど論じておらず希釈化の証拠を提出しない
・よって、本件ではフェアユースを認めるほかない。ただし、全体として見れば、この判断の影響は限定的で、原告13名のみに適用される。Metaによる著作物の使用が合法であるという判断ではない。単に、原告が適切な主張と立証をし損ねたにすぎない
踏み込みましたね。無論、この後の変容性や市場での打撃の個別判断も重要なのですが、むしろ「いくら変容的な生成でも、市場で原作品の価値を希釈化させる場合にはフェアユースは成立せず、大多数はそうなる」と述べている点が、最大の特徴とも言えそうです。これは、②の連邦著作権局報告書の「希釈化論」にほぼ完全に乗ったロジックといえます。他方、では「希釈化」とはどの程度のことを言うのかはまだわからず、今後ともいえる。
さて私は、この「希釈化」論じたいはあり得るという立場です。他方、裁判所がいった「許諾が必要となっても、企業は必ず著作権者に対価を支払う方法を見出すので開発は害されない」という点については、権利処理の苦労を知らないのだろうな・・・と思います。
以上、やはり生成AIの米国著作権判決は一筋縄ではいきませんね。ただ「どの程度であれば原作品への市場での打撃か」という本質論に、かなり焦点があたって来たとは思えます。ごく不完全ですが、これまでの4つの判断・意見を表にしてみましょう。
| AI学習は侵害か | AI学習は変容的か | AI学習での中間的利用は許容されるか | AI生成物は市場でオリジナルに代替するか | |
| ウェストロー判決 | 侵害 | 否定 | 否定 | 肯定 (競合サービスゆえ) |
| 連邦著作権局報告書(プレ公開版) | 商業目的、特に違法なアクセスがあった際には侵害 | 肯定的 | 否定的(出力目的を重視) | 肯定的 (市場の希釈化論) |
| アンソロピック判決 | 学習自体は非侵害 海賊版を汎用目的でコピーした点は侵害 |
学習自体については肯定 | 学習自体については認める | 学習自体については否定 (類似表現を出力せず) | メタ判決 | 本件は非侵害 しかし多くの場合は侵害 | 肯定か | 触れず | 肯定的(一般論として市場の希釈化論を認める) |
今後も、これらの裁判の上訴審、更に進行中の多くの著作権裁判が、連邦著作権局の報告書やこれら先行する判決の影響を受けつつ展開されて行くでしょう。そこでは「類似の表現を出力しない中間的利用の評価」「同種の作品の氾濫による市場の希釈化をどう見るか」「許諾を得るための市場システムの可能性」が大きな論点となって行くように思います。
いずれも、これまでの日本での2つの大きな検討会議⁵での議論と大きく重なる論点ですね。この辺も掘り下げて論じたいところですが、それはまた追って。
¹ 奥邨弘司「機械学習と著作権のフェア・ユース――Thomson Reuters v. Ross Intelligence」商事法務『NBL』1289号(2025年5月1日)、松﨑由晃「AIの学習データ利用について著作権侵害を認めた米国連邦地裁判決―Thomson Reuters v. Ross Intelligence事件―」https://www.noandt.com/wp-content/uploads/2025/02/technology_no58_1.pdfほか
² 上司にあたるカーロ・ヘイデン米議会図書館長の解任の直後。
³ Tor Constantino, U.S. Copyright Office Shocks Big Tech With AI Fair Use Rebuke, Forbes May 29, 2025ほか
⁴ 2024年3月15日付同報告書27頁以下。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/aiandcopyright.html
⁵ 前述「AIと著作権に関する考え方」、及び内閣府知財戦略本部「AI時代の知的財産権」検討会議中間取りまとめ
(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/ai_kentoukai/kaisai/index.html)
以上
【2025/7/23追記】米国で、明確な本人同意のない個人情報と著作物の学習を全て不法行為とし、賠償請求を可能にする法案が提出され、話題ですね。無論、注目すべき動きですが、ただ、この法案がそのまま成立する可能性は恐らく低いかと思います。
まず、これはまだ委員会審議段階で、米国では提出法案の成立率は1%程度しかないのですね。また著作権については、本文の通り、現在AI学習をめぐる多数の裁判が進行中とされ、まだまだ帰趨はこれからです。言えるのは、「完全な学習禁止」と「完全な学習自由」のいずれに収束する可能性も低い、ということ。その収束の方向を見て、法案を作ろう(修正しよう)とするのが一般の議員の発想でしょう。
まして(現在のところAI推進を崩していない)トランプ政権の拒否権発動も予想される中で、両党2名の提出案とはいえ、共和党の造反はやや予想しにくいですね。
【2025/9/6追記】コラム③のアンソロピック訴訟が2200億円で和解合意、と報じられました。著作権訴訟の和解額としては、史上最高額か。
クラスアクションで必要な裁判所の承認はこれからですが、海外メディアも「作家側の勝利」など一斉に書き立てています。本文で書いたように、米国には法定賠償というルールがあり、1著作物あたり最高15万ドルの賠償を裁判所は命じられます。700万冊ですから、理論上は兆単位の賠償額も十分あり得た。経営危機を回避するため、分割での2200億円を呑まざるを得なかったのかもしれません。
AI学習のためのどのダウンロードまでが侵害かは今後の裁判に委ねられます。
アンソロピックは「学習じたいはフェアユースと認められた」とアナウンスしたようです。が、他の2判決は競合物のための学習じたいも原則は侵害と述べる中、学習によほどの安全措置を施さないと生成AIへの投資に二の足を踏む投資家も増えそうです。まだまだ高裁の動向しだいではありますが、世界のAI開発をリードした米国AI産業界は大きな局面を迎えたかも、しれません。
【2025/11/19追記】米国の裁判そのものではありませんが、その帰趨に重要な影響を及ぼしそうな他国の裁判や動きが続いているため、備忘的に記載しておきますね。教えてくださった皆さんに感謝。
まず、各国でのAI関連の著作権裁判の頻発ぶりと帰趨は、ChatGPT is Eating the Worldという痺れる名前のこのサイトに詳しいですね。下の方に世界裁判マップがあります。なんというか、執念がすごい。
2025年10月には、③のMeta裁判で問題となった「希釈化≒市場での代替性」にとって重要な実証研究論文が、J・ギンズバーグ教授ら著名な研究者によって発表されました。
それによると、AIが有名作家の文体(スタイル)をファインチューニングによって模倣した場合、専門家・一般読者ともに人間が書いたものよりAI生成文を明確に好む結果となった。すなわち、市場においてAI生成物には人間作家に対する代替性が認められる。
その結果、このようなファインチューニングによってLLMを生み出す行為はフェアユースに該当しないと結論しています。他方、特定著者を対象としないLLMは、様々な用途に使えるため、市場希薄化リスクが低くフェアユースの主張はより強いと述べています。
同じ2025年10月、クリエイティブ・コモンズに続き、Wikipediaを運営するウィキメディア財団が生成AIに対する強い意見表明をおこなっています。これは記事の無断スクレイピングとAI生成記事によって、元の記事閲覧が減少したというものであり、やはり市場での代替を裏付ける主張といえるでしょう。
更に11月、財団はWikipediaの継続性に危惧を表明し、有料APIの利用による財政支援と適切な出典表示を求めています。ネットカルチャーや集合知の代名詞的存在による訴えだけに、影響は小さくないかもしれません。
続いてドイツです。11月、ドイツ・ミュンヘン地方裁判所はドイツ版のJASRACであるGEMAがOpenAIを訴えた事件で、OpenAIに賠償を命じました。同社が賠償を命じられた初の判決とされますね。
判決原文は未見ですが、こちらの解説が比較的緻密で、注目はその中で裁判所が長らく指摘されて来たAIによる学習データの記憶(memorization)を認めた点。つまり、現に簡単な指示で出力においてそっくりの歌詞が出力される以上、とりもなおさずAIのパラメーターは学習されたデータのコピーであるとし、ChatGPTによる出力は「更なる複製および公衆送信」を構成し、無許可利用だと結論づけています。テキスト・データマイニングを許容するEU著作物指令などについては、問題の歌詞の再現が情報評価の域を超えており、対象外との判断。
そっくりの表現を出力する行為はChatGPTなどOpenAIの製品ではいまだに見られますが、そうした場合に当初の学習も侵害になり得るという点は、日本や米国での主流の理解も一致しています。そしてこの点はOpenAIという世界のAIトップランナーの、恐らく大きなリスク要因でしょう。ただそれを「(再現できる以上)AIは学習データを記憶している」と整理した点は、技術的・法的双方で興味深いと感じます。
■ 弁護士 福井健策のコラム一覧
■ 関連記事
米国ロースクール留学日記
-ミシガンの小さな街から-
2025年8月27日 弁護士
寺内康介(骨董通り法律事務所 for the Arts)「概説AI法」
2025年9月24日 弁護士 小山紘一(骨董通り法律事務所 for the Arts)
法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
※文章内容には適宜訂正や追加がおこなわれることがあります。