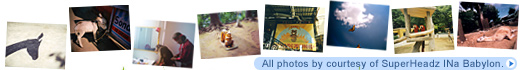2023年8月30日
「AI著作権ほかをめぐる~日独法比較レクチャー@デュッセルドルフ」
弁護士 橋本阿友子 (骨董通り法律事務所 for the Arts)
5月初旬、私はミュンヘンから電車で1時間ほどにある、日本とも縁の深い街、アウグスブルクにいました。ドイツ人法律家による日本法のレクチャーが聞けるというので、誘われて聴講に行ったのですが、そこで日本人の弁護士(ドイツ資格)の先生からお声がけいただいたことがきっかけで、Heuking Kühn Lüer Wojtekのデュッセルドルフ事務所にて、日本の著作権法についてお話する機会を持ちました。留学日記第3話は、8月21日に行われたレクチャーの内容の一部をご報告したいと思います。
レクチャーは、AIに関する内容を含めてほしいとのご要望に沿い、”Basics and structure of Japanese Copyright in comparison with German Law including the current discussion about the role of AI in Japan”というタイトルで行われました。レクチャー自体は、日本法を主軸に行いましたが、下記では、ドイツ法との比較のみに焦点をあてたいと思います。
●「著作権」の位置づけ
言わずもがな、日本法で「著作権」は、経済的権利。著作権法は、著作者に著作権を与え、著作物からその利益を回収できるようにすることで、著作者を保護しています。「著作権」は経済的権利であるため、譲渡、相続による承継が可能です。また、著作者は、「著作者人格権」という権利も有しています。これは文字通り人格権なので、性質上譲渡はできず、また相続の対象にもならないと考えられています。
以上が日本法ですが、ドイツ法は、著作権に対する考え方が、日本法と根本的に違います。ドイツ法は、11条で、「著作権は、著作者を、その著作物に対する精神的ならびに人格的な関係および著作物の利用において保護する」と規定しています(前段)1 。ここでいう「著作権」とは、人格的(精神的)機能と財産的機能が不可分に一体化した権利として構成されているのです。このように、ドイツ法でいう「著作権」(Urheberrecht)は、日本法でいう「著作権」とその中身が異なることから、ドイツ法では「著作者権」と呼ぶ方が、両者の切り分けがしやすいと考えられます。ですが、以下では便宜上、いずれも「著作権」と表記することとします。
●「著作権」の譲渡
上記のとおり、ドイツ法のいう「著作権」は人格的要素を含む権利として捉えられていることから、ドイツ法では「著作権」を譲渡することはできません。29条1項では、明確に、「著作権は、譲渡することができない」と規定されています。もっとも、相続の場合は別であることが、同項但書で規定されています。
とはいえ、ドイツでも、著作者自らしか「著作権」の行使ができないというわけではありません。29条は2項で、「使用権の許与(第31条)、利用権2に関する債権的な同意及び合意並びに第39条に規定される著作者人格権に関する法律行為は、許される。」と規定しています。つまり、著作者は、第三者との合意により、著作権を行使する権利を与えることができるのです。
この利用権の許与は、個別の利用方法をも全ての利用方法をも対象とすることができ、また、場所・時間・内容を限定したり、非排他的・排他的の別をも選択することができます。
●職務著作制度
また、「著作者」に関する規律の違いとして、職務著作制度があります。職務著作とは、日本法において、①(法人などの)使用者の発意に基づいていること、②その使用者の業務に従事する者が職務上作成すること、③その使用者の名義のもとに公表すること、④作成時に契約、勤務規則等に別段の定めがないこと、という要件を満たした場合には、著作物を物理的に作成した人(従業員)ではなく、使用者が「著作者」となるというものです(15条1項)。一旦作成者に権利が発生してそれが使用者に移転する、という建付けではないので、経済的権利の「著作権」だけではなく「著作者人格権」も使用者が持つことになるのです。反対に、職務著作が認められてしまうと、物理的な作成者は、自分が作成した著作物に対して、何にも権利を持てない、という結果となります。
他方、ドイツ著作権法は、2条2項で、著作物を「個人的かつ精神的な創作のみをいう」と定義しています。つまり、「著作権」は、個人(自然人)にのみ与えられると考えられており、会社といった自然人以外による著作物の創作を観念できません。そのため、その帰結として、日本のような職務著作制度は定められていないのです。もっとも、ドイツ法も、43条においては、「この款の規定は、著作者が雇用関係又は職務関係から生ずる義務の履行において著作物を作成した場合においても、その雇用関係又は職務関係の内容又は本質から格別の事情が生じないかぎり、適用するものとする。」と定めており、一定の範囲での職務著作が認められるとも評価できます。ただし、ドイツ法では、つまるところ雇用契約や労働契約など使用者と被用者間の契約によって、上記〔●「著作権(者)権」の譲渡〕で述べた、(排他的)利用権を付与できる、という内容にとどまっていると解釈されてます3。
(ちなみに、日本法では、従業員の著作物にかかる行為について、15条はあえて、「創作」ではなく「作成」というワードを使っており、従業員は創作者ではないことを前提とした規定となっています。)
●権利制限規定のアプローチ
また、権利制限規定についても、少し触れました。権利制限規定は、本来は必要な著作権者の許諾なく第三者が著作物を利用できる場合を定めた規定ですが、日本では、多くの権利制限規定が、無許諾にとどまらず、無償で著作物を利用できる場合として定めています。しかしながら、ドイツ法では、「著作権は、著作者を、その著作物に対するその精神的かつ個人的な関係において、及びその著作物の使用において、保護する。著作権は、同時に、著作物の使用に関する相当なる報酬の保障にも寄与する。」と定めており、権利制限規定は、基本的に有償での利用を定めています。もっとも、日本でも、最近の改正では、権利制限規定を拡充して利用を促進しつつも、補償金の支払いを条件とする規定が増えてきている傾向にあります。その意味で、ドイツ法との差異は縮まっていくのかもしれません。
●AI生成物への保護
ドイツ著作権法が「著作権」を個人にのみ付与される権利と捉えていることから、昨今各国で議論されている、「AIが生成した物が十分創作的であった場合に、当該生成物が著作権法上保護されるか(保護されるとすれば、誰が権利者か)」という論点については、AIは個人ではないため、ドイツ著作権法はAI生成物を保護しない、という結論が自動的に導かれます。この点、日本では、AI生成物の保護について、「思想又は感情」の表現にあたるのかという観点から議論がなされており、AIが自律的に生成したものは、人の「思想又は感情」が欠如していることから、著作物に該当しないと考えられています4。個人以外の著作者の存在を認めている日本と、それを認めていないドイツですが、この点に関する結論は概ね同じとなっているようです。
●TDMの可否
AIに関する最近の議論を…というお題をいただいたので、TDM(テキスト・データマイニング。大量の文章(テキスト)データから、有益な情報を抽出すること)の規律の違いについても触れてみました。日本法には30条の4という規定があり、情報解析の目的で著作物を利用することは、広く認められています。もっとも、30条の4で認められる利用は、「必要な範囲」にとどまり、また、「著作権者の利益を不当に害する場合」には、適用されない、と明記されている点について、注意が必要です。
他方、ドイツ著作権法は、EU指令をほぼ忠実に国内法化していますので、ここではTDMについて定めるDSM指令(デジタル単一市場における著作権指令)5 を比較対象に挙げたいと思います。DSM指令では、第3条で、TDMにおける著作物利用についての著作(者)権保護の例外を定めていますが、学術研究目的における研究組織や文化遺産機関による利用であること、適法にアクセスできる著作物であることが要件となっており、利用方法は複製及び抽出、学術研究目的での保持に限られています。
また、DSM指令は、第4条で、著作物を利用できる例外的場面として、TDM目的による利用を認めていますが、やはり適法にアクセスできる著作物であることが要件となっており、利用方法も、複製及び抽出、並びにデータマイニングに必要な期間における保持に限られています。さらに、権利者にはオプトアウトの権利が与えられており、権利者がTDMによる自己の著作物の利用を拒んだ場合には、この規定が適用されません。
上記DSM指令との比較において、日本法のTDM規定のポイントとしては、下記が挙げられます。
①非商業的な科学研究だけでなく、商業的な取引や活動にも適用される
(-したがって、オープンAIやスタビリティAIなどの事業会社において、オプトアウト抜きで著作物を利用することができる)
②権利者は日本の法律では商業利用でもオプトアウトができない
(-したがって、TDMに関して権利者がオプトアウトしているかどうかとは無関係)
③利用方法に制限がなく、複製を超えてデータセットの配布や公衆への伝達も可能
(-EU指令が認めているのは複製)
④適法アクセス要件がない
(-EU指令が認めるのは合法的にアクセス可能な著作物の利用)。
こうやってみると、確かに日本は、30条の4という規定のおかげで、機械学習パラダイスとも解釈できるでしょう6 。
現時点で、EUでは、AI Act案が欧州議会で承認されたばかりで、そこでは、権利者の権利を保護するための、透明性の要件などが定められています(出井弁護士のコラム参照)。
日本法30条の4も、利用は「必要な範囲」に限られ、また、但書で、「当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合」には、TDMによる著作物利用を認めないと定めていることから、著作権者の利益よりAI学習を完全に優先しているわけではありませんが、AI学習にとっての制限は、EU法に比べて少ないといえるのかもしれません。
こうやって諸外国の法律と比較すると、我が国の特徴や哲学がみえてきて、むしろ日本法の勉強にもなったように感じています。

Heuking Kühn Lüer Wojtekデュッセルドルフ事務所のオフィスにて。
末尾になりましたが、本レクチャーには、独日法律家協会の皆様にお集りいただきました。このような機会を設けてくださった金子浩永先生をはじめ、関係者の方々、聴講してくださった方々には、この場を借りて御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。
以上
■ 弁護士 橋本阿友子のコラム一覧
■ 関連記事
「マックスプランク留学日記-第2話:非営利・無償…有償の演奏?」
2023年5月30日 弁護士 橋本阿友子(骨董通り法律事務所 for the Arts)「マックスプランク留学日記ー第4話:
ドイツで出版社の権利を考える―楽譜の模倣が争われたケースを契機に」
2023年11月27日 弁護士
橋本阿友子(骨董通り法律事務所 for the Arts)
法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
※文章内容には適宜訂正や追加がおこなわれることがあります。