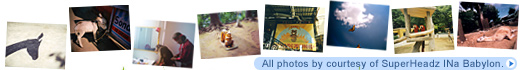2025年3月26日
「デザイン・クリエイティブ業界における著作権譲渡に関する解説
-著作権譲渡の申し出に対する検討・交渉ポイントとは-」
弁護士 田島佑規 (骨董通り法律事務所 for the Arts)
■フリーランス法による取引条件の明示と著作権譲渡
2024年11月にフリーランス法(正式名称「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)が施行され、フリーランスに業務委託をする際には、テキストによる取引条件の明示が義務化されました(同法3条)。
これにより従前は口頭発注などで業務依頼がなされていたという個人のデザイナーやクリエイターの方々も、クライアントから発注書や契約書など取引条件が記載されたテキストの提示を受けることが増加しているのではないでしょうか。実際に私の下にも発注書や契約書の記載内容に関するご相談が多くなっている印象です。
その際、ご相談内容の上位を占めるのが、本コラムタイトルにもある著作権譲渡に関するものです。これまで明確に著作権譲渡の申し出は受けていなかったところ、突然クライアントから契約書がでてきたと思ったら、「制作物に関する著作権(著作権法27条及び28条の権利を含む)その他一切の権利については、納品完了時に受注者から発注者に移転する。」といった記載が存在し、どう対応すればよいでしょうか?などといったご相談ですね。
今回のコラムでは、こうしたクライアントからの著作権譲渡の申し出に対して、その受け入れの可否をどう検討し、どう交渉していけばよいのかにつき簡単にまとめていきます。
■著作権譲渡により生じる主な4つの影響
まず著作権譲渡に関して受け入れの可否を検討するには、その意味するところを理解することが重要です。
そもそも著作権とは、著作物の創作者に発生する権利であり、一言でいえば「私に無断で私の作品(著作物)を利用するな!」といえる権利です。例えば、クリエイターであるXさんがクライアントであるY社の依頼を受けて、『骨董小僧』というキャラクターデザイン(以下『骨董小僧』といいます)を制作したとします。仮にXさんが『骨董小僧』に関する著作権をY社に譲渡すれば、以後、「私に無断で『骨董小僧』を利用するな!」といえるのは、著作権を有しているY社ということになります。よって、Y社は他人が無断で『骨董小僧』を利用していれば著作権侵害を主張しその利用をやめさせることができますし、「『骨董小僧』を利用したいのであれば、使用料を支払え!」などということもできます。
このことは創作者であるXさんに対しても同様です。すなわち、①別途契約書などで取決めを行わない限り、Xさんが自己の実績紹介として『骨董小僧』をWeb上で公開したり、営業資料に印刷して配布したりする場合であっても著作権を有しているY社に無断で行うことが基本的にできず、利用のためにはY社の許諾がいるということになります。
(特に駆け出しのデザイナーやクリエイターの中には、今後の営業活動などを考えて、実績として紹介できるのであれば多少金銭面などの条件が悪くても業務を受けようかなどと考える方もいるかと思いますが、その際には制作物を実績紹介として自由に利用できるのかが重要なポイントになってくるかと思いますので、この①の点は特に注意する必要があるでしょう。)
また、②今後、Xさんが他のクライアントの案件を行うにあたりY社の許諾なしには『骨董小僧』と同一のキャラクターデザインを用いることはできず、また『骨董小僧』と著作権侵害が認められる程度に類似するキャラクターデザインを用いることもできないということになります。今回の『骨董小僧』はY社のために新規に制作するオリジナルキャラクターということであれば、この点は影響が少ないかもしれませんが、例えばデザイナー自身が自己の制作物を特徴づけるものとして継続的に使用している具体的なデザイン(今後他のクライアントの案件でも使用していきたいと考えているデザイン)があったとして、そのデザインの著作権を譲渡してしまうと、今後そのデザインを他のクライアントの案件で利用することが制限されるということになります。
さらに、③著作権を有している者は、別の者にその著作物を自由に利用させたり、著作権自体を譲渡したりすることができるため、Y社が別のZ社に『骨董小僧』に関する利用許諾を行い(または著作権譲渡を行い)、気がついたらY社ではなくZ社が『骨董小僧』を利用しているということもあり得ます。
他にも、④著作権を有している以上、Y社は契約時点で想定されていた媒体と異なる媒体においても、Xさんの事前確認など必要なく自由に『骨董小僧』を利用することができます。また次に説明する「著作権法27条及び28条の権利」の併せて譲渡していたり、著作者人格権不行使の合意をしていたりする場合には、Y社はXさんの事前の確認など必要なく自由に『骨董小僧』の別カットの制作、色変更、ポーズ変更など改変を加えた上で利用することもできるようになります。
まずは以上のような著作権譲渡により生じる影響を理解した上で、著作権譲渡の申し出に対する受け入れの可否を検討することが必要です。なお、以上はいずれも契約において異なる定めをすることは可能です。すなわち、例えば、著作権譲渡はしてもよいが、著作権譲渡後もXさんは自己の実績紹介として当該著作物を利用することは可能である旨の合意をすること(上記①の影響に対する対処)や、Y社は『骨董小僧』の利用許諾や著作権譲渡を第三者に行ってはならない旨の合意をすること(上記③の影響に対する対処)などは可能であり、少なくともそうした契約上の義務はY社には生じます。ですので、著作権譲渡を受け入れたとしても、何か追加で交渉・合意しておくべきことはないかを検討することも重要です。
■著作権法27条及び28条の権利と著作者人格権不行使
著作権譲渡が規定される場合、「著作権(著作権法27条及び28条の権利を含む)を譲渡する」などと記載されることがあります。この著作権法27条及び28条の権利とは、著作物をそのまま利用するだけでなく、その著作物に修正や変更など新たな創作性を加えて別の著作物(「二次的著作物」といいます)を創作したり、その二次的著作物の利用したりする場合の権利のことをいいます。
なぜわざわざ「著作権(著作権法27条及び28条の権利を含む)」などと記載されるかというと、この権利は単に「著作権を譲渡する」と記載しただけでは譲渡されず創作者に残ったままと推定されてしまうからというのがその理由になります(著作権法第61条2項)。
したがって、著作権譲渡自体はよいが、クライアントが著作物に対して修正や変更など新たな創作性を加える形で利用することは認めたくないと考える場合には、この「著作権法第27条及び第28条の権利を含む」という文言を削除する必要があります。
また著作権譲渡には、「著作者人格権を行使しないものとする」という内容(いわゆる「著作者人格権不行使特約」と呼ばれるもの)が併せて定められることがあります。著作者人格権とは、著作権以外に著作物の創作者に発生するもう一つの権利であり、著作権とは異なり譲渡することはできないものとされています。著作者人格権の内容を簡単に説明しますと「私に無断で著作物を最初に公表するな!」(公表権)、「著作物を利用する際には私の指定した名前を表示せよ!(または何も表示するな!)」(氏名表示権)、「私に無断で改変するな!」(同一性保持権)といえる権利です。
クライアントとしては、著作権譲渡を受けたとしても、この著作者人格権が創作者に存在することにより著作物の自由な利用を一定の範囲で制限される可能性があるため、創作者に対して、著作権譲渡に加えて、この著作者人格権を不行使とする旨の同意を要求することが実務上は多々見られます。
著作者人格権不行使に同意するということは、以後、その著作物が利用されるにあたり、自分の名前を記載してくれと要求することや、私に無断で改変を加えることはやめてくれと要求するといったことができなくなります。上記のケースだと、Y社(あるいはY社が指定する第三者)が、『骨董小僧』を利用する際に創作者であるXさんの名前を表示するかどうかを自由に決められる、あるいは、『骨董小僧』に別の服装をさせる、色を変える、別のポーズをさせるなどの改変も自由にできるということになります。
こうした著作者人格権不行使の受入れが難しい場合には、こうした条項自体を削除する、あるいは、権利ごとに個別に別段の定めを設ける(例えば、氏名表示権であれば「Xさんは、Y社またはY社が指定する第三者が『骨董小僧』を利用する際には、Xさんの氏名等をXさんが指定する態様において表記するよう求めることができる。」など)が対応策として考えられます。
■著作権譲渡と対価
ここまで著作権譲渡をした場合の影響面を主に記載してきましたが、著作権譲渡の申し出に対する受け入れの可否を検討するにあたっては、著作権譲渡に見合う対価(そうした著作権譲渡による影響を受けても釣り合うほどの対価)が得られているかを検討する必要があります。(なお、対価の中には、単に金銭だけでなく、その案件に携わることにより得られる経験や実績などもあり得るでしょうが、以下では金銭による対価を念頭において記載します。)
クライアントから著作権譲渡を求められる際の対価は、制作や納品時に一定の金額が支払われるのみで、その後の利用などについて追加対価は発生しない(いわゆる買い切り)とされていることも多いかと思います。(なお、著作権譲渡の場合の対価は、必ず買いきりになると誤解されている方も多いですが、仮に著作権譲渡とした場合でも、その対価は制作や納品時に一括で貰うだけでなく、例えば、今後当該キャラクターによりクライアントが得る収益の●%を著作権譲渡の対価として支払うというようにロイヤリティ(印税)形式で対価を定めることも可能ではあります。)
著作権譲渡で、かつ、買い切り形式の場合には、最初に受け取る対価のみが著作権譲渡の対価(すなわち前述した著作権譲渡による影響が生じる対価)ということになり、以後、当該著作物がどのように利用されたとしても原則として追加対価を要求できる余地もなくなりますので、当該対価で著作権譲渡をしても問題がないかを十分に検討する必要があるでしょう。
またデザイナーやクリエイターの中には、クライアントが著作物を契約時に想定されていた媒体とは異なる媒体などで利用することや、デザイン変更や色変更など改変を加えて利用(以下これらを想定して「二次利用」といいます)する際には、別途、自身に制作や監修依頼がなされるだろうから、その際に追加対価をもらえばよいと安易に考え、特に追加対価のような話をせずに著作権譲渡の合意をしているケースも散見されます。しかし、前述したとおり、著作権譲渡を行っている以上、クライアントは契約時に想定していた媒体以外でも当該著作物を自由に利用することができ、また著作権法27条及び28条の権利も含めて譲渡し、著作者人格権不行使の合意も行っているような場合には、クライアントは著作物を自由に改変して利用することもできるため、二次利用時に別途自身に依頼がくることは全く保証されていません。
したがって、著作権譲渡は受け入れるが、クライアントによる二次利用時には追加対価を得たい、または、別途自身に依頼をしてほしいなどと考えている場合には、事前にその旨を契約書等で定めておく必要があります。
■利用許諾(ライセンス)という選択肢
以上のような観点から著作権譲渡(著作者人格権不行使も含む)を受け入れることが可能かにつき検討する必要があります。仮に著作権譲渡を受け入れることができないと判断した場合には、自ら制作した著作物をクライアントに利用させる方法として利用許諾(いわゆるライセンス)を行うことになるでしょう。例えば、前述したケースであれば、XさんからY社に対して、『骨董小僧』を利用してよい範囲をあらかじめ具体的に定めた上で、当該範囲内であれば自由に利用をして構わないが、当該範囲を超えて利用をする場合には二次利用等に該当するとして、別途Xさんの事前の許諾や追加の対価の支払いを必要とするといった内容です。
利用許諾に関する契約書における実際の規定方法やそのポイントについては、以前の私のコラム「デザイン分野における契約書作成・交渉のための基礎知識-業務委託契約書のひな型を題材に各条項のポイントを解説-」に掲載した契約書ひな型の第5条(権利の帰属)【著作権譲渡を行わない場合(利用許諾の場合)の一例】の条文例及び解説などを参考にしていただけたらと思います。
■交渉時において意識すること
クライアント側としては、あまりその必要性などを深く考えずに「著作権を持っていた方が色々と自由にできるだろうなぁ」とか「別の媒体に使用するのにいちいち許可をとるのはめんどうだなぁ」とか「自社で独占的に使いたいなぁ」などの思いから、「とりあえず著作権譲渡と著作者人格権は不行使で!」といったスタンスで著作権譲渡や著作者人格権不行使(以下「著作権譲渡等」といいます)を求めてきている可能性もあります。
実際にクライアントのニーズを聞けば、そもそも著作権譲渡等まで要求しなくとも、その時点でクライアント自身が想定している利用範囲において利用許諾(ライセンス)を行う(他の人の使用を禁止したいのであれば独占的な利用許諾にする)等の方法で十分という場合もあるでしょう。
他方、特に発注者であるクライアントが代理店のような場合には、代理店自身のクライアントから著作権譲渡等を求められている関係から、代理店としては制作物に関する著作権譲渡等を求めざるを得ないというケースも想定されます。
いずれにしても著作権譲渡等の内容やその影響をしっかりと理解し、適切な対価が得られているかなども踏まえて、場合によっては利用許諾でも十分ではないかなどクライアントのニーズも踏まえた代替策を提案するなど、取引ごとに適切に判断し交渉していくことが重要だと思いますので、本コラムがその一助となりましたら幸いです。
以上
■ 弁護士 田島佑規のコラム一覧
■ 関連記事
「概説フリーランス新法」
2023年8月29日 弁護士 小山紘一(骨董通り法律事務所 for the Arts)「デザイン分野における契約書作成・交渉のための基礎知識
-業務委託契約書のひな型を題材に各条項のポイントを解説-」
2023年2月27日 弁護士
田島佑規(骨董通り法律事務所 for the Arts)
法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
※文章内容には適宜訂正や追加がおこなわれることがあります。