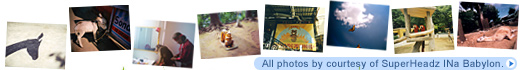2018年2月20日
「名誉毀損訴訟で損害を大幅減額した事案」
弁護士 二関辰郎 (骨董通り法律事務所 for the Arts)
「文春の賠償を大幅減額=イオンへの名誉毀損」(日経)
「名誉毀損、二審は大幅減額 文春のイオン中国産米報道」(時事通信)
2017年11月に名誉毀損訴訟の損害に関して東京高裁から重要な判決が出されました。上記は、その判決に関する記事の見出しです。
この事例では、「イオンが猛毒に汚染された中国産米を安全な米であると偽装して、1500万食分の弁当やおにぎりとして顧客に販売した」といった趣旨の記載を含む週刊文春の記事について、一審の東京地裁判決が約2500万円の損害賠償を認めていました。それを、控訴審である東京高裁が110万円に減額しました。上記いずれの記事の見出しでも「大幅減額」と評されているゆえんです。この判決を機に、名誉毀損訴訟における損害(もっぱら額)について少々整理したうえで、この判決について若干コメントします。
◆ かつての「慰謝料高額化」の流れ
かれこれ二十数年前に自分が弁護士になったころ、名誉毀損訴訟裁判所が認める損害額は、おおむね数十万円とか100万円前後でした。名誉毀損で訴える側にとっては、記事が間違っていたことを裁判で認めてもらうことが重要で、賠償額は「二の次」の場合も多いことなどが、それほど高額化しない原因と指摘されたりしていました。
その後、21世紀を迎えるころから高額化の動きが出てきます。当時の代表的な論文がいくつかあります。たとえば、慰謝料として100万円前後を認めるだけでは低額すぎ被害者救済になっていない等と指摘した升田純弁護士による「名誉と信用の値段に関する一考察(1)~(3)」NBL627・628・634号(1997・1998年)、塩崎勤元東京高裁判事による「名誉毀損による損害額の算定について」判例タイムズ1055号(2001年)などです。他に東京地方裁判所損害賠償訴訟研究会「マスメディアによる名誉毀損訴訟の研究と提言」(ジュリスト1209号63頁)、司法研究所「損倍賠償請求訴訟における損害額の算定」(判例タイムズ1070号4頁)などもあります。このうち、塩崎論文は次のように述べています。
「(筆者注:名誉毀損訴訟において)昭和45年に出された100万円の慰謝料は交通事故での最高慰謝料額400万円の25%程度であり、昭和52年に出された250万円の慰謝料も、改定後の死亡慰謝料に対し、ほぼ同じ割合を保っているが、(中略)戦後人格の値打ちがだんだん上がり、個人としての人格の価値に対する意識が高まっているので、それに応じて当然人格権侵害の賠償額が上がっていってもおかしくなく、(中略)現在の死亡慰謝料額は2600万円であるから、その25%に相当する額は650万円ということになるが、やや高額に過ぎるという感じがしないではなく、産業計全労働者の平均年収額(約495万円)にほぼ相当する500万円程度をもって一般的な平均基準額とするのが相当ではないかと思う。そのうえで、被害額が重要な公職にある政治家、高級官僚、会社役員、弁護士、医師、学者、芸能人などの著名人などについては原則として慰謝料額を増額して然るべきであるし、名誉毀損敵記事が興味本位の暴露趣味的なものであったり、極端に揶揄、愚弄、嘲笑、蔑視的なものである場合にも、慰謝料額を増額するのが相当であろう。」
塩崎論文は、名誉毀損による慰謝料を人が死亡した場合の慰謝料と比較する視点を取り入れています。各慰謝料の金額に直接の関連性はありませんが、塩崎論文は、それを単純に比較するのではなく、時期の変化にともなう各慰謝料相互の比率の変化に着目している点でユニークです。このように、一般的な平均基準額を500万円と定めたうえで、増額要素(や減額要素)によって調整する考え方については、損害額がいくら程度になるのか予見可能性を高める観点から評価する受け止め方もあるでしょうし、他方、スタートする金額を固定化する点など、千差万別である名誉毀損事件の処理の仕方として果たして妥当か疑問視する考え方もありそうです。
当時の大阪地裁の裁判官9名からなるプロジェクトチームの大阪地方裁判所損害賠償実務研究会が発表した「名誉毀損による損害賠償額の算定」(NBL731号6頁、2002年)は、塩崎論文の考え方を肯定的に取り入れ、次のように述べています。
「マスメディアによって相当広範囲にわたって名誉毀損行為が行われた場合について、慰謝料100万円では現在では低額に過ぎ、500万円程度が一つの目安になると考えられる(塩崎勤「名誉毀損による損害額の算定について」判例タイムズ1055号13頁)。具体的事案において、名誉毀損の程度がはなはだしく、被害者がいわば社会的存在を否定されたにも等しいような精神的な苦痛をこうむったような事情が認められる場合には、その慰謝料額が1000万円程度になることも当然考えられるところである。」(同論文10頁)。
こういった論文での指摘に並行するように、実際の裁判例でも高額化の流れが出てきました。代表的なものとして、プロ野球選手清原和博さんに関する名誉毀損訴訟で、2001(H13)年 3月27日東京地裁判決は、1000万円の慰謝料を認めました(後に控訴審で600万円に減額)。また、女優大原麗子さんに関する名誉毀損訴訟である2001(H13)年7月5日東京高裁の事案では、付帯控訴がなかったため第一審の認容額500万円を変更しなかったものの、「慰謝料額は1000万円を下回るものではない」と判断しました。
その後は、多少の反動(?)もあってか、全国規模のマスメディアによる名誉毀損の場合でも、塩崎論文で一つの目安とされた500万円より低い金額あたりで落ち着いている事案が多い印象を受けます。もちろん、個々の事案によって具体的金額は変わるべきですし、実際に幅があります。担当する裁判官の裁量によって決まる部分も大きいと言えます。
もっとも、裁判官の裁量によるといっても、裁判官は何も基準がない中で「えいや」と決めているわけでなく、いくつかの判断要素を踏まえて判断をしています。そういった判断要素として、たとえば前掲塩崎論文では、次のような要素をあげています。原告側・被告側いずれの立場から名誉毀損訴訟を代理する場合でも、損害論について主張・立証する際に参考になります。
被害者側の事情
(1)被害者の年齢・職業・経歴
(2)被害者の社会的評価
(3)被害者が被った営業活動上・社会活動上の不利益など
加害者側の事情
(1)加害行為の動機・目的
(2)名誉毀損事実の内容
(3)名誉毀損事実の真実性・相当性の程度
(4)事実の流布の範囲、情報伝播力
◆ 冒頭の事案に戻ると...
さて、冒頭の事案に戻ると、一審判決が出した約2500万円という金額は、上述した高額化の流れに照らしてもかなり高い金額であることがわかります。では、なぜ一審判決ではそのような高い金額になったのでしょうか。
この事案で原告は、損害として、
①売上減少による営業損失等の財産的損害(営業損害)
②名誉回復措置を講じるために支出を余儀なくされた費用(営業損害の拡大防止及び社会的信用回復のためにした社告及び意見広告掲載費用)
③社会的信用失墜等の非財産的損害
という3種類の損害を主張していました。
①の営業損害は、理論的に認められる可能性はあるものの、損害の発生の立証や名誉毀損行為との相当因果関係の立証は一般に困難とされており、裁判例で認められるのは稀です。この事案でも、東京地裁は、営業損害の発生の立証自体ができていないとして、これは否定しました。
③の非財産的損害(個人の場合の「慰謝料」に相当する概念で「無形損害」と言う場合もよくあります)について、東京地裁は、その事案で問題となった雑誌広告が前述のような衝撃的内容であることや、被告の雑誌が一般週刊誌として日本最大の発行部数を有し影響力が大きいことなどを指摘して、600万円と認定しました。
東京地裁が認めたこの③の金額自体が比較的高額と言えます。しかしながら、問題は②の名誉回復措置のための支出です。この事案では、名誉毀損訴訟で問題となった記事へのいわば対抗措置として、原告が、自ら次のような広告を打っていました。すなわち、「週刊文春は原告があたかも人体に有害な食品を安全な食品と偽って販売していたかのような誤解を読者に与えるものであるが、事実と異なる記述が多い」といった内容を含む社告、あるいは「週刊文春に記載された内容は事実と大きく異なるものであり、現在被告に対して記事の訂正を求めている」といった内容を含む意見広告を、それぞれ複数の新聞に掲載したのです。
原告は、そのような社告ないし広告を掲出するための費用として、合計約1億1150万円を広告代理店に支払っていました。そのうえで、その金額を、名誉回復措置のための支出として被告が賠償するよう訴訟で求めていたのです。東京地裁は、この社告と意見広告の掲載について、「被告の名誉毀損行為によって生じる損害を可及的に抑えるために行われたものであると推認」し、広告には他の内容も含まれていたことから全額は認めなかったものの、広告スペースに占める上記内容部分の割合などを踏まえて、原告請求額の一部である約1666万円を損害として認容しました。
これら600万円(上記③)と1666万円(上記②)の合計額に弁護士費用の一部を加えた結果、東京地裁は、前述のとおり約2500万円という損害賠償額を認めました。
これに対し、控訴審の東京高裁は、前述のとおり、この損害額を全部で110万円に減額しました。110万円のうち10万円は弁護士費用で、残りの100万円は、③の非財産的損害です。
東京高裁は、東京地裁が1666万円という高額を認めた②の名誉回復措置としての支出については、全額を否定しました。その理由として東京高裁は、名誉毀損を認定した広告と見出しの内容が、仮に「猛毒」の二文字を削除して「中国米偽装、〔原告〕の大罪を暴く」という表現にしていれば違法性は認められなかったことや、記事による有意な売上減少が原告側で見られなかったことを指摘しています。そのうえで、東京高裁判決は次のように続けます。
「表現の自由が保障された日本国憲法の下においては、訴訟を提起して言論や表現を萎縮させるのではなく、言論の場で良質の言論の応酬を行うことにより、互いに論争を深めていくことが望まれる。反論記事を別の雑誌等に寄稿したり、本件偽装問題が発覚した直後の平成25年9月25日及び同年10月4日に『お客様へのお詫びとお知らせ』を公表したように、記者会見、プレスリリースや自社ウェブサイトへの掲載などの方法により、自ら必要と考える意見や反論等を発信する方法が考えられる。他方において、言論に要した巨額の費用を訴訟を提起して相手方に請求することは、言論や表現を萎縮させる結果を産むので好ましくないと考えられる。」
ここでの東京高裁による萎縮効果の指摘は特に重要です。仮に、何らかの報道によって名誉を毀損されたと主張する者(原告)が、対抗措置として自己の判断で新聞の社告や意見広告を掲載し、一部であれ、その費用を損害として被告に請求できるとします。そのような多額の費用をかけて広告を出せるのは、資金が潤沢な企業や団体などに限られます。そうなると、大企業等に対する名誉毀損が成立した場合にのみ損害額が高額化するおそれがあることになります。一般的には、資金が潤沢で社会に対する影響力が大きい企業や団体を扱う記事は公共性が高い場合が多く、そういった企業等に対してこそ、メディアによる健全な監視や批判がなされるべきです。ところが、高額の賠償を裁判所が認めると、メディアが委縮し、むしろ、公共性の高いテーマに関する報道が減ってしまいかねません。
司法の主な作用は、個別具体的な紛争の解決にあります。裁判時点からみれば対象となる紛争は基本的に過去の出来事です。そういった過去の紛争をいかに解決するのが妥当か、がそこでの中心的課題になります。ただし、それと同時に、類似の紛争が将来起こった時に、裁判になればどのように解決されるかを人々に示すことを通じて、裁判は、人々の将来の言動に影響を与える場合があります。このように、個別事案をいかに解決するかという観点と、将来にいかなる影響を及ぼすかという観点(海外での法理論で前者をex post、後者をex anteと言ったりします)は、時に相容れず調整が難しいものです。この点、東京高裁の判断は、個別事案の解決として妥当なだけでなく、将来への影響という観点から適切であり、支持できるように思います。
以上
■ 弁護士 二関辰郎のコラム一覧
法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
※文章内容には適宜訂正や追加がおこなわれることがあります。