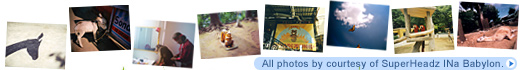2017年10月24日
「公正取引委員会は言った。『労働契約かどうか、それが問題だ。』
~芸能人・プロスポーツ選手と独禁法・労働法の関係~」
弁護士 小林利明 (骨董通り法律事務所 for the Arts)
1 はじめに
突然ですが、あなたがオールスターにも選出されるレベルのプロスポーツ選手だったとしましょう。もし、チーム側の申し合わせにより、どのチームに移籍してどんな活躍をしてもあなたの選手報酬の上限額はいくらだと決まっているとしたら、納得いくでしょうか。あるいは、あなたが事務所に不満を抱える芸能人だったとして、有力芸能事務所間で他事務所の所属芸能人の移籍は受け入れないという合意がされていたらどうでしょうか。
今年7月、公正取引委員会(以下「公取委」)が芸能界の契約に関して大手芸能事務所や業界団体の調査を始めたという報道がなされました。同じ月に公取委は、フリーランスなど雇用契約以外の契約形態を検討対象として独禁法の適用関係を理論的に整理する目的で「人材と競争政策に関する検討会 」を設置しています。検討会では「特定の業種・職種固有の事項や個別の取引慣行の評価は検討対象としない」とされてはいますが、今年は芸能人の移籍・独立問題が話題となる機会も多く、芸能人と所属事務所との契約内容に関する報道も多くなされました。また、公取委は同じ頃にラグビー・トップリーグにもヒアリングを行っており、芸能人やプロスポーツ選手の契約関係について一定の検討はなされるものと思われます。
しかし、近時の一連の報道の中には、芸能人は結局は特殊な世界の人だからということで片づけるだけの記事もあったように思いますし、プロスポーツ選手契約を取り上げた報道は少なかったように思います。実はこの問題は、独禁法・労働法の法的な理屈としても、また、現実におきている事象への理屈のあてはめの場面においても結構難しい話です。そこで、今回のコラムは、この点について少しだけ触れてみたいと思います。
2 この手の議論の歴史は意外に古い
実は、芸能関係者の契約やプロスポーツ選手と球団との契約について独禁法が適用されるかについての議論は古くからありました。
たとえば、1970年には、大手映画製作会社数社が映画監督との間で締結していた統一契約書が独禁法に違反しないかが問題視され(いわゆる五社協定)、監督や俳優の契約は労働契約か(これらの者は労働者か)という点が国会で議論されています。また1978年には、プロ野球のドラフト制や契約金の上限設定に関する球団側の申し合わせなどは独禁法が禁止する「不当な取引制限」(独禁法2条6項)や「一定の取引分野における競争の実質的制限」(独禁法8条1号)にあたらないかが、野球選手と球団との契約は労働契約か(プロ野球選手は労働者か)という観点から国会で議論されています。
でもいったいなぜ、独禁法の議論であるのに、一見無関係にも思える「芸能関係者や選手の契約は労働契約か」が議論されるのでしょう?
3 労働契約の内容を不当に制限する使用者の行為について独禁法は適用されるか?
(1)「労働者」とは何か。
労働者が使用者との間で結ぶ契約が労働契約であり、労働者には労働基準法その他の労働法が適用されます。そして、労働基準法にいう「労働者」とは、他人の指揮監督下で労働し、それにより賃金を得る者のことをいいます(詳細については筆者の過去コラムもご覧ください)。では、そもそも、芸能人やプロスポーツ選手は「労働者」なのでしょうか。
大物芸能人や大物プロスポーツ選手は独立した事業者という要素が強いといえ、サービス提供(出演なり試合出場なり)の実態を踏まえると、所属事務所や球団との間で雇用関係にあるとは見られないこともあるでしょう。他方で、仕事の取捨選択や進め方に裁量はなく使用者の指揮命令下にあり、賃金額もどれだけ働いても定額といった人もいるはずです。このような場合は労働契約下で働く「労働者」といえそうです。
上記のような「大物」の契約に関して、相手側(芸能事務所や球団)が独禁法の禁止する「不当な取引制限」を行った場合に、独禁法が適用されうることについては争いはないようです。では、「大物」より保護すべき必要性が高いようにも思える「労働者」の労働条件について、使用者が(又は複数の使用者が共同して)不当に制限する行為があったとすると、それについて独禁法は適用されるのでしょうか。
(2)公取委は言う。「労働契約かどうか、それが問題だ。」
公取委は、労働契約の内容を制限する行為について独禁法の適用はないと考えているようです。プロ野球選手の契約関係について議論された平成24年3月28日付の事務総長定例会見記録を見てみましょう。
「(事務総長) 選手と球団の,いわゆる野球選手契約については,これまでも,国会質問等でお答えしておりますが,野球選手契約につきましては,一種の労働契約に類する契約と考えられるので,プロ野球における現行の契約慣行を前提として考える限り,独占禁止法上の取引に直ちに該当するものとは解されないので,独占禁止法上問題となるということは言い難いと従来から考えてきているところであります。」
公取委の見解によれば、複数の芸能事務所や球団が共同して、「労働者」の報酬額上限の合意や引き抜き防止協定を行った場合でも、独禁法違反とはならないことになりそうです(※)。また、駆け出し時代(≒労働契約下で働く労働者)の選手の労働条件を制限しても独禁法違反とならないが、大物(≒独立事業者)になれば、選手は独禁法によって保護されるという、一見アンバランスな結論になってしまうようにも思われます。
実は、公取委の見解とは異なり、少なくない独禁法学者は、労働契約関係についても独禁法の適用があると考えています。たしかに、法解釈としても、労働契約に関して独禁法の適用を排除することを定めた明文の規定はありません。また、公取委の立場だと、独禁法の適用の有無を判断するに先立ち労働契約かどうかを判断する必要が生じ、その判断なくしては独禁法の適用の有無が決まらないことになりますが、労働法上、労働契約かどうか(労働者性)の判断は個別具体的な労働実態に基づいてケースバイケースで判断される難しい問題です。それゆえ、このような立場は、独禁法による保護を求める労働者側の負担が大きくなり、労働者の保護に欠けるようにも思われます。
※ この問題は多くの業界に関係しうる話です。アメリカでは大手IT関連企業、大手アニメ製作スタジオや映画製作会社を含む複数企業間で、相互の従業員の引き抜き禁止を合意したことが独禁法に違反するとして司法省が裁判を提起しました。司法省ではこの問題についてのガイダンスを昨年10月に公表しています。
4 独立した個人事業者と労働組合
(1)「事業者」は労働組合を組織して使用者と交渉することはできないのか?
話を少し変えましょう。
独禁法は「事業者」(法人に限らず個人であっても事業者にあたる場合はあります。)の一定の行為を規制しているところ、ここまでは、労働者である芸能人やプロスポーツ選手の契約内容を制限する事業者(使用者)の行為について独禁法は適用されるか、という観点で考えてきました。
では逆に、大物芸能人やプロスポーツ選手が労働組合を組織して(※)、出演や選手活動の条件について各芸能事務所や球団と団体交渉を行い、組合メンバーの最低報酬額や契約期間上限などに合意すると、「事業者(団体)」の行為として芸能人や選手側が独禁法に違反することになるのでしょうか?(つまり、事業者たる大物芸能人らが、芸能事務所が任意の条件で芸能人と契約する自由を不当に制限した、ということになるのでしょうか。)
この点については、違反しないと考えられています。その理由として、関係法令に準拠した行為であるので正当化されるため、などと説明されています(白石『独占禁止法』)。
※ 個人事業者であっても労働組合法上の労働組合を組織することもできます。やや専門的な話になるので詳細は割愛しますが、労働組合法上の「労働者」概念は、労働基準法上の「労働者」概念より広く解釈されているためです。裁判例でも、プロ野球選手は労働組合法上の労働者であることを前提とした判断がされています。なお、ここでは個人事業主と独禁法上の事業者とは同じものとして議論しています。
(2)NBA選手会による法律の使いこなし方に学ぶ
参考までに、アメリカの事例を1つ紹介しましょう。
2011年、NBA(プロバスケットボールリーグ)では、リーグと選手間の利益分配方法をめぐり労使対立が先鋭化しました。このとき選手会(労働組合)は、自ら選手会を解散することをちらつかせて使用者との交渉に臨みました。本来、労働組合を組織する権利は、個々の選手が使用者と個別交渉したのでは得られないであろう有利な労働条件を得るために法が特別に認めたものです。ですから、選手会を解散するということは、自らを守るための権利を放棄するようにも思えます。
なぜそんな戦術をとったのでしょうか。それはこんな理由なのです。
アメリカでは、労使間合意や団体交渉が行われている場合には独禁法(反トラスト法)は原則として適用されません(これをlabor exemptionといいます)。労働組合として労使交渉を行っている間は労働法の適用が優先され、相手を独禁法違反で訴えることはできないのです。でも選手会が解散したらどうなるでしょう?労働組合が存在しなくなる以上、労働組合としての労働法の保護は及ばなくなります。しかし、労働組合がなくなれば団体交渉も消滅するため、labor exemptionはなくなり、リーグ側に独禁法が適用される可能性がでてくるのです。選手側は、こうすることで、法律論はともかく労使合意の下に行われてきたドラフト制や報酬額合意、サラリーキャップ制など様々な制度の法的有効性について裁判で争うことが可能となるのです。
この交渉はある意味「捨て身の作戦」であり、その戦術としての当否については議論がありうるでしょう。実際に、NBAは選手会に対して不誠実団交を理由に裁判を起こしましたが、最終的に、選手会は主要な獲得目標を達成したそうです。アメリカではいかに選手会が法律を交渉道具として駆使して使用者(リーグ)と交渉を行っているか、そんな一例とも言えるでしょう。
5 労働法的に見ると、一連の芸能界トラブルはどう見えるのか
芸能人やプロスポーツ選手といっても、大物を除けば労働者といえる場合が多いと思われ、その場合は労働法による保護が及ぶことはすでにみたとおりです。では、もし労働者だとした場合、労働法の一般的理論・実務感覚からすると、近時の芸能界やスポーツ選手をめぐるトラブルは、どのように見えてくるのでしょうか。ここでは、移籍制限・競業避止義務と引退について考えてみます。
(1)移籍制限・競業避止義務
雇用関係を解消する場合、同業他社への移籍制限や、移籍制限はないが移籍後一定期間は同じ業務を行ってはならないという合意がなされることがあります。裁判実務上、このような競業避止合意の有効性は、退職従業員の地位の高低、時間的・場所的競業制限の程度、禁止競業行為の範囲、競業制限の代償措置の有無などの観点から総合的に判断されるのが通常です。競業禁止期間の長短はケースバイケースの判断となりますが、長いと判断されればそのような合意は無効とされる傾向にあります。長さについては裁判例の積み重ねによる一応の「相場」もありますので、期間設定については注意が必要です。また、代償措置の内容をどう設計するかも、使用者側としては大いに工夫の余地のあるところです。
以上からしても、芸能人の競合事務所への移籍や独立それ自体を禁止すること、別事務所での芸能活動開始を長期間制限すること、あるいは所属元の同意がなければ移籍不可とすることは、労働法の一般理論からすれば、そう簡単には認められないのです。
もちろん、芸能界・スポーツ界のように活動の場や活動方法が極めて限定される職種について、一般会社員に対する競業制限の当否についての常識をそのまま適用することはナンセンスでしょう。「投資」を行った側のリクープ(投資の損益分岐点を超えること)がおよそ見込めないような契約しか適法と認められないとすれば、業界ごと衰退してしまう可能性もあるわけですから。他方で、「採算が厳しい」、「リクープできない場合も多い」といった抽象論だけを語っていても、いつまでも議論は平行線かもしれません。そこで、具体的な数字を踏まえた経済分析を行うことがもし可能ならばおもしろい議論になりそうですが、これまた、サービスの内容が極めて属人的といえる芸能界やスポーツ界において、数値化・一般化することは困難だという考えにも一理あります。一筋縄ではいかない問題です。
またスポーツの世界については、Wリーグ(日本女子バスケットボール)が今シーズンから、移籍にあたり所属元チームの同意を必要とするルールを撤廃しています。従来は特にこのルールにより主力選手の移籍は困難とされていたのですが、今回の撤廃により移籍を決断した選手もいます。スポーツの場合、他の職業と比べてトップレベルの能力で活動できる選手生命が極めて短いという特徴があるので、1シーズンでも無駄にしたくはありません。大きな改革と評価できるでしょう。
(2)引退
プロスポーツ選手の場合、一定の手続きを踏めば契約期間中に引退することはさほど厳しく制限されてはいません。他方で、芸能人は、自身の判断だけで引退や活動停止を決めること自体が認められていないことが多いようです。事務所としては、売れている芸能人をそう簡単に手放したくないと思うのは当然でしょう。この点はマネジメント契約の解除の可否とも関連しますが、契約有効期間が長期であり中途解約できないというような報道も耳にします。
しかし、仮に有効期間が長期とされている契約があったとしても、労働者であれば、その期間ずっと拘束される必要は必ずしもないのです。これは労働法の一般理論からしてもそうですし、実際に、契約期間が2年の「マネジメント専属契約」を締結していたシンガーソングライターについて、労働基準法を適用し、労働契約締結から1年経過時をもって契約終了を認めた近時の東京地裁判決もあります。
報道ではともすれば芸能界やスポーツ界の特殊性だけが着目されがちですが、原則論もちゃんと理解しておきたいところです。そうすることによって、労使双方にとってより妥当でリスクの少ない労働契約が締結されることが期待でき、また何が本当に妥当な業界の特殊性なのかを深く考えることもできるのではないでしょうか。
6 さいごに
日本では、労働者か独立事業者かを問わず、誰にでも職業選択の自由が憲法上保障されています。しかし、業務の性質上活動の場が限られている狭い業界にあっては、他の業界にもまして、「場」を提供する者や「場」への登場に関して影響力を持つ者が強い交渉力を持つのが現実であり、わがままばかり言っているとすぐに「君の代わりなど他にもいるよ」ということになってしまいます。これは需要と供給のバランス上やむを得ないことと思いますが、そのことと、不当な制限が許されるかというのは別問題でしょう。お互いの立場の違いはあれど、業界全体が発展しないと共倒れになってしまうわけですから、今後さらに議論が深まり、良い方向に進むことが期待されます。
以上
■ 弁護士 小林利明のコラム一覧
■ 関連記事
「プロスポーツ界における男女『同一労働・同一賃金』
~女子サッカー米国代表選手たちの絶対に負けられない戦い~」
2019年8月29日 弁護士
小林利明(骨董通り法律事務所 for the Arts)
法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
※文章内容には適宜訂正や追加がおこなわれることがあります。