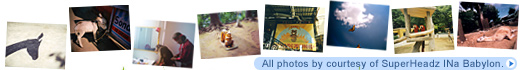2014年1月27日
「特定秘密保護法の刑事手続 ― 『秘密』は秘密のまま人は裁かれる?」
弁護士 二関辰郎 (骨董通り法律事務所 for the Arts)
1 はじめに
著作者やジャーナリストの団体、法学その他の学者・研究者、日弁連といった法律家の団体がそろって反対するなか、2013年12月、強行採決を経て特定秘密保護法が成立した。著作者の団体としては、たとえば、日本映画監督協会・日本児童文学者協会・日本シナリオ作家協会・日本美術家連盟・日本脚本家連盟及び日本映画撮影監督協会があり、これら6団体が共同緊急声明を出している。ジャーナリストの団体としては、たとえば、日本ペンクラブ・日本新聞協会などがある。
この法律は、特定秘密の漏えいや、一定の不正な手段を用いた取得、それらの共謀、教唆、扇動に対する罰則を定めている(以下では、これらの行為をまとめて「秘密漏えい」とする)。
秘密漏えいを対象とする刑事裁判では、漏えいの対象となった「秘密の内容」が重要な意味を持つ。しかし、公開裁判で秘密の内容が明らかになれば、それこそ秘密が国内外に漏えいさかねない。では、こうした裁判手続では、秘密の内容は明らかにされないまま手続が進行するのであろうか。
2 政府見解
国会審議における政府答弁をみると、政府は、「外形立証」と言われる秘密の内容を明らかにしない裁判手続を想定していることがわかる。
外形立証についての政府見解を記載した資料に、内閣官房「特別秘密の保護に関する法律案【主要論点集】」というものがある。この資料では、その【論点5】で「刑事手続における特別秘密の立証方法について」というテーマを取り扱っている。この資料*に沿って、政府見解をみてみることにする。
* NPO法人情報公開市民センター(理事長 新海聡弁護士)が情報公開請求で入手したもの。この【論点5】と実質的に同じ文書を、同センターのウエブサイトで見ることができる。トップページの「秘密保全法に反対します」タブで開かれるページにある目次40番中の全538頁の文書のうち、121~122頁にある「刑事裁判手続における特別秘密の立証方法について(案)」という文書が、それに相当する。
この資料には、おおむね次のような記載がある。
外形立証について
◆これまでの国家公務員法違反等の秘密漏えい事件の刑事裁判においては、いわゆる外形立証の方法が採られている。
◆外形立証とは、①秘密指定の基準(指定権者、指定される秘密の範囲、指定及び解除の手続)が定められていること、②当該秘密が国家機関内部の適正な運用基準に則って指定されていること、③秘密の種類、性質、秘扱いをする由縁等を立証することにより、当該秘密が実質秘であることを推認する方法をいう。
◆外形立証は判例上も認められており(東京高裁昭和44年3月18日判決)、秘密の内容そのものを明らかにしないまま実質秘性を支障なく立証する方法として実務上確立している。
この政府見解は、外形立証という立証方法が実務上確立していることを前提として、秘密の内容そのものを明らかにしなくても良いとする立場である。しかし、外形立証という立証方法が、実務上確立していると言って良いであろうか。
3 裁判例について
上記資料が引用する東京高裁判決は、1969(昭和44)年に出された結構古い判決である。
国家公務員法が保護する「秘密」の意義については、従来、形式秘をいうのか、実質秘をいうのか議論があった。形式秘とは、行政官庁において秘密の取扱いをすると指定された事項をいい、実質秘とは、その性質上非公知性と要保護性を有する事項をいう。実質秘を意味するとなれば、漏えい対象が「秘密」に該当するか否かが争点になった場合、個別具体的に検討する必要が出てくる。
この点について、最高裁は、有名な外務省漏えい事件(最高裁1978(昭和53)年5月31日第一小法廷決定)において、実質秘説をとっている。この外務省漏えい事件では、控訴審判決(東京高裁1976(昭和51)年7月20日判決)も実質秘説を一応とってはいた。しかし、控訴審判決は、公務員の専門性や経験を重視し、公務員による秘密指定があれば実質秘と推定するような考え方であった。そのため、控訴審判決に対しては、「形式的実質秘説ではないかとの批判があった」と指摘されている(最高裁判例解説刑事篇昭和53年度152~153頁・堀籠幸男調査官)。
また、この最高裁判決が出された当時、米国連邦最高裁は、「国防又は外交政策に関する情報につき秘密指定がなされたときは、そのような行政府の指定の当否に対しては、司法審査は及ばない」とする立場をとっていた(前掲最高裁判例解説153頁)。
そのような状況にあったにもかかわらず、外務省漏えい事件において最高裁は、「(秘密性の)判定は司法判断に服することを明言し〔た〕」(前掲最高裁解説同頁)。そのうえで、最高裁決定は、秘密漏えいの対象とされ、証拠提出されていた電信文案を見たうえで実質秘性を判断している。この経緯や最高裁判例解説のニュアンスなどを踏まえると、最高裁決定は、「秘密」の該当性判断を司法府が実質的に行うことを、控訴審判決との比較でも、より重視した立場をとったと考えられる。
外形立証は、行政府による秘密指定などの行政府の判断を重視した考え方であるから、外務省漏えい事件の控訴審判決と似たような考え方であると言いうる。ただし、その控訴審判決も、「第一〇三四号電信文案及び第八七七号来電文の記載内容上も極秘の指定がなされるにふさわしいものであり、かつ、刑罰による威嚇をもつて漏示を禁止する必要性、つまり、秘匿の必要性のある文書に当たるもの」と判示しており(下線は筆者)、漏えい対象とされた電信文案自体を証拠として採用のうえ、その内容を判断の一要素としていた。外務省漏えい事件最高裁決定は、その控訴審判決よりも、「秘密」の内容を司法府が実質的に判断することを重視した立場と考えられる。そうすると、外形立証をとりいれた1969(昭和44)年東京高裁判決の考え方が、この最高裁決定後も直ちに妥当するとは言いがたいように思える。
なお、判例を調べた限りでは、1978(昭和53)年の外務省漏えい事件最高裁決定後に外形立証を認めた裁判例は見当たらなかった。すべての判例を網羅できていない可能性もないではないが、特定秘密保護法案の国会審議で森担当大臣及び谷垣法務大臣が外形立証の例としてあげた裁判例も、1969(昭和44)年東京高裁判決であった。
4 不正競争防止法の法改正に関する議論から
不正競争防止法では、2011(平成23)年の法改正により、営業秘密を保護するための刑事訴訟手続の特例として、秘匿決定制度という仕組みが定められた。同法では、すでに2004(平成16)年に民事裁判との関連で裁判の公開停止に関する仕組みが設けられているが、その後、刑事裁判に関する規定を別途設けたものである。
不正競争防止法のこの改正に先立って、経産省・法務省が、共同で、営業秘密保護のための刑事訴訟手続の在り方研究会という有識者会議を開催した。研究会の議事録は、法務省のウエブサイトで見ることができる。
この研究会の会議において、法務省の担当官は、国家公務員法の秘密漏えい罪等の公判活動での工夫として外形立証がとらえていることについてコメントし、「ただ、〔外形立証〕が十分に機能しているかどうかといった点は、なかなかそこは検証が難しい」と述べている。また、この会議の構成委員のひとりである土肥一史日本大学大学院教授は、「被告人の公開裁判を受ける権利というもの、それから外形立証というようなこともあったわけでございますけれども、真実発見のための手続であって、被告人の防御権の完全な行使という観点からは、やはり外形立証には限界がある」とコメントしている(いずれも同会議の第1回議事録)。
このように、外形立証という仕組みについて、それが十分機能しているか否かが不明である旨政府担当者自身が述べている。また、被告人の防御権の行使という観点から、外形立証には問題があることを有識者も指摘している。
5 誰に対して秘密を明らかにしない仕組みか
これまで明確に区別をせずに述べてきたが、秘密の内容を「明らかにしない」と言った場合、秘密の内容を、裁判の傍聴者や報道機関などには知らせないという場合と、裁判官や裁かれる立場にある被告人側も知らないままに手続が進行する場合とが考えられる。
不正競争防止法の秘匿決定制度では、裁判所が、営業秘密の内容を公開法廷で明らかにしない旨の決定をした場合、たとえば、営業秘密を特定する事項を他の呼称に置き換えたり、当該事項にわたる尋問や陳述を制限したりすることができる。そのような制限がなされた場合、弁護側もそれに従うべきこととされているから、この制度は、基本的には、営業秘密の内容を弁護側が知っていることが前提になっている。弁護側も知ったうえで、言い回し等を工夫することで、傍聴人等には知られないようにする仕組みである(なお、営業秘密の内容を被告人に知らせない仕組みもあるが、あくまでも個別に検察官がそのような措置を求めた場合であって、「被告人の防御に関し必要がある場合」(不正競争防止法30条1項)などは除かれる)。
これに対し、外形立証は、秘密の内容を裁判官にも伝えずに実質秘性を立証しようとする方法であるから、裁判官や被告人側にも秘密の内容を知らせないことを想定した仕組みである。*
* 公判前整理手続において、いわゆるインカメラ審理(裁判所だけが直接文書等を見分する方法によって行われる非公開審理)がとられれば裁判官は秘密の内容を見ることになる。また、その結果、裁判官が証拠開示を命じてその判断が確定し、国がそれに従えば被告人側にも秘密が示されることになる。ただし、ここに記載したインカメラ審理以降の手続は、そもそも、弁護側が求める証拠開示に国が応じなかった場面で問題になるから、国は、望まない証拠開示を防ぐべく、裁判所がインカメラ審理を行わないよう、また証拠開示を命じないよう対応・主張するであろう。被告人側は、手持ち資料なしに、それに反論しなければならない。裁判所も、限られた情報に基づいて判断を迫られる可能性がある。くわえて、一度広く知られた情報を元の秘密の状態に戻すことはできないから、裁判所の判断は、自ずと開示方向に対して慎重なものになるおそれがある。それゆえ、公判前整理手続における開示の制度があるからといって、必要な場合に被告人側に秘密の内容が示されることが保証されているとは言いにくい。
既遂の事案では、被告人側は秘密の内容を見ているかもしれないが、未遂の場合や、教唆等で自分は入手していない場合には、被告人は秘密の内容を一切見ていないことになる。また、既遂の事案であっても、いったん入手はしたが、捜索押収によって捜査機関が持ち去ったため手元にない場合もある。人の記憶は不正確であるから、その場合にも正確な内容がわからないまま防御をしなければならないことになる。
秘密を特定する事項を他の呼称に言い換えたり、秘密事項にわたる尋問や陳述を制限されたりする場合でも、被告人の防御に支障が生じる可能性は多分にある。しかし、被告人側が秘密の内容そのものを一切知らずに防御をしなければならない場合に被告人側が被る支障は、その比ではない。前者の場合、ある程度、法廷技術的な要素で対応可能な面もあるが、後者の場合、たとえば実質秘性を争うのが妥当か否かといった判断にも支障を生じ得る。つまり、何を争点とすべきかといった根本的な防御方針に影響するのである。
この点、政府は、不正競争防止法の秘匿決定制度と同様の仕組みを特定秘密保護法でも取り入れるか否かを検討していた。先に紹介した内閣官房の資料などから、そのことがわかる。しかし、結果的に政府はそのような仕組みは採用しないことにした。その理由の一つは、秘密漏えいにかかわる刑事事件は、憲法82条2項ただし書の「政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保証する国民の権利が問題になっている事件」に該当する余地があるため、秘匿決定制度のような制度を採用することは、対審の一部を非公開にするものとして憲法に抵触するおそれがあるという考えからである。
しかし、裁判の公開を制限する仕組みが憲法上とれないからといって、審理対象となる秘密の内容を被告人側に知らせないで済ます発想は、訴追者側の一方的な都合に偏していないであろうか。そもそも裁判の公開原則の趣旨は、公開によって裁判を国民の批判のもとにおき、公正な裁判を確保することにある。裁判が公正か否かによって最も影響を受けるのは、言うまでもなくその事件で裁かれる被告人である。憲法82条2項ただし書は、特に重要な権利にかかわり、公正な裁判を確保する必要性が高い範疇の事件につき、公開性の徹底を求めた規定であろう。政府見解は、そのような重要な権利にかかわる裁判の場合に、かえって被告人の防御への配慮が少なくても良いと言っているようにも思える。
6 若干のまとめ
政府は、外形立証が実務上定着していることを前提に、秘密の内容そのものを被告人側に明らかにしないまま刑事手続を進行させることを想定している。しかし、政府見解が依拠する外形立証を認めた裁判例は古いものである。外務省漏えい事件最高裁決定がすでに出されている現時点において、裁判所が同様の判断をするとは限らない。外形立証が実務上確立しているという前提は成り立たないというべきであろう。また、被告人の防御権を確保する観点からは、外形立証を認めるべきではない。
政府見解を前提にすると、秘密の内容がわからないまま、秘密漏えいについて刑罰が科される可能性がある。表現行為・創作行為に対して萎縮的効果が働く懸念があるように思うが、みなさんはどのように思われるであろうか。
■ 弁護士 二関辰郎のコラム一覧
法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
※文章内容には適宜訂正や追加がおこなわれることがあります。