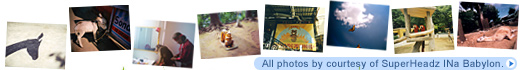2013年6月27日
「自己増殖する植物と特許権の消尽
~全米を揺るがした「モンサント」連邦最高裁判決」
弁護士 諏訪公一(骨董通り法律事務所 for the Arts)
2013年5月13日、アメリカで遺伝子組み換え作物に関する特許訴訟の連邦最高裁判決がありました。遺伝子組み換え作物の巨人:モンサント社は、インディアナ州で農業を営むバウマン氏に対して、業者が育てた大豆を購入し、それを種子にして大豆を栽培することが自社の特許を侵害するとして訴訟を提起したのです。遺伝子組み換え作物の安全性の議論に加え、その遺伝子組み換え作物の世界シェアが大きいことなどから様々な意味で注目されるモンサント社ですが、今回の判決は、遺伝子組み換え作物の栽培と「特許権の消尽」について判断をした判決として注目されています。このコラムでは、今回のアメリカ連邦最高裁の判決の概要(判決文はこちら [PDF:105KB])の紹介を中心に、日本の法律についても簡単にご説明したいと思います。
■ モンサント社の「ラウンドアップ・レディー大豆」とは
ミズーリ州に本社があるモンサント社は、遺伝子組み換え作物(genetically modified organism。頭文字を取って「GMO」とも呼ばれます)の世界シェアの実に9割をも占める企業です。今回問題となった対象製品は、遺伝子組み換え作物のうちの、「ラウンドアップ・レディー大豆(Roundup Ready soybean)」という大豆です。「ラウンドアップ・レディー」とは、モンサント社が自ら開発したグリフォセートを有効成分とする除草剤「ラウンドアップ」の耐性ができるように遺伝子を組み替えた作物のことを指します。つまり、モンサント社は自社で除草剤を作り、さらにその除草剤に耐えられる大豆をも自社で作っているのです。そして、モンサント社はこの「ラウンドアップ・レディー」に関する遺伝子の特許(USP5,352,605及びUSRE39,247E)を有しています。
■ バウマン氏の栽培方法とは
では、モンサント社から訴訟を提起されたバウマン氏は、一体何をしたのでしょうか。「ラウンドアップ・レディー大豆」を栽培しようとするとき、農家はモンサント社のライセンスを受けた種子生産業者から種子としての大豆を購入します。ただ、購入に際し、モンサント社はあるライセンス条件を定めていました。これは、「その種子から1回だけ作付け・収穫することができ、収穫した大豆は消費するか食用または飼料として販売することはできる。収穫した大豆を基に再度栽培してはいけない」という条件です(モンサント社ホームページにも、条件があることが明記されています)。なお、「ラウンドアップ・レディー大豆」は遺伝子を組み換えた結果備わる除草剤への耐性ですので、第2世代以降も「ラウンドアップ・レディー大豆」が誕生します。
バウマン氏は、毎シーズン1回目の作付け用には、ラウンドアップ・レディー大豆の種子をモンサント社から購入していました。しかし、シーズン2回目の作付けに関しては、大豆を第三者から購入してきて、そこから作付けをしていました(より正確にいうと、大豆の大穀物倉庫(grain elevator)から商品を購入し、その中に含まれるラウンドアップ・レディー大豆を選り分けて作付けしていたようです)。なぜバウマン氏がシーズン2回目の作付けだけこのようなことをしたかというと、2回目の作付けは一般にリスクが高く、コスト削減のために、高い種子を避けたようです(モンサントから種子として購入するよりも、業者の商品の方が安く購入できます)。そして、モンサント社は、シーズン2回目のこのような作付け行為について、特許権侵害であると訴えたのです。
■ アメリカ連邦最高裁判決の判断
アメリカの地裁は、バウマン氏からモンサント社へ84456.20ドルの損害賠償を認める判決をし、連邦巡回区控訴裁判所(判決はこちら [PDF:113KB])も、地裁判決を支持しました。今回、アメリカ連邦最高裁も、全員一致でモンサント社の請求を認め、バウマン氏は特許権侵害をしたと判断しました。
この事件は、法律的には、自己増殖する種子の栽培で「特許権の消尽」が認められるかという点で争われました。判決によれば、特許権の消尽理論(the exhaustion doctrine)とは、「特許製品の販売が行われた場合には、そこで一度発明の対価が支払われているため、その製品の使用や再販売に特許権者は重ねて特許権を行使できない」というものです。ただ、消尽理論は、特許製品を新しく生産(make a new product)することには及ばないとされています。なぜ、このような理論があるのかというと、特許権者は、適法に販売された特許製品からは既にロイヤルティを取得しているため、その使用や再販売については特許権者に別途ロイヤルティが支払われなくても(特許権が及ばなくても)問題ないためです。他方、新しく生産された特許製品の場合、特許権者はロイヤルティが支払われていないため、このような製品についても特許権者にロイヤルティを獲得する機会を与えるべく、消尽は及ばないとされるのです。もし仮に、特許製品から新しく生産されたものに特許権が及ばないとなると、1回購入したら永遠に再生産が可能となり、特許権者にとって十分なロイヤルティ収入などが期待できなくなってしまいます。
そして、判決では、バウマン氏の行為は、本来飼料等になるべき収穫物としての大豆を購入し、それを種子としてラウンドアップ・レディー大豆を栽培し、固体数を増やしたものであるから、まさに「特許発明を実施した大豆を再生産する」行為であり、特許権の消尽理論の適用はない、つまり特許権侵害になるとしました。
これに対し、バウマン氏は、「確かに私は特許製品から生産された大豆を購入した。ただ、その大豆を通常の用法で栽培しているだけである。特許権の消尽とは、適法に販売された特許製品の『使用』は自由であるとする理論であるから、通常の用法で栽培していることについても特許権の消尽の適用があるはずだ」と反論しました。しかし、先ほどご説明したように、たとえ適法に販売されたものであるとしても、その再生産に特許権が及ばないとするとたった1回の取引で特許権が消滅してしまいます。そうすると、特許権が認めた「20年間の独占期間」は空論になりかねず、発明のインセンティブを損ねる可能性があるとしました。
さらに、バウマン氏は、上記に加えて「大豆は自然に発芽し、自己増殖する(self-replicate)ものである。だから、『作付けされた大豆』自身が再生産したのであり私が大豆を再生産したのではない」という反論もしました。判決文では「blame-the-bean defense」(さしずめ「大豆のせいにする抗弁」といったところでしょうか)と名付けられていますが、この主張も認められませんでした。判決では、バウマン氏は、ラウンドアップ・レディー大豆が含まれていると予期して大穀物倉庫から大豆を購入し、その中からラウンドアップ・レディー大豆を選んで栽培をした上で、さらに次の栽培のために貯蔵し、これに別途購入してきた収穫物としての大豆を追加しながら栽培し・・・ということを続け、8世代も再生産しているのですから、大豆の再生産をコントロールしているのは、「大豆自身」ではなく、バウマン氏であるとしました。
以上のとおり、バウマン氏はモンサント社の特許を使用した大豆を再生産しているとして特許権の消尽は認められないとして、モンサント社の特許権侵害とされました。
■ 日本における「特許権の消尽」理論
日本においても、市場における特許製品の円滑な流通が妨げられること、最初の譲渡においてロイヤルティ収入を得ているため更なる譲渡について二重に利得を得ることを認める必要はない、といった政策的理由により、特許法上の明文はないものの、「特許権の消尽」の理論が認められています。最高裁が特許権の消尽を正面から認めたものとして、キヤノン社のプリンターの正規品のインクタンク(使い終わったもの)をリサイクルし、インクを再充填して販売したことがキヤノン社の特許権に反するか問題となった事件の判決があります(最判平成19年11月8日。判決文はこちら)。
日本における特許権の消尽の理論は、修理や加工等においてどこまでの行為が消尽の範囲内か、という点で議論されてきました。インクタンク事件最高裁判決の詳細な検討は優れた論稿が多数存在しますのでそちらに譲るとして、判決では、特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象は「特許権者等が我が国において譲渡した特許製品そのもの」に限られ、特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたならば特許権の行使ができるとされました。そして、「特許製品との同一性の有無」は、総合考量で判断するとしています(当該特許製品の属性(製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様)、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様(加工等がされた際の当該特許製品の状態、加工の内容及び程度、交換された部材の耐用期間、当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値)のほか、取引の実情等も総合考慮して判断)。
消尽論が、特許権者のロイヤルティ獲得機会を保証するという機能と、取引の安全を図るという政策的理由から特許権の効力を定めるものであることからすれば、「排他的にその対価を取得する機会が与えられていたか、特許権者においてその実施についての対価を取得することが客観的に想定されていたか否か」という観点を加味しながら「特許製品との同一性の有無」基準が判断されることになります。今回は、修理や加工ではないため多少事例は異なりますが、大豆の作付けを行い管理をして元の種子の個体数を増加させることは新たな「生産」(特許法2条3項)行為の一部であり、少なくとも増加した個体については特許権者がロイヤルティを受け取る機会を奪っているものとも考えられることといった点は、特許権は消尽しないと判断される要素となるでしょう。
■ 種苗法と権利の消尽
今回のアメリカの連邦最高裁判決は特許法上の議論に関する判決でした。ただ、今回の判決とは関係ありませんが、日本においては、新品種の保護に関しては、「種苗法」という法律がありますので、そちらについても簡単にご紹介します。
種苗法においては、品種登録を受けている品種の育成者権が認められていて、業としての利用を独占できます(アメリカにおいても、一般特許や植物特許を定める特許法の他、「植物品種保護法」という法律があります)。植物の新品種を特許権で保護するか、育成者権で保護するかは植物の新品種の保護に関する国際条約(UPOV条約)との関係で過去の経緯はあるものの、現時点では、特許権及び育成者権双方の登録が可能です。
この種苗法には、特許法とは異なり、権利の消尽に関する規定が明文で設けられています(21条4項)。同項では、適法に登録品種等の種苗・収穫物を譲り受けた場合には「(育成者権は)その譲渡された種苗、収穫物又は加工品の利用には及ばない」と規定されています。ただし、これには例外が定められており、その例外の一つが「登録品種等の種苗を生産する行為」です。これは、植物には増殖能力があるので、譲受人が種苗を生産することにより種苗の個体数が増大し、育成者権者が自ら生産した種苗の販売の機会を失う恐れがあるためであり、ちょうど特許についての米最高裁判決と同じ考え方と言えます。
また、この「種苗の生産」には、種苗の増殖の他、収穫物として譲渡されたものを種苗に転用する行為も含まれると解釈されています。これも、転用された分だけ、育成者権者が種苗を販売する機会を失う可能性があるためです(農業者の自家増殖を定めた21条2項は除きます)。
もし仮に、モンサント社が同品種を日本で登録していて、「バウマン氏の行ったような栽培行為はモンサント社の育成者権を侵害している」として日本で侵害訴訟を提起した場合には、収穫物として第三者から譲渡されたものを種苗に転用して生産をしていることになりますので、種苗法21条4項により、権利の消尽はしないと判断されたのではないかと考えられます(なお、農水省の「品種登録データ検索」において、「出願者の氏名」を「モンサント」として検索をすると、日本モンサント社が有する稲種の2件のみがヒットしましたので、ここで検索する限り、ラウンドアップ・レディー大豆の品種登録はされていないようです)。
■ 最後に
収穫物として販売されている大豆を購入し栽培するという今回の行為に関していえば、種子に対する正当な対価を払っていないケースですから、特許権は消尽していないと比較的判断しやすい事例であったように思われます。なお、この判決では、今回の判断は事例判決であり、判決の射程は広くないと明記されています。しかし、本判決は、細胞株やソフトウェアなどの「自己増殖できる製品」に波及するおそれがあるのではないかという意見もあるようです。
報道によれば、モンサント社は、2013年初頭において446もの農家等に対して144の訴訟を提起しているようです(ニュース記事)。これらの訴訟の中で、同社の特許に関しても引き続き様々な判断がなされる可能性もあり、その動向が今後も注目されます。アメリカの判決の動向は、それがストレートに日本に反映されるものではないとしても、日本において今まであまり注目されなかった、動植物などの生物関連発明や自己増殖するものに関する発明と特許権の消尽の問題を考える、一つのきっかけになるでしょう。
以上
法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
※文章内容には適宜訂正や追加がおこなわれることがあります。