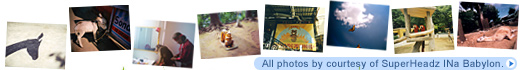2013年7月29日
「実演家の権利について再確認してみよう-北京条約を契機に 【後編】」
弁護士 唐津真美(骨董通り法律事務所 for the Arts)
前編から少し時間が経ってしまいましたが、今回は、コラム【前編】で紹介した「視聴覚実演に関する北京条約」(Beijing Treaty on Audiovisual Performances)(以下本稿において「北京条約」)の主要な条文を取り上げて、具体的な中身を見ていきます。とりあえず条約全体を読みたい方は、文化庁が公表している条約の原文と参考訳[PDF:257KB] をご覧ください(今回のコラムで引用している条文は、すべて同参考訳に依拠しています)。「そもそも実演家って何?」「日本の著作権法の規定はどうなっていたっけ?」という方は、【前編】を先に読んでいただくとわかりやすいと思います。
■ 北京条約の全体像
北京条約は、俳優や舞踊家といった"視聴覚的な実演家"に対して著作隣接権を設定するなどして、権利の保護を図ることを目的とした条約です。全体像を把握するために、まずは目次を見てみましょう。
前 文
第1条 他の条約との関係
第2条 定義
第3条 保護の受益者
第4条 内国民待遇
第5条 人格権
第6条 固定されていない実演に関する実演家の財産的権利
第7条 複製権
第8条 譲渡権
第9条 商業的貸与権
第10条 固定された実演を利用可能にする権利
第11条 放送及び公衆への伝達に関する権利
第12条 権利の移転
第13条 制限及び例外
第14条 保護期間
第15条 技術的手段に関する義務
第16条 権利管理情報に関する義務
第17条 方式
第18条 留保及び通告
第19条 適用の時期的範囲
第20条 権利行使の確保に関する規定
第1条から第4条は条約全般に関する規定であり、第5条から第11条が、視聴覚実演家に与えられる具体的な権利を規定しています(以下特に記載のない限り条文番号は北京条約の条文を意味します)。第12条・第13条は、これらの実演家の権利に関して各締結国が国内法で任意に規定することができる内容を定めており、第14条は実演家の権利の保護期間を定めています。第15条・第16条は、実演家の権利自体ではなく、権利の保護をはかるための手段に関する規定です。第17条以下は、権利を享受するための方式や、条約締約国が条約を適用する際の措置等、条約加盟に関する手続的な内容を中心に規定しています。また、条文には適宜合意声明が付されており、解釈について補足されています。(本コラムでは、必要に応じて、条文の後に合意声明の要旨を【 】に入れて付記しています。)
北京条約の締約国は、他の締約国の実演家に対して条約に規定される保護を与えなければならず(第3条)、また自国の法制に従い、条約の適用を確保するために必要な措置を定めることが求められています(第20条)。第3条を読むと、条約が意図している保護の対象は外国の実演家ということになりますが、日本は従来から、著作権・著作隣接権の保護に関して自国の権利者と外国の権利者を同様に保護していますので、国内法である著作権法との間に齟齬があるならば、北京条約加盟の前提としてこれを整備することが必要になります。スペースの関係上、本コラムで北京条約の全条文を解説することは難しいので、日本が北京条約に加盟するにあたり何が問題になりうるのかという視点から、国内法との整合性の検討を中心にしたいと思います。
■ 定義規定
第2条 定義
この条約の適用上、
(a) 「実演家」とは、俳優、歌手、演奏家、舞踊家その他文学的若しくは美術的著作物又は民間伝承の表現を上演し、歌唱し、口演し、朗詠し、演奏し、演出し、又はその他の方法によって実演する者をいう。
【合意声明:実演の過程において創作された又は最初に固定された、文学的又は芸術的著作物の実演を行う者も含む】
(b) 「視聴覚的固定物」とは、音又は音の表現物を伴うか若しくは伴わない動く影像の収録物で、装置を用いることによりこれらが知覚され、複製され、又は伝達され得るものをいう。
(c) 「放送」とは、音若しくは影像若しくは影像及び音又は音の表現物を、公衆に受信させるために無線の方法により送信することをいう。衛星によるそのような送信も「放送」である。放送機関により又はその同意を得て、暗号解除の手段が公衆に提供されている場合は、暗号化された信号の送信も「放送」である。
(d) 実演の「公衆への伝達」とは、放送以外のあらゆる媒体により、固定されていない実演又は視聴覚的固定物に固定された実演を、公衆に送信することをいう。第11条の規定の適用上、「公衆への伝達」は、視聴覚的固定物に固定された実演を公衆に聴取可能若しくは視覚可能又は聴取可能及び視覚可能にすることを含むものとする。
(a) は「実演家」の定義です。日本法では、著作隣接権で保護される「実演」とは、「著作物を演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、またその他の方法により演ずること」と定義されており(著作権法第2条1項3号)、「実演家」については、「俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう」と定義されています(同2条1項4号)。北京条約における「実演家」の定義に関しては、国内法との整合性はとれているといえるでしょう。
(b) の「視聴覚的固定物」(audiovisual fixation)という用語自体は、著作権法上に規定はありませんが、「映画の著作物」(同2条3項)が参考になるでしょう。「映画の著作物」については「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。」と規定されているからです。(ちなみに、著作権法には、「映画」とは何かという定義はありません。)
(c) の「放送」は、著作権法上の「放送」(同2条1項8号)が該当します。
(d) の「公衆への伝達」は、一見すると著作権法上の「公衆送信」(同2条1項7の2号)に相当しそうなのですが、微妙な違いがあります。北京条約上は、「公衆への送信」の中に「放送」と「公衆への伝達」が含まれることになりますが、著作権法上は、「公衆送信」の中に「放送」「有線放送」「自動公衆送信」が含まれているからです。北京条約の「公衆への伝達」は、その位置づけからすると、著作権法上の「有線放送」と「自動公衆送信」を合わせたものになります。(差異もありますが、詳細は割愛します。)
■ 人格権
第5条以下は、実演家が享有できる権利の内容について定めた規定です。第17条には、以下の権利の享有及び行使には、(登録などの)いかなる方式の履行も要しないことが規定されています。では、権利の内容を条文の順番に見てみましょう。
第5条 人格権
(1) 実演家は、その財産的権利とは別個に、それらの権利が移転した後においても、生の実演及び視聴覚的固定物に固定された実演に関して、次のような権利を保有する。
(i) 実演の利用の態様により省略することがやむを得ない場合を除き、その実演の実演家であることを主張すること
(ii) 視聴覚的固定物の特質を十分に勘案しつつ、実演の変更、切除又はその他の改変で、自己の声望を害するおそれのあるものに対して異議を申し立てること。
【合意声明:実演家により許諾された使用の過程においてなされる、実演の通常の利用に伴う改変(編集、要約、吹き替え、又はフォーマッティング)は、本項の改変に該当しない。】
(2) (1)の規定に基づいて実演家に認められる権利は、実演家の死後においても、少なくとも財産的権利が消滅するまで存続し、保護が求められる締約国の法令により資格を与えられる人又は団体によって行使される。もっとも、この条約の批准又はこれへの加入の時に効力を有する法令において、前項に基づいて認められる権利のすべてについて実演家の死後における保護を確保することを定めていない締約国は、それらの権利のうち一部の権利が実演家の死後は存続しないことを定める権能を有する。
(3) この条に基づいて認められる権利を保全するための救済の方法は、保護が要求される締約国の法令の定めるところによる。
北京条約の第5条から11条は、実演家に対して付与される個々の権利についての規定です。まず第5条が、実演家は固有の権利として人格権を有すると規定しています。具体的には、実演家は(1)実演家として氏名を表示する権利(氏名表示権)、及び(2)自己の声望を害するおそれのある実演の改変に対する異議申し立ての権利(同一性保持権)の2つの権利を享有するとされています。このうち同一性保持権については、条約本文に「視聴覚的固定物の特質を十分に勘案しつつ」と書かれているほか、合意声明において、実演家が許諾した実演の使用の過程で行われる通常の改変(実演の編集、吹き替え等)については本条で問題となる改変には該当しない旨が明記されており、視聴覚的固定物の利用者側に過度の制約とならないように配慮されています。また、人格権の保護期間については、実演家の死亡に伴って終了するものではなく、少なくとも下記で触れる財産的権利が消滅するまでは保護が存続すると規定されています。ただし、条約の批准または加入時にすでに国内法によって死後の人格権保護を定めていない国については、実演家の死後は人格権の一部が存続しないと定めることもできると規定されています。これは、実演家の人格権が実演家の死亡と共に消滅することを前提として実務が行われている国における、利用者側の利益に配慮した規定といえます。(ちなみに、北京条約第14条は、実演家に認められる保護の期間は実演が固定された年の終わりから少なくとも50年間と規定しています。)
日本の著作権法は、2002年にWIPO実演・レコード条約(詳細は【前編】参照)に加入した際に、実演家の権利を付与するよう改正されました。氏名表示権(著作権法第90条の2)と同一性保持権(同90条の3)については、すでに北京条約の上記規定に沿った権利が付与されています。実演家の死後における人格権の保護については、実演家人格権は一身専属的なものとされており(同101条の2)、実演家の死亡によって消滅するという原則に立ちます。しかし一方で、実演家の死後であっても、実演を公衆に提供する者は、実演家が生きていれば人格権侵害に相当したような行為をしてはいけないという規定(同101条の3)によって、実演家の死後も人格権の保護が図られています。ただし、「行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該実演家の意を害しないと認められる場合」は例外とすると旨が規定されていますし(同但書)、侵害行為について差止請求等をすることができるのは遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)に限られるという制限もありますので(同116条1項)、実演家の生前とまったく同一の保護が、死後も確実に継続するわけではありません。もっとも、北京条約は、死後の人格権を行使する者については、「締約国の法令により資格を与えられる人又は団体」と規定していますし、国内法によって、人格権の一部が実演家の死後は存続しないと規定することも認めている点を考慮すれば、死後の実演家人格権に関する日本法の規定は北京条約が認める締約国の裁量を認める範囲内に収まっているようにも思われます。
■ 実演家の財産的権利
第6条 固定されていない実演に関する実演家の財産的権利
実演家は、その実演に関して、次のことを許諾する排他的権利を享有する。
(i) 既に放送された実演を除き、固定されていない実演を放送し、又は公衆に伝達すること
(ii) 固定されていない実演を固定すること
第6条は、「固定」されてない実演に関する規定です。(北京条約には「固定」という用語自体の定義はありませんが、「録音・録画」とほぼ同義だと考えて良いでしょう。)(i)の「放送」「公衆に伝達」の意味は、上記の定義規定(第2条)によるので、著作権法でいうと、録音権・録画権(著作権法第91条)、放送・有線放送権(同92条)、及び送信可能化権(同92条の2)が本条に対応する規定になります(詳細は【前編】参照のこと)。前編でも説明したように、著作権法上、実演家の権利にはワンチャンス主義や放送のための固定などの特別な取り扱いが定められていますが、ワンチャンス主義は固定された実演に関する規定であることを考えれば、本条については、著作権法は基本的には対応していると言えそうです。
他方、第7条以下では、「視聴覚的固定物に固定された実演」に関する規定が続きます。ここは著作権法上例外的な取り扱いが定められている分野なので、まとめて見てみましょう。
第7条 複製権
実演家は、視聴覚的固定物に固定された実演について、あらゆる方法及び形式による直接的又は間接的な複製を許諾する排他的権利を享有する。
【合意声明:デジタル形式の実演の利用等、デジタル環境についても適用される。実演をデジタル形式により電子的媒体に蓄積することは、複製に該当する。】
第8条 譲渡権
(1) 実演家は、視聴覚的固定物に固定された実演の原作品及び複製物について、販売又はその他の譲渡により、公衆への供与を許諾する排他的権利を享有する。
(2) この条約のいかなる規定も、固定された実演の原作品又は複製物の販売又はその他の譲渡(実演家の許諾を得たものに限る。)が最初に行われた後における(1)の権利の消尽について、締約国が自由にその条件を定めることを妨げるものではない。
第9条 商業的貸与権
(1) 実演家は、実演家自身による又は実演家の許諾による頒布の後においても、締約国の国内法が定める視聴覚的固定物に固定された実演の原作品及び複製物の公衆への商業的貸与を許諾する排他的権利を享有する。
(2) 締約国は、その商業的貸与が、実演家の排他的複製権を著しく侵害するような当該固定物の広範な複製をもたらすものでない場合には、(1)の権利を与える義務を免除される。
【第8条及び第9条に関する合意声明:「原作品又は複製物」とは、譲渡権及び商業的貸与権に関しては、有体物として流通に供されるような固定された複製物のみを指す。】
第10条 固定された実演を利用可能にする権利
実演家は、視聴覚的固定物に固定された実演を、公衆の構成員が個別に選択した場所及び時においてこれにアクセスできるように、有線又は無線の方法により、公衆に利用 可能な状態にする排他的権利を享有する。
第11条 放送及び公衆への伝達に関する権利
(1) 実演家は視聴覚的固定物に固定された実演を放送し又は公衆に伝達することを許諾する排他的権利を享有する。
(2) 締約国は、WIPO事務局長に寄託する通告において、(1)に規定する許諾権の代わりに、視聴覚的固定物に固定された実演の放送又は公衆への伝達のための直接的又は間接的な使用について、衡平な報酬を請求する権利を創設することを宣言することができる。また、締約国は、衡平な報酬を請求する権利の行使に関する条件をその法令において設定することを宣言することができる。
(3) 締約国は、(1)又は(2)の規定の適用に関しこれを特定の使用のみに適用すること、その適用を他の方法により制限すること、又は(1)及び(2)の規定をまったく適用しないことを、WIPO事務局長に寄託する通告において、宣言することができる。
【通告の方法については第18条に規定】
視聴覚的固定物に固定された実演(例えばDVDとして販売されている映画や舞台作品を頭に思い浮かべてください)について、実演家に排他的権利を与えています。第7条は複製権(ダウンロードを含む)を、第8条は譲渡権を、第9条は商業的貸与権(レンタル店でのレンタル)を、第10条は利用可能化権(ネット配信など)、第11条は放送権及び前述の「公衆への伝達」権を、それぞれ与えています。実演家が排他的権利を有するということは、実演家の許諾なしに複製等の行為はできないことを意味し、それは多くの場合、許諾の条件として実演家に対する対価の支払いが生じることを意味します。(なお、第10条にある「利用可能化権」(Right of Making Available)は著作権法上の「送信可能化権」と内容が若干異なるという議論があるのですが、本コラムでは割愛します。)
第7条から第11条の規定では、各締約国の国内法による例外的な取り扱いが認められている場合があります。商業的貸与権(第9条)については、「実演家の排他的複製権を著しく侵害するような当該固定物の広範な複製をもたらすものでない場合」には、国内法が実演家に商業的貸与権を与えなくても良いと規定されています。「公衆への伝達」権については締約国の国内法による裁量の幅がより広く認められています。排他的権利の代わりに報酬請求権を認めるという規定も可能です。この場合、公衆への伝達について実演家に許諾を求める必要はありませんが、実演を利用された実演家は、利用者に対して報酬を求めることができます。さらに、また、「公衆への伝達」について実演家の排他的権利(許諾権)も報酬請求権も認めないことも可能と規定されています。各締約国は、上記のような例外的な取り扱いが認められていない場合には、実演家に対して条約所定の排他的権利を与えなければならないことになります。
■ ワンチャンス主義と北京条約の整合性
ここで思い出していただきたいのが、著作権法上のワンチャンス主義です。著作権法は、実演家に対して録音権・録画権(著作権法第91条)、放送・有線放送権(同92条)、送信可能化権(同92条の2)、譲渡権(同95条の2)、商業用レコードの貸与権(同95条の3)といった排他的権利を与える一方で、対象となる実演が最初に利用される時にだけ実演家に許諾のチャンスを認める、いわゆる「ワンチャンス主義」を採用しています(詳細は【前編】参照)。端的な例が映画の著作物の取り扱いで、映画の著作物に録音・録画された実演については、その映画の以後の利用について、実演家の録音・録画権、放送権、譲渡権等が及びません(同91条2項、92条2項2号ほか)。実演家からすれば、最初の出演の時に映画の二次利用の条件も話し合っておくべき、ということです。
では、北京条約の第7条から第11条の規定と、著作権法のワンチャンス主義の整合性はどのように考えるべきでしょうか?この問題を扱っているのが次の第12条です。
第12条 権利の移転
(1) 締約国は、国内法において、国内法に定められるところにより交わされた実演家と当該視聴覚的固定物の製作者間の契約に他の定めがない限り、一度実演家が自らの実演を視聴覚的固定物に固定することに同意した場合には、本条約第7条から第11条に規定する排他的許諾権は当該視聴覚的固定物の製作者が有し若しくは行使し又は当該製作者に移転するものとすることを規定することができる。
(2) 締約国は、自らの国内法の下で製作された視聴覚的固定物に関し、そうした同意や契約は、書面により、かつ契約の両当事者又は適正な代理人によって署名されることを要するものとすることができる。
(3) 上記の排他的許諾権の移転とは関わりなく、国内法又は個別的、集合的若しくはその他の契約等をもって、第10条及び第11条を含む本条約により定められた実演のいかなる利用についても、ロイヤリティ又は同等の報酬を受け取る権利を実演家に与えることを定めることができる。
※ 原文には項目番号がありませんが、説明の便宜上
(1),(2),(3)と項目分けしております。
利用者の側から見れば、やれやれ一安心・・・といったところでしょうか。まず(1)は、各締約国が、実演家が自らの実演を視聴覚的固定物に固定することに同意した場合について、国内法で、視聴覚的固定物の製作者(以下「製作者」)と実演家が別途契約しない限り、(i)製作者が実演家の排他的許諾権を有する(権利が製作者に原始的に帰属する)、または(ii)製作者が実演家の排他的許諾権を行使する(実演家は権利を持つが、行使できるのは製作者)、または(iii)実演家の排他的許諾権が製作者に移転する(実演家が原始的に権利を取得した後に権利が移転する)、という規定を置くことができるとしています。
(2)は、国内法によって、(1)に規定する実演家と製作者間の契約や実演家の同意は書面による必要があると規定することができる、と定めています。
(3)は、実演家の権利を製作者に移転させるか否かとは関係なく、国内法で、実演の利用に対する実演家の報酬請求権を認めることができる、という規定です。
いずれも「国内法で○○と定めることができる」という規定なので、各締約国の裁量に任されています。
一見すると、日本法上の「ワンチャンス主義」も北京条約で認められているといえそうです。ところが、日本法の規定の文言をよく見ると、ワンチャンス主義が適用される場面においては、実演家の権利が製作者に帰属したり、製作者に譲渡されたり、または製作者が実演家に代わって実演家の権利を行使できるわけではなく、そもそも実演家の権利が発生しないと読めるのです。ワンチャンス主義があらわれている条文の例を見てみましょう。
著作権法
第91条 実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。
2 前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。
上記の条文を読むと、第1項が実演家に録音・録画権を認め、第2項は実演家の許諾を得て映画の著作物に録音・録画された実演については、第1項の規定を「適用しない」と書いてあります。そもそも(固定された)映画上の実演については、実演家の録音・録画権が発生しない、という意味だと読めます。北京条約では各締約国の裁量でこのような規定を定めることも認められているのか、それとも、日本法の規定は北京条約で与えられている裁量を逸脱しているのか、さらなる検討が必要だと思われます。
また、第13条において、文学的及び美術的著作物の著作権の保護に関して国内法令において定めるものと同一の種類の制限又は例外を、実演家の保護に関しても定めることができると規定されていますので、著作権法が、規定している実演家の権利の各種制限規定(著作権法第102条)も、基本的には北京条約で認められているといえます。ただし、第13条において、それらの制限・例外は「実演の通常の利用を妨げず、かつ実演家の正当な利益を不当に害しない特別な場合に限定しなければならない」と規定されていますので、権利制限規定の正当性については改めて確認する必要があるでしょう。
技術的手段に関する義務(第15条)、及び権利管理情報に関する義務(第16条)については、本コラムでは省略します。保護期間(第14条)、方式(第17条)、及び 留保及び通告(第18条)の概要については、上記文中で触れたとおりです。
■ このまま加盟していいのか?
以上で検討したように、今のところ、北京条約の各規定と現行著作権法の間に大きな隔たりはないように見えます。では、日本としては、実演家の権利に関して著作権法の規定に手を加えることなく北京条約に加盟してしまえば良いのでしょうか?
前編でも述べたように、現行著作権法上、視聴覚実演における実演家の権利は、音楽実演における実演家の権利と比較すると、不利な状況に置かれていると言わざるを得ません。日本俳優連合や芸団協のような視聴覚実演の実演家側は、以前から繰り返しこの点を指摘し、著作権法の「改善」を求めています。たしかに映像作品には数百名を超える実演家が登場するものも珍しくなく、その全員と権利処理しないと映像の二次利用ができないとなると問題も生じるでしょう。しかし、個人的な見解ですが、筆者には、視聴覚実演の利用者側が、実演家と正面から契約書を交わすよりも、法解釈や実務慣行に頼って権利処理を回避することに腐心しているような側面もあるように見えます。ビジネス慣行も含めて、現状が必ずしも理想的だとは思えません。著作権法と北京条約との整合性を確認していく一方で、「条約に加盟できれば良い」という単なる合格点を目指すのではなく、実演家、製作者、そして実演がもたらす感動を享受する聴衆のためにより良い法制度や実務は何かを考え、改善できる点があれば改善していくことが望ましいと考えています。。
以上
法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
※文章内容には適宜訂正や追加がおこなわれることがあります。