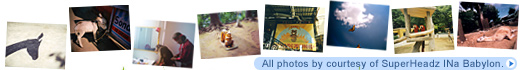2025年10月17日
「農to the World!〜輸出とライセンスで世界へ挑む日本の種苗〜」
弁理士 城田晴栄 (骨董通り法律事務所 for the Arts)
1.はじめに
こんにちは!農業知財大好き、農ガール弁理士です。2022年に種苗法のコラムを書いてから、かれこれ3年が経ちました。改正種苗法施行からも4年半、そろそろ何か動きがあるかしら?と思っていた矢先に、大きな話題が飛び込んできました。
去る9月25日、山梨県知事が当時の農林水産大臣に、農林水産省(以下、農水省)が検討しているとされるシャインマスカットの海外ライセンス(海外で、品種やブランド・栽培技術など知的財産の利用を許諾・許可すること)に対する要望書を提出したとの報道がありました。これが大きな話題となり、「国が生産者を裏切るのか?」「日本の産地が輸出できていないのにどうして先に他国が正規栽培できるのか?」「日本の品種・技術・ブランドが他国に売られる!」といった、農家や産地を心配する声や公平性に対する疑問の声がインターネット上に溢れました。
まるで諸悪の根源かのような言われようの『シャインマスカットの海外ライセンス』ですが、果たして海外ライセンスにはデメリットしかないのでしょうか。この先、日本の種苗を守りながらも我が国の農作物が世界に打って出るにはどうすればよいのでしょうか。シャインマスカットを頬張りながら、この美味しさを取り巻くこれからを考えてみたいと思います。
2.日本の種苗の優秀さと狙われる知財
日本の農作物は、世界で高い評価を受けています。特にアジア地域では、1990年代半ばから、巨峰や藤稔といったブドウの品種が人気を博してきました。そして、近年では、シャインマスカットが爆発的な人気となっていることは周知の事実です。ブドウのみならず、「紅ほっぺ」(いちご)や「べにはるか」(サツマイモ)などの日本発の品種は、研究者や生産者が長い年月をかけて改良に改良を重ねて生み出した「知的財産」であり、日本の農業の高い技術力や創造力、あくなき探求心が具現化されたものと言っても過言ではありません。
しかし、こうした優秀な種苗は、取締りが緩かった2010年頃までに海外へ無断で持ち出され、中国や韓国で大規模栽培されるようになり、東南アジア各地では、日本産ではない日本発祥の農産物が大量に出回る事態となっています。その被害は、ライセンス収入を逃した経済的損失に加え、市場に低品質な農産物が日本産と偽られて出回った(※2)ことによる風評被害も含めると、計り知れない規模と推察されます。種苗の海外への無断持ち出しは、日本の農業の未来や農業知財を脅かす非常に深刻な問題であり、種苗法改正は、こうした事態を打開するための最初の期待の一手でした。
3.改正種苗法(2020年12月公布2021年4月施行)のポイント~おさらい~
ここで、改正種苗法について、主なポイントをおさらいしてみましょう。
① 海外持ち出し制限と栽培地域の制限
改正種苗法では、登録品種の種苗について、指定国以外への持ち出しや、指定地域以外での栽培を制限する仕組みが導入されました。制限内容は農水省のHPで公表されます。
② 栽培地域の指定
作物の品種によっては、その品質が土地の気候や風土と密接に関連しているものがあります。法改正で、種苗の登録時に栽培地域の指定を可能としたことで、前号の栽培地域の制限とも関連して、無秩序な拡大による品質低下を防止するとともに、特定地域に紐づいたブランド力を守ることを目指しています。この考え方は、地理的表示(GI)とも通じるところがありますね。
③ 自家増殖の許諾制
改正前まで生産者に認められていた無許諾の「自家増殖」(収穫物から種や苗を採取して次の作付けに使用する行為)は、法改正後、登録品種については、原則として権利者の許諾が必要となりました(※3)。これにより、登録品種の無許諾増殖を防ぎ、権利者が開発に投下した資本を回収しやすくするとともに、安心して新品種の開発に投資することができるようになりました。一方で、生産者が不慣れな許諾取得をしなくてはならなくなり、手続き面・知識面の負担軽減が課題として浮上しました。
④ 表示義務と罰則強化
種苗の販売に際し、登録番号や輸出制限・栽培地域制限の有無を表示することが義務付けられました。この登録品種版の「タグ」は、購入者にとっての品種に関する正確な情報の提示且つ証明であるとともに、流通の透明性を高める仕組みとなっており、実効性の担保のため、これらの表示義務に違反する等一定の場合には刑事罰の対象ともなり得るよう、制度の整備がなされました。
⑤ 制度運用の改善
手続きの電子化などの環境整備、審査の質の向上や迅速性の工夫など、出願のしやすさと審査の信頼性の両立を目指して制度運用の改善がなされました。これにより、小規模品種開発者も制度を利用しやすくなり、開発のすそ野の広がりが期待されます。
4.改正種苗法~現場はどう動いたか~(2025年現在)
種苗法改正当時、生産者の反発が特に大きかったのは、前章③の自家増殖の許諾制でした。「登録品種が作れなくなるのではないか」「許諾料が高額になり、経営を圧迫するのではないか」といった改正種苗法に対する不安の声があちこちで上がったのは記憶に新しいところです。
農産物の市場では、一度新品種が出ると、それほど時間をかけずにその新品種が主流となることが多いため、生産者は将来の売れ行きを見越して、栽培品種を切り替えることがよくあります。しかし、新品種の導入時のみならず、もし、翌年以降の自家増殖時にも費用が必要となると、そのコストは生産者にとってそれなりの負荷となります。そのため、生産者は種苗を自家増殖し、次の作付以降は種苗自体には費用がかからないという形でコストを削減してきました。自家増殖の許諾制が想像以上の反発となったのは、そうした理由も大きかったようです。
さて、改正種苗法施行から4年半、新制度が動き出し、農業の現場でも少しずつ変化が起きているようです。
例えば、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構は、種苗法改正当初から、農作物の品質維持や種苗の海外持ち出し等の対策を行うとともに、登録品種の自家栽培について、生産者が手続きしやすいよう配慮した許諾を行っています。
また、長野県などでは県が主体となり、品種を一元的に管理する仕組みを整えており、品種によっては、その利用や栽培に長野県内限定という制限をかけるなど、種苗の流出を防ぎ、ブランドを保護する施策を行っています。
他にも、多くの自治体やJAが、生産者にとって利用しやすく、且つ、流出を防いで地域の農業活性化につながるような制度設計に工夫を凝らしています。
5.「海外ライセンス指針」とは?
さて、話はシャインマスカットの海外ライセンス問題へと戻ります。
これまでも、「種苗の海外流出」はたびたびニュースになってきましたが、「種苗の海外ライセンス」は、大きなニュースとして取り上げられることがありませんでした。そのため、今回の山梨県知事の要望書提出のニュースを見て、まるで農水省が突然思い付いて動き出したかのように思った方もいるかもしれません。しかし、農水省は実は2023年12月には既に「海外ライセンス指針」を公表しています(※1)。この指針は、ただ単に、日本の品種を海外で作らせるか否かではなく、管理の方法や方針、目標とするところを明確に示し、侵害抑止・国内農業振興・輸出促進を実効性のあるものとすべく、今後の海外ライセンスの道しるべとして示したところに非常に意義があるものです。
この指針で明らかにされている、海外ライセンスが目指す明確なモデルの柱は、『我が国の優良品種が海外で無秩序に生産・販売される現状から、国内農業振興・輸出促進に寄与する管理された生産・販売への転換を目指す。(「海外ライセンス指針(別紙1)」より引用)』というものであり、具体的に以下の3つのポイントが掲げられています。
① ライセンスを受けて海外で種苗の知財を利用する者(パートナー)の経済的メリットに基づく侵害監視が機能し、日本品種の無断栽培の実効的な抑止を確保。
② 輸出と連携した海外ライセンス生産・販売を通じ、海外市場での日本品種の周年供給を実現するなど輸出促進に寄与。
③ ライセンス生産・販売を通じ相応のロイヤルティを確保し、新品種の開発投資など農業振興に還元するサイクルを実現。
これらを通じ、日本産品の販路・市場の拡大、国内農林水産・食品分野の付加価値・稼ぎの向上に寄与する。(以上、「海外ライセンス指針(別紙1)より引用」)
6.日本の果実輸出の構造的障壁
ここで気になるのが前章②の「ライセンスが輸出促進に寄与する」という点です。山梨県知事は、要望書に対する先日の記者会見で「ライセンスの前にまずは輸出環境の整備を」と訴えている通り、現時点で、農産物の輸出はクリアすべき構造的課題が多く、それらを解決しないまま、ライセンスから輸出促進へ繋げることはハードルが高いように思われます。
① 制度・規制面
農産物の輸出には、病害虫リスクを防ぐための厳しい検疫条件がある上、国ごとに基準が違うため、手続きや検査に時間やコストがかかるといった問題があります(※4)。
② 関税障壁
国によっては高関税、輸入枠などがあり、日本の農産物が割高になりやすい状況です。
③ 鮮度保持・輸送コスト、コールドチェーンの不足
果物は日持ちしないため、航空便が基本となり、高額な輸送費により価格競争力が削がれる上、国によっては冷蔵輸送網が不十分で、品質劣化リスクが高いという問題があります。
④ 小規模分散生産と人材・ノウハウ不足
日本の農家は小規模で分散しており、輸出に向く「安定供給・大量ロット」を組みにくい上、輸出手続きや販路の開拓を担える人材が限られています。
⑤ 他国産の低価格品との競争
中国などではシャインマスカットのような人気品種が既に大量生産・低価格供給されており、単純な価格競争では太刀打ちできない状況です。
こうした構造的課題を抱えたまま且つその解決の提示もないままに、海外ライセンスが輸出促進に寄与すると言われても、農業関係者からすれば、輸出機会をさらに奪われるだけと感じるのは無理のないことです。
この点、海外の品種ビジネスに、ライセンスが輸出促進に寄与する理由を説明するヒントがあるように思います。世界では、「輸出」と「ライセンス」は必ずしも対立するものではないビジネススタイルが広がっています。世界の品種ビジネスは今、どのように動いているのでしょうか。
7.世界のブドウ品種ビジネスに学ぶ
実は、世界の品種ビジネスの成功事例では、「輸出」と「ライセンス」は相互補完の仕組みとして機能しています。海外ライセンスの議論を考えるうえで、事例として、世界のブドウ産業の動向を検討してみると、多くの示唆が得られます。
アメリカのSun WorldやIFG(Bloom Fresh傘下)、スペインのSNFLなど、世界には、ブドウなど主要品目において市場をけん引するグローバル育種企業があり、これらの企業は品種の開発のみならず、例えばSun Worldのように「苗の供給」「栽培技術の提供」「ブランド使用のライセンス」を一体化させたビジネスモデルを確立し、世界中の生産者と契約関係を築いているような企業も存在します。各国の生産者は、これらの育種企業とのライセンス契約に基づいて、苗木使用料や販売量に応じたロイヤルティを支払って人気品種を正当に栽培し、品種のブランド力にあずかって安定した収入を得ることができています。それだけでなく、世界各地へライセンスする際、収穫の季節差を活用して栽培・出荷を行うことで、一年を通じた果実の供給を実現している企業もあります。つまり、輸出できる地域での販売機会を維持しながら、自ら輸出できない季節や地域にライセンスをし、自らの輸出と組み合わせて市場を維持・拡大するという戦略です。
このように、各国の育種企業は、自国の優良品種を守りながら、輸出の限界を補い、世界中で安定的に販売・供給するためにライセンスビジネスを巧みに活用し、ブランド力を国際的に維持していることが分かります。
この点、日本のブドウ産業は、素晴らしい品種を生み出す力に優れている一方で、こうしたライセンスビジネスの整備やそれと輸出との連携では大きな後れをとってしまいました。海外ライセンス指針では、この後れを取り戻し、海外での保護と攻めを戦略的に実現するため、次のような実践的提言がなされています。
8.海外ライセンス実践のポイント
「海外ライセンス指針」で掲げられている実践提言のうち主要なものを見てみましょう。
① ターゲット市場の選定
ターゲットとする市場は無作為に広げるのではなく、輸出と競合しない地域、あるいは検疫・物流の制約により日本から輸出しにくい地域であったり、生産・出荷時期の調整により、輸出との棲み分けや連携ができる市場を選ぶことが提言されています。先日の海外ライセンス問題では、正式発表はされていないのに、一部でニュージーランドという具体的な国名が報道されました。これは、日本と生産時期がずれる南半球での生産が、年間を通じた供給体制の構築に有効という観点から広まった話かもしれません。
② 生産国とパートナーの選定
侵害リスクの低減のためには、品種保護制度の有無やその運用実態、ライセンスビジネスの成熟度、その他のリスクを十分に分析してライセンスする国を選定する必要があります。併せて、我が国の輸出促進に理解があり、輸出との連携を図るための販売管理能力がある者、契約を遵守する信頼できる者を「パートナー」に選定することが何より重要です。ライセンスは契約であり、これを破られて無断栽培が拡大してしまっては元も子もないからです。
また、無断栽培の効果的抑止の観点から、侵害リスクが高い国に敢えてライセンスを検討する余地もあります。この場合、その国の信頼できるパートナーに限定してライセンスをし、パートナーに経済的メリットが生まれることで、パートナーによる監視体制が機能するようにしたり、その国からの輸出を制限して、日本からの輸出拡大を狙う考えも示されています。
③ 他の知的財産制度の活用
シャインマスカットの無断栽培が拡大してしまった原因の一つに、日本の権利者が、中国で種苗の権利確保をしなかったことが挙げられます。失敗を繰り返さないためにも、今後の種苗は、直接的な保護手段としての品種登録を行うのはもちろんですが、それだけでなく、商標権・GI・営業秘密・特許権などの関連する知的財産制度を組み合わせ、ライセンス対象を多層化することも重要です。指針においても、日本産品の品質・ブランド価値の源泉となる栽培技術を、重要な知的財産として適切に保護・管理することが提言されています。
ここで、先述したアメリカの育種企業であるIFGの事例を見てみます。IFGは「Sweet Sapphire(スウィートサファイア)」というブドウの品種の権利を持っていますが、この品種もシャインマスカット同様、2010年代後半から中国で無断栽培されていました。しかし、同社は、中国で植物品種保護権を取得し、この権利に基づく訴訟の結果、無断栽培者に対する生産停止命令を勝ち取りました。さらに、IFGは「Sweet Sapphire」と「甜蜜蓝宝石」(Sweet Sapphireの中国語商標)の商標権を確保し、商標の保護も並行して行っています。まさに、多面的な保護の実例といえるでしょう。
④ ロイヤルティの回収と再投資の仕組みづくり
契約の締結に際しては、種苗販売時の売上の回収にとどまらず、ロイヤルティを新品種開発や地域振興に還元するサイクルの確立を目指して、収穫量等に応じた長期的ロイヤルティ契約を結ぶことが重要です。日本の農業人口は減る一方であり、後継者不足に悩まされている現実がありますが、ロイヤルティがもたらす再投資の循環により、農業で生活していける未来が見えたり、或いは、新品種の開発で農業全体を活性化できれば、若者の農業従事者の増加も期待できます。
9.終わりに~「守る」から「広げる」へ~
ここまで見てきた通り、海外ライセンスをはじめ、日本の農業を守るための仕組みづくりは今まさに進化の途上にあります。一方で、制度を整えるだけでなく、制度を十分に活かせる環境づくりも欠かせません。輸出に関する障壁や課題の解消はもちろん、日本の農家の多くが小規模経営である現実を踏まえ、海外との交渉や契約に不安を抱く生産者のサポート体制を整えることも重要な環境づくりです。制度があることと制度が使えることの溝を埋めるため、国や自治体、民間一体となっての連携を期待したいところです。
また、今回の海外ライセンス問題では、一部で、「海外ライセンス=品種の流出や譲渡」という誤解もあったようです。しかし、ライセンスは、信頼できる契約のもとで正当に種苗を使わせて品種を守る仕組みであり、むしろ無秩序な無断栽培に対抗するための有効な手段です。先日配信された海外ライセンス問題を取り上げた番組で、生産者の方が「海外ライセンスは雲の上の人が決めた」と発言していましたが、これこそが生産現場のおいてきぼりを如実に表した発言にほかなりません。国には、海外ライセンスの意義を生産者に丁寧に説明する義務と、農業関係者の理解と信頼を築く努力、それらすべてが構築された上での海外ライセンスの実施が強く求められます。
改正種苗法が目指した守りは、日本の農業を支える重要な礎です。そして、その先に位置する「海外ライセンス指針」は、守りから、管理された拡大へと進むための新たなツールです。もともと優秀な日本の種苗ブランドが、種苗法による保護と正しいライセンスという活用のバランスの下、世界に羽ばたく好機が到来しています。
守りから攻めへ、日本から世界へ、そして未来へ!
日本の種苗ブランドがより強く、より豊かに育つための農業知財物語からますます目が離せません。
【参照(2025年10月12日現在確認)】
(※1)「海外ライセンス指針」
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/attach/pdf/kaigai_license-1.pdf
(※2)「China Daily / 2024-11 / 30」
https://epaper.chinadaily.com.cn/a/202411/30/WS674a3f5aa3105c25b38ee1f0.html
(※3)権利者が包括許諾を示す場合など、許諾を求めない登録品種もあり得ます
(※4)検疫条件は国ごとに異なります
諸外国に植物等を輸出する場合の検疫条件一覧(早見表)
https://www.maff.go.jp/pps/j/search/e_hayami_kamotu.pdf
以上
■ 弁理士 城田晴栄のコラム一覧
■ 関連記事
「秋の夜長の農密なお話
~流出に立ち向かう農業知財法~」
2022年11月22日 弁理士
城田晴栄(骨董通り法律事務所 for the Arts)
法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
※文章内容には適宜訂正や追加がおこなわれることがあります。