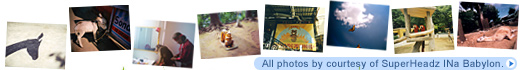2020年3月18日
「『相殺』を使いこなすためには? ~改正民法の施行に備えて~」
弁護士 北澤尚登 (骨董通り法律事務所 for the Arts)
もうすぐ2020年4月1日、債権法(民法)改正の施行期日です。そこで今回は、「相殺」がどのような場合に使えるのか、改正後の条文に即して、シンプルな仮想事例をもとに解説します。近時の新型コロナウィルス問題などで、企業の資金繰りが苦しくなると、このような事例が生じやすくなることも考えられます。その意味でも、ご参考になれば幸いです。
▶まず、以下のような事例で考えてみましょう。
X社は、舞台公演のプロデュースをしています。2020年5月1日、ある公演のために、舞台セットの制作をY社に代金100万円で発注しました。X社は同日、Y社の資金繰りを助けるために30万円を貸し付けてもいます。同日付で「セットの制作代金は、完成したセットの引渡しから30日後に、貸付金を差し引いて支払う」という契約をしています。
5月10日、裁判所からX社に「債権差押命令」が送られてきました。A社が、Y社に対する資材代金債権の未払を理由に、Y社のX社に対するセット制作代金債権を差し押さえたとのことです。
5月20日、X社はY社から、完成したセットを受け取りました。その後、5月30日になって、A社がX社に100万円の支払を請求してきました。
X社は、誰にいくら支払うべきでしょうか。
X社が、A社に対する30万円の貸金債権(相殺する側が持っている債権=「自働債権」といいます)と、100万円の代金債務(相殺される側が持っている債権=「受働債権」といいます)を相殺することができれば、差額の70万円をA社に支払えばよいことになります。
他方、相殺ができないとすれば、X社はA社に100万円支払った上で、Y社に30万円を請求することになりますが、Y社からは回収できないリスクがあるため、この方法はX社にとって最善とはいえなさそうです。
そこで、差押えの場合における相殺の可否について改正民法の条文をみると、511条1項は以下のようになっています(下線は筆者)。
差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。
上記の下線部分により、「受働債権の差押え前に取得した債権を自働債権とする相殺は可」とされています。上記の事例では、X社(=第三債務者)は受働債権の差押え(5/10)よりも前に自働債権を取得(5/1)しているので、両者を30万円の限度で相殺することができ、A(=差押債権者)には残額の70万円を支払えばよい、と解されます。
なお、上記の下線部分は、法改正によって追加された文言です。改正前から判例によって認められてきた内容ではありますが、改正民法では明文化され、わかりやすくなったといえましょう。
ちなみに、上記の条文に続く511条2項には、「差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる」と定められています。これは、法改正により相殺の権利を拡張した規定といわれています(上記の事例には直接関係しないものと思われますが、参考までにご紹介します)。
▶次に、上記の事例における(2020年)5月10日の出来事を、以下の事実に置き換えたらどうなるでしょうか。
5月10日、A社からX社に「債権譲渡通知」が送られてきました。Y社が、X社に対するセット制作代金債権をA社に譲渡した、とのことです。
債権譲渡の場合における相殺の可否については、改正民法の469条1項に以下の定めがあります。
債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。
この規定は、511条1項とパラレルになっており、「受働債権が譲渡された場合、その対抗要件具備前に取得した債権を自働債権とする相殺は可」とされています。ここでの「対抗要件具備」とは、債権の取得や回収において第三者に優先するための要件を備えることで、確定日付のある書面での通知などがこれに該当します。 上記の事例では、X社(=債務者)は受働債権の譲渡の対抗要件具備(=Xへの通知)(5/10)よりも前に自働債権を取得(5/1)しているので、やはり両者を30万円の限度で相殺することができ、A(=譲受人)には残額の70万円を支払えばよい、と解されます。
なお、X社とY社との契約書には「Y社はセット制作代金債権を譲渡できない」という条項があったが、A社はそれを知らなかった、という場合はどうでしょうか。 債権譲渡を制限(禁止)する特約がある場合について、改正民法の466条2項・3項は以下のようになっています。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
上記の事例では、A社(=譲受人)が特約の存在を知らなかったことについて重大な過失がある場合には、X社はA社への支払を拒絶できる(Y社に70万円支払えばよい)ことになります。例えば、A社がY社との間でXY間と同種の契約書を最近締結したことがあり、そこでは定型的に譲渡禁止特約が定められていた、などの場合は、重過失ありといえる可能性もあるでしょう。
他方、A社に重過失がない場合は、A社への支払を拒絶できないため、A社に対して上記の相殺を主張する(その結果、70万円をXに支払う)ことになるでしょう。
以 上
■ 弁護士 北澤尚登のコラム一覧
法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
※文章内容には適宜訂正や追加がおこなわれることがあります。