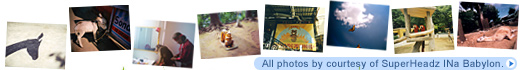2015年9月30日
「ファッションと著作権の微妙な距離
―次元の狭間で揺れる両者の関係」
弁護士 中川隆太郎 (骨董通り法律事務所 for the Arts)
一般に、衣服などのファッションアイテムは「実用品」に分類され、そのデザインの著作権による保護は原則として難しいといわれていますが、実は近年日米で相次いで重要な裁判例が現れており、その関係性に改めてスポットライトが当たっています。今回のコラムでは、ファッションと著作権との間の「微妙な距離」について、最新の裁判例を切り口に再考したいと思います。
● これまでのルール
従来の大多数の裁判例では、実用品のデザインの保護については、通常の美術の著作物よりも一段高いハードルを課す考え方が採られています。この考え方も、詳細に検討するといくつかの考え方に分かれていますが*、近時有力となりつつある考え方は、そのデザインについて、①実用品の実用的側面と分離して把握することができること、及び②美的鑑賞の対象たりうる美的特性を備えることを条件に、著作物としての保護を認める考え方です(例えば、知財高裁平成26年8月28日ファッションショー映像事件判決)。
* 代表的なものは、「純粋美術と同視しうる場合」に保護するというものです。この点を含め、実用品のデザインの著作権による従来の保護のあり方や、後述するTRIPP TRAPP事件判決の影響については、拙稿「問い直される実用品デザインの保護のルールーTRIPP TRAPP事件知財高裁判決のインパクト」(コピライト2015年9月号)で論じているので、詳しくはこちらをご覧下さい。
このうち、上記条件①の考え方の根底にあるのは、「実用面と分離できないデザインを保護すると、その機能についても同時に著作権による独占を認めることになり妥当でない(機能については他のしかるべき法律により保護すべき)」という価値判断です。また、その背景には、「実用品のデザインは実用面と分離して把握することができ、かつ、独立して存在しうる絵画、図形または彫刻の特徴を持つ場合に限り保護される」という明文のルールを持つ米国著作権法の影響があると指摘されています*。そこでまずは、どういった場合に「デザインが実用面と分離可能」と判断されるのか、米国での議論を少し見てみましょう。
* 他方、条件②については米国法には見られない考え方です。従来は、条件②に関し、意匠法とのすみ分け等を理由に、高度の芸術性といった高いハードルを設定する見解が通説的見解でしたが、近時は、条件②を求めない見解(高林龍『標準著作権法(第2版)』46頁)や、高度の芸術性などは不要で、見て楽しむ程度の鑑賞性で足りるとする見解(吉田和彦「応用美術の保護について」中山信弘ほか『竹田稔傘寿記念論文集 知財立国の発展へ』476頁ほか)も広がりを見せています(前記拙稿参照)。
● 「物理的な分離」と「概念的な分離」
米国法で「実用面と分離可能」とされるひとつのパターンは、実用品のデザインとその実用面とを物理的に分離できる場合です。こちらは比較的単純で、例えば、英国車ジャガーのボンネットについたジャガーのマスコットの彫刻は、自動車という実用品のデザインの一部ではあるものの、彫刻部分を分離しても、残った本体部分は引き続き自動車としての機能を発揮できます。このとき、彫刻部分のデザインは物理的に自動車の実用面と分離可能とされます。
米国法で「実用面と分離可能」とされるもうひとつのパターンは、実用品のデザインとその実用面とを「概念的に分離」できる場合です。・・・といわれても、すぐにピンと来る方はきっと少ないかと思います。この点は米国でも議論が割れており、百家争鳴ともいうべき状況です*。以下、具体的に見てみましょう。
* 例えば、「デザインの芸術的特徴が機能を発揮するために必要不可欠でなければよい」という考え方や、「デザインの芸術的特徴が主で実用的機能が従であればよい」という考え方、「芸術的特徴を分離しても実用品としての機能が損なわれなければよい」という考え方などがあります。
ファッションデザインと「概念的な分離」に関する考え方としては、最近では、米国著作権局の公式見解とともに、Jovani Fashion事件における第2巡回区控訴裁の判断(2012)がしばしば参照されています。
まず著作権局の公式見解(および同局による著作権実務概要第3版)によれば、「概念的に分離可能」とは、デザインの芸術的特徴と実用品とが並存し、完全に別の作品(一方が美術作品で他方が実用品)として認識される(言い換えれば、その特徴について、実用品の基本的な形状を損なうことなく、実用品から分離し、独立して思い描くことができる)ことを意味するとされます。そして、衣服やバッグなどのファッションアイテムのデザインであっても、そのファブリックやテキスタイル、プリントのデザイン(柄、パターンなど)のような2次元のデザインは、「概念的に分離可能」で著作権により保護されうるとされています。
これに対し、衣服の立体的なデザイン(3次元のデザイン)は、身体の保温や保護といった機能を持つ実用品である衣服と物理的にも概念的にも分離できず、著作権では保護されないものと整理されています。
このように、著作権局は衣服のデザインについて、次元の違いにより著作権による保護/不保護を区別する境界線を引いているといえそうです。
● 美しい装飾は「実用的」なのか?
この境界線付近をさまよう微妙なケースが問題となったのが、2012年に出されたJovani Fashion事件における第2巡回区控訴裁の判断です。下記のようなプロムドレス(ダンスパーティー向けのドレス)のデザインが著作物として保護されるかが争われたこの事件で、第2巡回区控訴裁は、ドレスの胴体部分の表面に施されたシークイン(スパンコールのような光を反射する服飾素材)やクリスタルの装飾、ウエスト部分のフリル状のサテン、そしてスカート部分のチュール(網目模様の薄手の生地)のレイヤーに関する装飾的なアレンジについても、「実用品と概念的に分離できない」として、保護を否定しました。
しかし、「ドレスの基本的な立体的形状がドレスの持つ衣服としての機能性(身体を覆う等)と分離できない」とのロジックは(賛否はさておき)理解しやすいですが、美しさを追求する色合いの強い装飾についても「実用的」であるとはどういう意味なのでしょうか?
 |
| 著作物性が争われたJovani Fashion社のプロムドレス |
この点について、第2巡回区控訴裁は「衣服は身体を覆うだけでなく、『装飾的な機能』も提供している」「Jovani Fashionのドレスの装飾的なデザインの要素は、特別な日のための衣服としてのドレスの機能を高めるために用いられている。つまり、ここでは、特別な日のために、とりわけ魅力的な方法により身体を覆うという機能が、審美性と融合している」と説明しています。つまり、ここでの「実用性」「機能」とは、純粋に技術的・工業的な機能だけでなく、社会的なコンテクストにおいてある物の美しさが果たす役割・効用を含む、広い概念として用いられています(その分、著作物性は認められにくくなります)。
しかし、このような物の魅力を増すという美しさの効用までも「実用的機能」とし、結論としてそのデザインにつき著作権による保護の対象外とすることは本当に適切か、筆者としては疑問もあります。この考え方によれば、例えば絵画や彫刻などの美術品でさえも、それが飾られた空間を彩り、より魅力的にする効用を持つ以上、保護の対象外となりかねないように感じるからです。
● 一石を投じる新たな判決 ―Varsity Brands事件第6巡回区控訴裁判決
そんな中、先月(2015年8月)、Jovani Fashion事件における装飾的機能論に対して同様の疑問を呈し、正面からこれを批判した注目すべき判決が米国で出されました(Varsity Brands事件)。この事件では、チアリーディングのユニフォーム(下記参照)のデザインの著作物性が争われ、第6巡回区控訴裁は、これらのデザインは実用品であるユニフォームと「概念的に分離可能」と判断しました。
 |
この中で、被告(Star Athletica社)は、Jovani Fashion事件を引用しつつ、「これらのデザインは、チアリーディングのユニフォームの装飾的機能という実用的側面と分離できない」と主張しました。しかし、裁判所は、
・ そのような考え方では、ほとんどの芸術作品が著作権で保護されなくなる。例えば、このような機能論の下では、モンドリアン【筆者注:抽象画で著名なオランダの画家、ピエト・モンドリアン】の絵画でさえ、それが飾られる部屋を装飾する以上、保護されないことになってしまう。
・ 装飾的機能が「実用的側面」だとすると、あらゆるファブリックデザインは衣服をより魅力的にするために用いられる以上、著作物として保護されないことになってしまうが、これらが著作物として保護されることは実務上確立されている。
などと批判し、デザインの装飾的機能は、実用品の「実用的側面」との分離可能性を否定するものではないと結論付け、Star Athletica社の主張を退けました。
その代わりに、第6巡回区控訴裁は、実用品のデザインが「概念的に分離」できるかどうかについて、従来の様々な考え方のいずれかひとつに限定せず、それらのハイブリッドにより判断するというアプローチを採用したうえで、米国著作権法の条文に基づき、以下の5つの問いにより判断するとしました。
① そのデザインは、絵画、図形、彫刻の著作物か?
② ①を満たすとして、それは「実用品」のデザインか?
③ その実用品の「実用的側面」とは何か?
④ デザインを見る者が、絵画、図形または彫刻的な特徴を、その実用的な側面(上記③)から分離して識別できるか?
⑤ 絵画、図形または彫刻的特徴は、実用品の実用的な側面から独立して存在できるか?
そして、④および⑤について、前記のような「概念的な分離」に関する様々な見解のいくつかを援用しつつ、特に上記の著作権局の判断基準が有益であると述べました。そのうえで、上記の「チアリーディングのユニフォームは、そのグラフィックデザインがなくともチアリーディングのユニフォームと識別でき、デザインがユニフォームの衣服としての機能を高めていない」「このようなデザインの代替可能性は、消費者が各デザインを識別できることを裏付ける。その結果、デザインの特徴とユニフォームとは並存し、別の作品として認識される」とし、結論として、同デザインはユニフォームの実用的側面と「概念的に分離可能」と判断しました。
このように、衣服のデザインがどのような場合に実用的側面と分離できるとされるのか、その考え方は米国でも確立されてはいませんが、上記のような米国での議論(2次元と3次元による区別や、デザインの装飾的要素と実用性・機能性の問題)は、今後の日本における議論を深化させるうえで参考になるように思います。そこで参考までに、これらの米国での議論を前提に、日本におけるこれまでの裁判例について手短に振り返ってみましょう。
● ファッションデザインの著作権に関するこれまでの日本の裁判例
これまでに日本においてこの点が正面から争われた主な裁判例としては、佐賀錦袋帯事件(京都地裁平成元年6月15日判決)とTシャツ事件(東京地裁昭和56年4月20日判決)があります。冒頭でご説明したように、従来の大多数の裁判例では、実用品のデザインの保護については、通常の美術の著作物よりも一段高いハードルを課す考え方が採られており、これらの裁判例でも同様です。
まず、佐賀錦袋帯事件では、下記のような着物の帯のデザインについて著作物性が否定されました。
 |
京都地裁は、実用品のデザインについて「対象物を客観的にみてそれが実用性の面を離れ一つの完結した美術作品として美的鑑賞の対象となりうる」場合に限り保護されるとしたうえで、原告の袋帯のデザインについて、
帯の図柄としてはそれなりの独創性を有するものとはいえるけれども、帯の図柄としての実用性の面を離れてもなお一つの完結した美術作品として美的鑑賞の対象となりうるほどのものとは認め難い
としました。ここでは「帯の図柄としての実用性」に言及があるものの、どのような位置付けで考慮されたのか、判決文からは定かではありません*。仮に、帯のデザインの持つ「装飾的な機能」(デザインの美しさによって帯をより魅力的にするという効用)をもって帯の実用的側面と捉え、これと分離して鑑賞の対象になるとは認められないとしたのであれば、前記の米国Jovani Fashion事件での第2巡回区控訴裁の考え方に近いともいえそうですが、その場合、Varsity Brands事件における第6巡回区控訴裁の批判がそのまま当てはまることになりそうです。
* 「着物の帯という商品の性格から絵柄の表現が実質的に制約されていることを考慮したのではないか」との指摘もあります。(榎戸道也「著作権法による応用美術の保護」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務 第4巻〔著作権法・意匠〕』(新日本法規出版、2007))
これに対し、Tシャツ事件では、下記のようなサーファーを描いたTシャツのプリントのデザインについて著作物性が認められました。
 |
東京地裁は、実用品のデザインは「専ら美の表現を追求して制作された...美的創作物である」場合に限り保護するとし、「実用...目的のため美の表現において実質的制約を受けて制作されている...もの」は著作物として保護されないとしています。そのうえで、上記のTシャツのデザイン(プリントの柄)について、
左下方に花の模様を、中心にサーフアーのスピード感あふれる波乗りの姿を描いたもので、全体として十分躍動感を感じさせる図案であり、...客観的、外形的にみて、テイーシヤツに模様として印刷するという実用目的のために美の表現において実質的制約を受けることなく、専ら美の表現を追求して制作されたものと認められる
として、著作権による保護を認めています。ここでも、実用目的による実質的制約とは具体的に何を指すか不明確ですが、結論として著作物性を認めている点も考慮すると、プリント柄のデザインによってTシャツがより魅力的になること(装飾的機能)をもってTシャツの実用的側面と捉えた判決ではないと見ることもできそうです。
● 知財高裁が突如打ち出した新機軸
さて、最後に、今年の4月に知財高裁が突如打ち出した新機軸についてご紹介しましょう。これまで見てきたような、実用品のデザインについて一段高いハードルを課す考え方に正面から異論を唱えた、TRIPP TRAPP事件知財高裁判決です。同判決は、実用品のデザインについても他の場合と同様に、作者の個性が発揮されていれば著作物として保護すべきという考え方に立ち、結論としても実用品である椅子(TRIPP TRAPP)は著作物であると判断しました。この考え方は、学説上は有力に唱えられていましたが、裁判例で採用されたのはこの判決が最初であり、大きなインパクトとともに受け止められています。
この考え方によれば、ファッションアイテムのデザインは、(2次元か3次元かの違いにかかわらず、また、実用品の持つ実用的な側面との分離可能性といった要件を課されることもなく)作者の個性が発揮されてさえいれば保護される可能性があることになり、「個性が発揮されている」か否かのボーダーの定め方次第では、従来と結論が大きく異なる可能性があります。ファッションデザインの著作権による保護を広く求める立場からは、歓迎すべき判決といえます。他方で、他の裁判所が本判決の考え方に追随し、この考え方が定着するのか、本判決はあくまで「異端児」となり、従来の裁判例の趨勢は変わらないのか、まだ定かではありません。また、このTRIPP TRAPP事件判決のように実用品のデザインについて広く保護することについては、著作権による機能の独占への懸念や意匠制度没却への危惧、さらには、ブログやSNSなどでの一般ユーザーによる著作権侵害増加への憂慮の声も少なくないところです(ご関心のある方は、前記の拙稿をご覧ください)。
以上見てきたように、ファッションと著作権をめぐっては、デザインの装飾的機能をどう考えるのか、そして、そもそも実用品のデザインに関するTRIPP TRAPP事件知財高裁判決の考え方は定着するのか、といった「要継続検討」の論点が残されており、両者の関係は今後も当面は揺れ続けそうです。両者の間の「微妙な距離」がどうなるのか、引き続き動向をフォローしていきたいと思います。
以上
■ 弁護士 中川隆太郎のコラム一覧
法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
※文章内容には適宜訂正や追加がおこなわれることがあります。