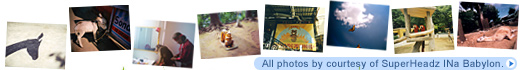2009年3月23日
「(続)全世界を巻き込むGoogleクラスアクション和解案の衝撃 Q&A編」
弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts)
前回のコラムが予想を超える反響を各方面からいただき、この間、Google和解の問題はメディアを大きく飾った。紹介される筆者(福井)のコメントも、ある所ではGoogleの説明不足を非難し、別な所では和解歓迎と、各紙の料理しだいで実に変幻自在。
当方のコメントなど警鐘でも歓迎でもどちらでも良いが、Google和解を論ずる発言には時に内容への誤解も見られ、また、この間さまざまな方からご質問もいただいた。そこで、特に多いご質問や重要と思われる部分について、簡単なQ&Aを作成してみた。
Q:自分の作品がディジタル化されているかどうか、どうやって調べるのか?
A:和解管理サイト(http://books.google.com/booksrightsholders/)に行き、自分(自社)のアカウントを作ってログインすると、「検索と申し立て」ページで作品データベースにアクセスできる。たとえばある作家の名前を入力すると、先方が把握している作品のリストがずらりと出る。試みに「Haruki Murakami」なら、日本と海外の書籍が943冊ヒットした(名前の表記法によって結果は変わる)。このリストをダウンロードすると、各書籍がすでにディジタル化されているか、Googleが絶版とみなしているかがわかる仕組みだ。日本語版リストの説明には誤訳があり、英語ページから出力するリストがわかりやすい。
ちなみに村上春樹をして、3月23日時点で日本語書籍はほぼ全て「絶版」扱い、英語の翻訳書にも予想以上に「絶版」扱いが見られる。日本語の「絶版」本の中では、「羊をめぐる冒険」「パン屋再襲撃」「ねじまき鳥クロニクル」など、かなりの点数がすでにディジタル化されている。
Q:この作品データベース上の作品が、今回の和解の対象なのか?
A:これはよくある誤解だが、和解通知書の5項にも、データベースは和解対象を網羅していないと注記がある。クラスアクションの原告側弁護士も、データベースは和解対象の書籍の一部しかカバーしていない発展途上のもので、そこに乗っていなくても今後のGoogleのスキャン対象になると明言した。あくまでも、2009年1月5日以前に出版された米国でも著作権が守られる各国の書籍や挿入物は対象なのである。
仮に今はもれている書籍があっても、権利者自らがデータベースに書籍と権利者の情報を追加入力できる。というより、米国での利用からお金を受け取ったり、あるいは米国での利用をやめさせようとすれば、こちらから情報提供することになるだろう。
Q:米国で絶版の書籍だけが、今回の和解の対象か?
A:これも違う。対象は、2009年1月5日以前に出版された米国でも著作権が守られる各国の書籍や挿入物である。ただ、米国で絶版扱いのものはGoogleがデフォルトでネット配信でき、米国で流通しているものは権利者の同意がないとネット配信できないという違いだ。
たとえば、すでにアメリカ国内でネット流通している日本の書籍なら、「絶版」とみなされない可能性はある。しかし、多くの日本書籍のように、アメリカから日本の「Amazon.co.jp」などにアクセスして購入し、日本から出荷されるようなものは、つまりは日本からの個人輸入である。これを「アメリカ国内で流通している」と呼ぶのはおそらく難しく、それが日本書籍の高い「絶版認定率」の原因ではなかろうか。
2009/4/28付記: Google日本担当者の最近の説明によれば、少なくとも「Amazon.co.jp」などを経由してオンラインで日本から取り寄せ可能な書籍などについては、「アメリカで流通中」と分類されるよう(=デフォルトでネット配信されないよう)、同社では仕組みを見直し中だという。ただし、和解管理サイト上のGoogle分類に基づくデータベースでは、現在もほとんどの日本書籍は「絶版認定」のままなので、今後、実際に分類がどう変わるか注目される。
2010/4/5付記: すでに広く報道されている通り、その後、国内外での批判や指摘を受けて、2009年11月13日付で和解案は大幅に修正された。対象となる書籍の範囲は、①米国著作権局に著作権登録されているか、②カナダ・英国・オーストラリアで出版されているものに限定されたうえ、なお裁判所の審議が続いている。この間の経緯とわが国への影響については、本コラムの北澤尚登「Google Booksクラスアクション和解 アップデート ~経緯・現状・今後の展開(電子書籍ビジネスとの関係をふまえて)~」を参照。
Q:「収益の63%」とはどういう意味か?
A:どうも、この「収益」という言葉を、Googleの経費を控除した後の「利益」の63%と思われた方も一部にいるようである。和解契約の用語はrevenueで、これは「収入」又は「収益」と一般に訳され、おおむね入ってくるお金の総額を指す。和解契約ではその計算方法も明記されていて(4.5(a)項、1.86項、1.87項ほか)、まぎれもなく原則として総収入の63%を権利者側に渡すというのだ(ただし版権レジストリの手数料込み)。「高率の収益配分」と書いた所以である。
Q:ベルヌ条約があることが裏目に出て、こんな和解に巻き込まれたのか?
A:ベルヌ条約などがあるから日本の書籍の著作権も米国で守られ、米国で著作権が守られているからクラスアクションに含まれることになったのは、事実だ。しかし、「裏目」というのは少し違う。仮に条約関係がなく、日本の書籍の著作権が米国で守られていなかったら、そもそもGoogleだろうが誰だろうが、自由にその書籍を使って配信ビジネスができる。日本の作家や出版社には何をいう権利もない。
各種条約があるから、権利侵害と言ったり収益配分を受けられる余地があるのだ。
その意味で、和解の効力が日本の権利者に及ぶのはクラスアクションという制度の性質によるのであって、ベルヌ条約があることが「裏目」に出たとはいえないだろう。
Q:クラスアクションだから、ベルヌ条約には違反しないということか?
A:厳密にみて違反しないかは、実はよくわからない。
ベルヌ条約は加盟国に、「同盟国の著作者に作品の排他的権利を与えなさい」と求める。他方、米国クラスアクションの制度上、共通の利害関係者が(裁判所の承認を条件に)和解に拘束されるのは事実だ。しかし、拘束された結果、個別に同意をしていない権利者の作品まで米国で配信される結果になった時、それがベルヌ条約の原則に違反しないかどうかは、ややグレーに思える。
これは研究者には魅力的なテーマかもしれない。しかし現実の世界で、仮に裁判所が全世界の書籍に及ぶという現在の和解案を正式承認してしまえば、果たして誰かが「それはベルヌ条約違反だ」という厄介な裁判をあえて起こし、戦い抜くだろうか。「和解に巻き込まれたくなかった」という権利者が仮に後から出て来たら、そんな難しい裁判闘争をするより簡単な解決方法がありそうだ。自分の書籍を全て「削除」してしまえばいいのである。
こう考えると、ベルヌ条約との関係はおもしろいテーマではあるが、焦点はやはりこの夏、(6月11日の最終公聴会を経て)裁判所が和解を正式承認するか、であるように思える。
Q:5月5日が過ぎたら、確定的に和解内容に拘束されるのか?
A:上記で書いた通り、裁判所が和解を正式承認すれば、確定的にそうなるだろう。
では、裁判所が和解を正式承認しない可能性はあるのか。
裁判所は、この和解条件(各国の権利者に対して今おこなわれている通知の方法や内容を含む)をすでに暫定承認している。自分が暫定承認した全世界での通知プログラムのためにGoogleは巨額の費用を使っているのだから、常識的には、裁判所はすんなりとこの和解を正式承認しそうである。
ただ、最近の権利者に対する説明の不親切ぶりを見ると、本当に大丈夫なのか心配になる。和解管理サイトの説明を見て、何が起こっており、自分はどういう手続をとればいいのかすぐ理解できる日本の権利者は、おそらく極めて少数であろう。新聞に掲載された「法定通知」に至っては、そもそも日本語がよくわからない。
建前上は、和解承認は各国の権利者が十分な説明を受けることが前提になるはずだ。であれば、Googleを含む関係者はもう少し一般人に理解できる説明を尽くすべきだろう。
2009/5/8付記: 一部の作家などの求めを受け、ニューヨーク連邦地裁は4月28日、和解からの離脱期限を約4ヶ月延期して2009年9月4日とする決定をおこなった。Googleなどの訴訟関係者は60日延期を主張していたが、これを超える延長になった格好である。あわせて最終公聴会も10月7日の午前10時に延期された(http://www.scribd.com/doc/14741799/SDNY-Order-Extending-Deadline-to-September-4)。秋口までに和解案の周知と理解を広げられるか、訴訟関係者の努力が問われそうだ。
2010/4/5付記: すでに広く報道されている通り、その後、国内外での批判や指摘を受けて、2009年11月13日付で和解案は大幅に修正された。対象となる書籍の範囲は、①米国著作権局に著作権登録されているか、②カナダ・英国・オーストラリアで出版されているものに限定されたうえ、なお裁判所の審議が続いている。この間の経緯とわが国への影響については、本コラムの北澤尚登「Google Booksクラスアクション和解 アップデート ~経緯・現状・今後の展開(電子書籍ビジネスとの関係をふまえて)~」を参照。
Q:作品の流通が進むから、基本的にいい話なのでは?
A:確かに、埋もれた絶版書籍を人々が読むことができる機会が広がるなら、社会にとっても権利者にとっても素晴らしいことだ。
問題は、その権利を管理し、流通をコントロールするのは誰かである。
先に述べた通り、世界中の権利者は、米国での利用からお金を受け取ったり、あるいは米国での利用をやめさせようとすれば、自ら和解管理サイトのデータベースを充実させざるを得ない。おそらく、この和解案の最もすごい(あるいは恐ろしい)ところは、この点である。今は単に不完全な「書誌情報」データベースに過ぎないものが、権利者自身に情報を持ち寄らせる状況を作ることで、1年後には世界一の「書籍の権利情報」データベースになっているかもしれないのだ。
そのデータベースと使用料分配ルートを握るのは、Googleの資金で米国の作家と出版社が運営する「版権レジストリ」。日本人には今ひとつピンと来ない名前だ。いずれはもっとわかりやすく、「全世界書籍版JASRAC」と呼ばれるようになるかもしれない。レジストリは、「ブック検索」に限らず他の事業者とのビジネスでも権利者を代理する方針が、通知書には記載されている。
なぜそれが米国主導、Google主導なのか。このことにある種の焦燥感を呼び起こされた人もいるかもしれない。
Q:米国流のルールを世界に押し付けるのは、自分勝手ではないか?
A:確かに今回の和解は、米国とは契約慣行から違う他国の事情に配慮しない、自国の関係者の都合だけを考えた「手打ち」の面が否めない。
しかしこれは珍しいことではない。悪名高い構造改革協議からビジネス契約の「裁判管轄」条項に至るまで、ことが国際的なスタンダード作りとなると、米国の手法はしばしば自国本位で人騒がせだ。言いかえれば、したたかで辣腕なのだ。
それに対して勝手だと反発するだけでは、今後も米国の後塵を拝することになろう。日本の関係者にいま必要なのは、読者と、作家や出版社のために、書籍の最善の再流通ビジネスモデルは何かという、ビジョンとしたたかな戦略ではないだろうか。
11世紀、「源氏物語」で幕を開けた書物の千年紀とそこで生きた無数の先人達は、我々に汲んでも尽きない豊かな文化の水脈を残してくれた。これを受け継ぎ、次の世代にどんな水脈を残すのか。書物の次なる千年紀ははじまったばかりである。
(2009.4.28 一部加筆)
2011/3/25付記: 2011年3月22日、ニューヨーク連邦地裁は和解案修正後の長い「黙考」の末、修正和解案を不承認とする決定を下した(決定原文:http://www.nysd.uscourts.gov/cases/show.php?db=special&id=115)。 Denny Chin判事は決定中で、学校・研究者・障害者によるアクセスや作家・出版社による新たな収入可能性など、書籍のディジタル化自体の価値は強調する。他方で、権利者が通知しない限り「絶版書籍」などのオンライン配信を許す現在の「オプトアウト」方式では、権利者不明の「孤児作品」の扱いを含め、Googleが競争者たちに対して圧倒的優位に立つ点など多くの懸念点を挙げる。その結果、「和解案は公正でも十分でも合理的でもない」と結論し、関係者に対して、事前に権利者の許諾を得る「オプトイン」方式への和解案の再々修正を強く勧めた内容。 再々修正の成否は現時点で未知数であり、この決定により、すでに1500万冊がスキャン済みとされるGoogleの巨大電子図書館構想をめぐる訴訟は、海図なき航海に突入したといえる。
以上
■ 弁護士 福井健策のコラム一覧
法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
※文章内容には適宜訂正や追加がおこなわれることがあります。