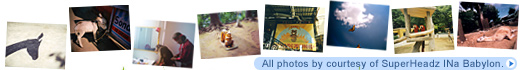2017年4月25日
「侮るなかれ 国際契約における紛争解決条項」
弁護士 岡本健太郎 (骨董通り法律事務所 for the Arts)
1.裁判と仲裁
外国企業との国際契約において、相手方ともめて争いとなった場合の主な解決方法には、「裁判」や「仲裁」があります。「(民事)裁判」とは、当事者間の紛争を裁判所が解決する手続をいい、「仲裁」とは、当事者間の紛争を私人である仲裁人が解決する手続をいいます。多くの方にとっては、仲裁より裁判の方がイメージしやすいのではないでしょうか。
裁判所は国内外を含めて各地にありますが、国際仲裁を行う仲裁機関は限られています。主なものには、日本商事仲裁協会(JCAA)のほか、パリに本部を有する国際商業会議所(ICC)、ロンドンに本部を有するロンドン国際仲裁裁判所(LCIA)、ニューヨークに本部を有するアメリカ仲裁協会(AAA)等があります。また、アジアにも、シンガポール国際仲裁センター(SIAC)、香港国際仲裁センター(HKIAC)等があります。
裁判と仲裁は、第三者による紛争解決手続である点で共通しますが、上記のように、裁判は国(裁判所)が行う一方、仲裁は民間の仲裁機関が行う点が異なります。その他、概要、以下のような違いがあるといわれています。
| 裁判 | 仲裁 | |
| 公開・非公開 | 公開が原則 | 非公開が原則 |
| 当事者の合意の要否 | 相手方の同意なく訴訟を提起できる | 仲裁を行うには相手方との合意(仲裁合意)が必要 |
| 上訴の有無 | 上訴できる | 上訴できない(終局解決) |
| 手続 | 手続法(民事訴訟法等)に従う | 当事者間で手続を決定できる |
| 判断者の選任 | 当事者は裁判官を選任できない | 当事者が仲裁人を選任できる |
| 言語 | 各法域の言語が使用される | 当事者が言語を選定できる |
また、一概には言えませんが、裁判よりも仲裁の方が、費用が高くなる場合があります。仲裁では、当事者が仲裁人の費用を負担する上、国際商事紛争の経験豊富な弁護士(≒報酬が高い弁護士)が仲裁人に選任される場合も多いからです。試しにICCのウェブサイトで、「請求額を100万ドル(1ドル=110円換算で約1億1000万円)、仲裁人1名による通常の仲裁」の費用を算定してみたところ、仲裁機関に支払う仲裁費用、すなわち仲裁人費用と管理費用の合計額は62,714ドル(約690万円)でした(ご参考までに、日本の裁判所の印紙税額は、請求額が1億1000万円の場合、35万円です)。
この仲裁費用は平均額のようですので、より高額になる場合もあるでしょう。また、(裁判も同じですが)その他にも弁護士費用、渡航費等の諸経費がかかります。中には、「国際仲裁は、費用がかかるため、請求額が数千万円や数億円の事案ではお勧めしない」といった意見もあるようです。
2.裁判と仲裁の選択
日本企業間の国内契約では、紛争解決方法として、裁判が選択される場合がほとんどと思われます。では、外国企業との国際契約では、裁判と仲裁のどちらを選択すべきでしょうか。これについて唯一の正解はなく、ケースバイケースです。契約当事者の力関係も影響するでしょう。ただ、相手方の提案を安易に受け入れることはお勧めしません。選択した内容次第では、裁判や仲裁に至らない場合であっても、事前交渉が有利にも不利にもなるからです。
例えば「日本での裁判」が選択された場合には、両当事者は、最終的には、日本の裁判所で、日本語で訴訟を行うことになります。相手方の外国企業は、裁判所に提出する書面や証拠を日本語に翻訳する必要がありますし、来日するとなれば渡航費や宿泊費もかかります。外国企業は、こうした負担を嫌がり、話し合いでの解決を希望してくるかもしれません。他方で、「相手国での仲裁」が選択された場合には、日本企業としては、(日本の弁護士に加えて)現地の弁護士を雇う必要がある上、上記算定のように仲裁費用が嵩む懸念もあることから、相手国での仲裁を避けるために早期妥結を優先し、結果的に交渉力が弱まってしまうかもしれません。
ただ、実務上、国際紛争の解決方法としては、仲裁が選択されることが多いようです。その理由として、国際的な裁判においては送達の手間と時間がかかる、書面や資料の現地語訳が必要となるといった裁判の手続負担も挙げられますが、大きな理由の一つに、強制執行が挙げられます。裁判は強制執行が制限されやすい一方、仲裁は強制執行しやすいのです。裁判(判決)の強制執行は、国家の権限の発動でもあることから、各国の国内法に従った判決の承認手続が必要となるなど、外国では制限され得るのです。アメリカでは州毎に対応が異なる可能性がありますし、中国、タイ、インドネシア、マレーシア、インドのほか、ベルギー、ロシア等でも、日本の裁判所の判決の強制執行は認められていないようです。判決の批准国での強制執行を認める国際的な枠組みとしてハーグ条約(国際裁判管轄の合意に関するハーグ条約)がありますが、批准国は現時点でEU諸国、メキシコ、シンガポール等の30か国に留まっており、日本は批准していません。つまり、管轄合意に従って日本で裁判を行って有利な判決を得られたとしても、肝心の相手国で強制執行できない可能性が出てきます。
他方、仲裁(その判断)は、ニューヨーク条約(外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約)の締結国間では、所定の要件を満たせば強制執行できます。ニューヨーク条約の締結国は現時点で約160か国に及び、アメリカ、カナダのほか、英国、フランス、ドイツ等のEU諸国は締結済みです。また、アジアでも、日本や韓国のほか、中国、タイ、インドネシア、マレーシア、インドといった、上記の判決の強制執行を認めない国々も締結しています。アート・エンターテインメント分野の国際契約に登場する相手国は、概ね網羅されているのではないでしょうか。
また、仲裁は、近年、新たな制度の導入により、利用しやすくなっているようです。例えば、JCAA、SIAC、ICC等の仲裁機関は緊急仲裁人制度(Emergency Arbitrator)を導入しています。「緊急仲裁人制度」とは、仲裁機関が迅速に緊急仲裁人を選任し、仮差押え等の暫定保全措置を行う制度です。「暫定保全措置」は、強制執行の対象の確保、証拠保全、紛争の一次的な維持・回復等を行う裁判上の仮処分に似た制度ですが、裁判上の仮処分よりも様々な内容の申立てが可能といわれています。ただ、ニューヨーク条約の加盟国でも暫定保全措置の強制執行はできず、相手方の任意の履行を期待せざるを得ない場合もあるようです。アメリカ、ドイツ、フランス、シンガポール、香港等、暫定保全措置に裁判上の仮処分と同様の効力を認める国や地域も増えているようですが、その取扱いは国や地域毎に異なりますので、個別の確認が必要です。
また、近年、JCAA、SIAC等の仲裁機関が簡易手続(Expedited Procedure)を導入しています。「簡易手続」とは、早期の紛争解決と仲裁費用の低減を目的とした、簡略化した手続によって仲裁を行う制度です。ICCも、本年(2017年)3月1日から簡易手続を導入しており、この簡易手続を利用した場合には、証人尋問、ディスカバリー(強制的な証拠収集手続)等を行うことなく、約6か月以内に仲裁判断が出されるようです。ICCでは、請求額が200万ドル(約2億2000万円)以下の紛争が簡易手続の対象となり、請求額が200万ドルの場合、通常手続の仲裁費用(平均92,059ドル。約1010万円)と比べると、簡易手続の仲裁費用は平均79,890ドル(約880万円)と若干安くなります。「まだ高い!」と感じられるかもしれませんが、こうした制度の導入により仲裁がより使いやすいものとなり、紛争解決条項として仲裁が選択され、また、実際に仲裁に至るケースも増えていくかもしれません。
3.条項
さて、契約書の規定である「紛争解決条項」に話を移します。一般論としては、紛争解決条項として、少なくとも手段(裁判か仲裁か)や場所・手続(裁判所の場所、仲裁機関・手続等)を規定しておくことをお勧めします。特に、上記のとおり、仲裁を行うには当事者間の合意(仲裁合意)が必要ですので、仲裁を希望する場合はなおさらです。契約書に仲裁合意が規定されていなくても、後から当事者で合意すれば仲裁は可能ですが、紛争が生じた後では仲裁合意を得ることが困難な場合もあるからです。
シンプルな仲裁合意には、①仲裁機関・手続や②仲裁地を規定しますが、その他に、③言語、④仲裁人の数(1人又は3人)、⑤費用負担(敗訴者負担か折半か)、⑥事前交渉義務(仲裁前に、当事者間で紛争解決に向けて交渉すること)等を規定する場合があります。このうち①仲裁機関や② 仲裁地は重要な交渉ポイントですが、「仲裁の範囲」や「終局性」にも注意が必要です。仲裁の範囲を「契約に関する全ての紛争」ではなく「契約違反に基づく紛争」に限定してしまうと、理論上、裁判といった仲裁以外の方法でも「不法行為に基づく損害賠償請求」や「不当利得に基づく利得金請求」が可能となり得るのです。また、仲裁判断に納得できない相手方による訴訟の提起を防止するため、「仲裁で最終的に解決する」というように終局性を確保しておく必要があります。
例えば、JCAAでは、以下のようなモデル仲裁条項を作成しています。
この契約から又はこの契約に関連して、当事者の間に生ずることがあるすべての紛争、論争又は意見の相違は、一般社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、(都市名)において仲裁により最終的に解決されるものとする。
また、モデル仲裁条項に倣った、裁判を選択する場合の規定例(管轄合意)は以下のとおりです。
この契約から又はこの契約に関連して、当事者の間に生ずることがあるすべての紛争、論争又は意見の相違については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
このように、仲裁合意も管轄合意も広めに規定しておくのが通例ですが、あまり広く書きすぎるのも問題です。島野製作所が米国アップル本社に対して損害賠償等を請求した事件で、東京地裁(東京地判2016年2月15日中間判決)は、アップルの管轄合意条項を無効と判断しているのです。アップルは、基本契約において、以下のような管轄合意条項(一部省略)を規定していました。
①両当事者間に紛争が生じる場合、両当事者は...上級管理職によりまず当該紛争の解決を図るよう試みる。
②(当事者間の和解交渉で60日以内に解決できない場合)両当事者はカリフォルニア州...で実施される...調停により当該紛争の解決を求める。
③各当事者は、調停開始後60日以内に紛争を解決できない場合、カリフォルニア州...の州又は連邦裁判所で訴訟を提起できる。各当事者は当該裁判所の専属的裁判管轄権に...付託し、当該裁判所に提起される訴訟や訴訟手続における判決が確定的であること...に合意する。
④(省略)
⑤ 別の書面による契約が適用されない限り、紛争が本契約に起因又は関連して生じているか否かにかかわらず、本条の条件が適用される。
上記の規定例とアップルの管轄合意条項を比較すると、上記の規定例は、対象が「この契約」に限定されている一方、アップルの管轄合意条項の①や⑤は、「両当事者間に紛争が生じる場合」、「紛争が本契約に起因又は関連して生じているか否かにかかわらず」などと規定し、当事者間の紛争であれば全てその対象に含まれるように規定されています。文字どおりに適用されるなら、将来にわたって両者間の全ての紛争がアップルの本拠地で裁判されることになるため、極めて強力な条項と言えるでしょう。なお、アップルの管轄合意条項は、多段階紛争処理条項といわれるもので、①まずは上級管理職による60日間の和解交渉を行い、②解決しない場合に、60日間の調停を行い、③それでも解決しない場合に訴訟に至るというものです。
裁判所は、国際裁判管轄の合意は「一定の法律関係に基づく訴え」に関する必要があるところ(民事訴訟法3条の7第2項及びその適用以前の条理)、アップルの管轄合意条項は、対象とする訴えについて原告・被告間の訴え以外に限定もなく、「一定の法律関係に基づく訴え」を定めていないため無効としました。
4.補論(準拠法)
紛争解決条項と並んで規定されることが多いのが、準拠法です。「準拠法」とは、民事紛争に適用される法律です。国際契約では、各当事者の居住国等も異なることから、いずれの法律に従って契約を解釈すべきかが問題となるのです。日本では、契約書に準拠法の規定がある場合、通常、それに従って準拠法が決まりますが(法の適用に関する通則法7条)、契約書に規定がない場合には、契約内容に最も密接な関係がある国の法律が準拠法となります(同法8条1項)。
また、裁判等で準拠法が争いとなることもあり、近年でも、ピカソ等の著作権を管理するフランス法人が、日本企業に対して、オークション用カタログに無断でピカソ等の作品の写真が掲載されたなどとして損害賠償等を求めた事案で、フランス法人が「著作権の譲渡を受けた」と主張していたことから、その著作権移転の判断に関連して準拠法が問題とされました(知財高判2016年6月22日判決)。本コラムではこのご紹介に留めますが、著作権に関する準拠法は、帰属、譲渡、ライセンス等の場面で様々な考え方があって複雑ですし、仮に契約書に規定したとしても、そのとおりにならない場合もあります。ただ、準拠法の規定がないと当事者間で準拠法について争いになる可能性が高まりますので、(特に自己に有利な法律を準拠法として規定できるような場合には)契約書に記載しておくことがセオリーではあります。
本コラムが、契約書検討の際のヒントとなれば幸いです。
以上
■ 弁護士 岡本健太郎のコラム一覧
法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
※文章内容には適宜訂正や追加がおこなわれることがあります。