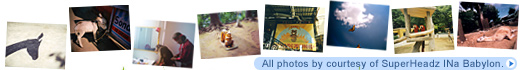2010年8月24日
「音楽著作権侵害の判断手法について -『パクリ』と『侵害』の微妙な関係」
弁護士 唐津真美(骨董通り法律事務所 for the Arts)
■「そう言えば、似てるよね」を発端に
この夏休み、上海万博を見るために海を越えた方もいると思います。本コラム執筆現在で累計入場者数が4000万人を超えている上海万博は、まずは成功といえるのではないでしょうか。
ところで、上海万博開演直前の今年4月、万博PRソングの盗作疑惑が話題になったのを覚えていますか?最初は中国のインターネット上で疑惑が指摘されたといわれています。You Tubeには、万博PRソングと盗作されたと言われる日本の楽曲を交互に聞かせるような投稿まであったので、聞き比べてみた方もいるのではないでしょうか。筆者も聞いてみた1人です。(感想は省略します。)
今回の盗作疑惑自体は、外部からはよくわからない「大人の解決」で落ち着いたようですが、仮に本件のような事件が日本で裁判になった場合、裁判所としては、判決書に音源データを添付して「聞いたらわかるように2つの楽曲は似ているので・・・」と書くわけにはいきません。2つの曲を聴いた時の「そう言えば、似てるよね」という印象と、法的な著作権侵害の成立の間には、いくつものステップがあるのです。今回は、音楽著作権(編曲権)侵害の存否を裁判所が判断する手法について、書いてみたいと思います。
■著作権侵害とは
著作権は、しばしば「権利の束」と言われています。著作権者には、「著作権」という1つの権利があるのではなく、複製権、上演・演奏権、公衆送信権、翻案権(翻訳権・編曲権・脚色権等)といったいくつもの権利(支分権)が与えられているからです。著作権者ではない者が、著作権者に無断で、支分権の対象となる行為(翻訳・編曲・脚色等)を行った場合に、著作権侵害が問題になります。ある楽曲について「既存楽曲に類似している」というクレームを受ける場合、通常その法的構成は、編曲権(著作権法27条)の侵害であると考えられます。
■過去の裁判例がしめした判断基準 -「記念樹」事件
異なる楽曲として公表された2つの楽曲間の複製または編曲の成否が争われた先例は乏しく、現行著作権法に基づく裁判例で公表されているものとしては、ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件(東京高判昭和49・12・24)及び記念樹事件(一審・東京地判平成12・2・18、控訴審・東京高判平成14・9・6)程度のものです。このうち、記念樹事件の控訴審判決(以下「参考判決」といいます)は、編曲権侵害の判断基準及び判断例を初めて示したものと理解されています。
記念樹事件は、1992年に発表されテレビ番組のエンディング・テーマとして放送されていた楽曲「記念樹」が、1966年にCMソングとして発表された既存楽曲の盗作であるとして、この既存楽曲の作曲者と著作権者である音楽出版社が、「記念樹」の作曲家に対して損害賠償を請求する訴訟を提起した事件です(以下、参考判決において著作権侵害の主張を受けた楽曲を「判決楽曲」といい、原曲とされた楽曲を「判決原曲」といいます)。
後述するように、参考判決の内容については批判もありますが、実務上東京高裁の判決は相当程度重視されますので、今後同種の案件が訴訟となった場合は、参考判決の採用した定義や判断手法が適用される可能性が高いと考えられます。そこで、以下、この参考判決の考え方を少し詳しく見てみましょう。
■編曲権侵害の成立要件
参考判決は、著作権法上の「編曲」の意義について、「既存の著作物である楽曲に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が原曲の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物である楽曲を創作する行為をいう」と述べています。(「パクリ」という言葉の意味を裁判所が説明すると、こんなに小難しい表現になるわけです。)
その上で、参考判決は、編曲権侵害の成否を、(1)楽曲の表現上の本質的な特徴の同一性(類似性)、(2)依拠性、の2つの問題に分けて検討しています。
■「類似性」の判断手法
参考判決は、楽曲の類似性の判断においては、楽曲ごとに表現上の本質的な特徴を基礎付ける要素が異なるのだから、原曲とされる楽曲において表現上の本質的な特徴がいかなる側面(旋律(メロディー)、和声(ハーモニー)、リズム・テンポ、形式(フォーム)等)に見いだし得るかを検討した上で、その表現上の本質的な特徴を基礎付ける主要な要素に重点を置きつつ、双方当事者の主張する要素に着目して判断するほかないと述べています。同時に、少なくとも旋律を有する通常の楽曲に関する限り、著作権法上の「編曲」の成否の判断において相対的に重視されるべき要素として主要な地位を占めるのは旋律である、との判断を示しています。
以上を前提として、参考判決は、判決楽曲と判決原曲の旋律の類似性を判断するために、以下のような分析手法をとりました。
(1) 判決楽曲と判決原曲のうち、比較対照するフレーズ(類似性が争われているフレーズ)を抽出する
(2) 比較対照するフレーズの長さが同じになるように調整した楽譜を並べる
(3) 音の高さの一致する程度を数量的に計測する
上記の手法による数量的な計測結果に加え、参考判決はさらに以下の点を検討しています。
(4) 両曲の旋律の相違部分を抽出し、相違部分が両曲の表現上の本質的な同一性を損なうか否か検討する
(5) 和声の相違部分を抽出し、相違部分が両曲の表現上の本質的な同一性を損なうか否か検討する
(6) リズム・テンポの相違部分を抽出し、相違部分が両曲の表現上の本質的な同一性を損なうか否か検討する
(7) 楽曲全体の形式(フォーム)の相違部分を抽出し、相違部分が両曲の表現上の本質的な同一性を損なうか否か検討する
なお、旋律の相違部分については、参考判決は、「原曲と同じ高さの音を用いて譜割りのみ変更することは、編曲の範囲内にとどまる常套的な手法にすぎず、原曲の表現上の本質的な特徴の同一性を損なうような改変と見ることはできない」と述べています。したがって、対象曲と譜割りが異なるだけである場合、両楽曲の旋律は実質的には一致すると考えられる可能性があります。
上記のような分析の結果、参考判決は、判決楽曲がその一部に判決原曲にはない創作的な表現を含むことを認めつつ、(1)旋律の相当部分は実質的に同一といい得るものである、(2)旋律全体の組み立てにかかる構成において類似している、の2点から、「判決楽曲に接する者が判決原曲の表現上の本質的な特徴を直接感得することができる」と結論付けたのです。
■裁判所の判断手法は妥当なのか
本来、2つの楽曲の同一性・類似性の判断においては、「人が同一性を感得できるか否か」が問題とされるべきであり、以上のような分析手法を採用すると、音楽の内面的な構造や、楽曲に表現されている思想または感情という本質的な部分が結果的に看過されてしまうおそれがあります。参考判決については、この点を批判する見解も存在します。(実際のところ、筆者が問題となった2つの楽曲を聞いた時には、「ずいぶん感じが違う曲だなあ」という印象を持ちました。)
しかしながら、裁判所としては、ある程度客観的な判断基準を採用する必要がある以上、少なくとも楽曲の類似性の判断の出発地点としては、今後もこのような定量的分析手法が採用される可能性が高いと考えられます。
参考判決も、「もとより、楽曲の表現上の本質的な同一性が、このような抽象化された数値のみによって図りうるものではないことはいうまでもない」としつつ、「形式的、機械的手法によって得られた数字が示す2つの楽曲の旋律の高さの一致の程度が格段に高い」という事実(参考判決における一致率は72パーセント)は看過できないと判示しています。
■「依拠性」について
理論上は、新しい楽曲を制作するにあたって、制作者が既存楽曲に依拠していなければ、たとえ当該新作楽曲と既存楽曲が全く同一であっても、著作権侵害は成立しないことになります。
しかしながら、裁判においては、問題となる楽曲の制作者が、「原曲とされる既存楽曲に依拠していない」と主張すれば、その主張が認められるというわけではありません。参考判決においても、判決楽曲の作曲者は依拠性を否定しましたが、裁判所は、①判決原曲が著名な楽曲である、②判決楽曲と判決原曲の顕著な類似性が偶然の一致によって生じたものと考えることは著しく不自然かつ不合理である、という根拠から依拠性を認定しています。
他方、依拠性を否定した裁判例として、冒頭で言及したワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件があります。同事件では、旧著作権法1条の「複製」が問題になりましたが、控訴審判決は、まず「複製」とは複製者が既存の著作物の存在・内容を知っていることを前提とするとしました。その上で、問題となった楽曲の作曲当時に原曲(米国の楽曲)が日本において有名であったか否かを論じ、日本においては有名ではなかったと結論付け、次に、作曲家が原曲に接したとも推認できないとし、結局、作曲家が原曲とされる楽曲の存在、内容と知っていたとは認められないと判断しました。さらに同判決は、原曲を知らなければ問題となっている楽曲を作曲できない程度に強度に両楽曲が類似しているかという見地から2つの楽曲を検討し、一定の類似性は認めつつも、このような強度な類似性は認められないと判示したのです。
■侵害の可能性の減少要因
新規楽曲と原曲とされる既存楽曲との間に強度の類似性が認められ、依拠性を否定することが困難な場合であっても、なお著作権侵害が否定される可能性もあります。
音楽の著作物に関する裁判例ではなく、言語の著作物の翻案が問題になった裁判例として、江差追分事件(一審・東京地判平成8・9・30、控訴審・東京高判平成11・3・30、上告審・最判平成13・6・28)があります。同事件の最高裁判決は、「言語の著作物の翻案とは,既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう。」と判示した上で、「著作権法は、思想又は感情の創作的な表現を保護するものであるから、既存の著作物に依拠して創作された著作物が、思想、感情若しくはアイデア、事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において、既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には、翻案には当たらないと解するのが相当である。」と述べています。
江差追分事件の判示内容を音楽の著作物の翻案に敷衍して考えてみると、(1)一般的に類似部分が短ければ短いほど、類似部分の創作性が否定されやすく、したがって、著作権侵害はより認められにくくなると考えられますし、また、(2)類似する部分が慣用的な音型の連続であると認められれば、創作的な表現とはいえない慣用的な音型の一致または類似にすぎず、表現上の本質的な特徴の同一性を基礎付けないと判断される可能性が高いと考えられます。
もっとも、音楽の著作物に関しては、江差追分事件と類似する裁判例が存在しないため、上記(1)(2)に関して具体的な判断基準を想定することはなかなか困難です。
■前提―著作権が保護されている楽曲であること
今まで述べてきたことは、「既存楽曲」の著作権の保護が存続していることを前提としています。平原綾香の名曲「ジュピター」(原曲はホルスト(1874-1934)の「木星」(管弦楽組曲「惑星」の第4曲))のように、原曲が著作権保護期間の終了した楽曲である場合は、これに依拠して類似する別の楽曲を作ったとしても、基本的には問題にならないからです。(実は、著作者人格権の問題を別途検討する必要があるのですが、本稿では割愛します。)
■結論―既存楽曲に"ヒントを得て"作曲する時に気をつけるべきこと
天才モーツァルトには天から音が降りてきたそうですが、通常、私達が創作活動をする場合には、過去に触れてきたさまざまな作品がそのベースになっているはずです。「依拠性」といわれても、過去にどこかで聞いた曲を事細かに思い出すことは難しいでしょう。
しかし、少なくとも、著作権で保護されている著名な既存曲をイメージして新規楽曲を作曲し、これを商業的に世に送り出そうという場合(例えばあなたが次の万博イメージソングの作曲を依頼された場合)は、上で述べた数量的な判断手法に従って、既存楽曲と新規楽曲の類似性がないことを検討した方が良いかもしれません。「裁判官は音楽のことなんてちっとも分かってないよなあ」と心の中でつぶやきながら。
以上
法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
※文章内容には適宜訂正や追加がおこなわれることがあります。