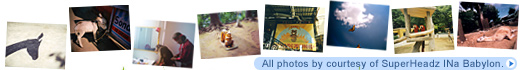2010年5月14日
「製作委員会シンドローム2 -最強のガラパゴスになるために-」
弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts)
■続発する製作プロダクションの破たん
コラム『製作委員会シンドローム』を書いて、「次回は製作委員会症候群への対処策を考えたい」と予告してから半年以上もお待たせしてしまった。年末年始の宿題どころか、もうすぐ初夏である。その間、別なコラムを書き散らし、新書を出し、Twitterをはじめ、果ては仕事に打ち込むなど逃避に逃避を重ねて来た。ちびまるこちゃんでも、ここまで宿題はためない。
逃避行の間に、ムービーアイ(「HINOKIO」)に続いて、シネカノン(「パッチギ!」「フラガール」)民事再生、トルネードフィルム(「日本以外全部沈没」)破産申立、CCRE(「罪とか罰とか」)民事再生と、元気だった映像企業の破たんが続いている。
「製作委員会シンドローム/著作権共有のマイナス面」を示す事態も、現実に見られた。
たとえば、「幹事会社などの破たんによる著作権持分の流出」について、それに近い事態に至ったケースもある。とはいっても、著作権法では他の共有者の同意がないと著作権の持分を第三者に譲ることはできないし、譲られる方も単に持分だけを貰っても仕方がない場合が多い。よって、もう少し複雑な方法がとられるが、他のメンバーが作品のサルベージ(保全)に苦労する点では変わりがない。根拠になる法律や契約の条文がなければ、そうした作品の保全はしばしば難航する。
破たんに至らなくても、作品利用についてメンバー間で合意がとれずに行き詰るケースも、相変わらず多いようだ。著作権を共有している場合、その全員の同意がなければ作品を利用できないのが法律上の原則。権利意識・契約意識の高まりで、これまで日本の特徴といわれた「合意最優先」の文化が薄れつつあり、各社が思惑をストレートにぶつけ合う場面は増えている。商社のように、投資リターンを至上命題に映像製作に参入して来た「半アウトサイダー」ほど、この傾向は強いように感じられる。
無論、毎回コンセンサスで苦労しなくて済むように、製作委員会契約で利用のルールを明確にしておくことになっている。が、不十分なケースも多いと前回書いた。ネットビジネスの加速で、このことは一層あからさまになって来たようだ。
当事務所で実際に扱ったケースの話はできないので、2005年頃に出版された代表的なコンテンツビジネスの実務書に掲載された、「製作委員会契約書の雛形」を例にとろう。
こうした契約書では、「利用窓口」の規定に多くのスペースが割かれる。放送やDVDなどのビデオグラム化といったビジネスの形態ごとに、どの製作委員会メンバーが利用の権限を得て、収益をどのように他のメンバーに配分するか、定めるのである。
ところが雛形では、明瞭に窓口となる会社を取り決めているのは、「国内放送」「国内ビデオグラム化」「商品化」の3種類のビジネスだけ。それ以外は「他の利用」として記載が省略されており、おそらくメンバー間の協議で取り決める建付けだ。「ネット配信」「海外番組販売」の窓口すら決まっていない。
そもそも、この雛形には「窓口については10年目にメンバー協議で決する」という見直し規定がある。はじめから、当初10年間の利用しか想定していないのだ。映画の著作権の保護期間は「公表から70年」なので、見直し合意できなければ、残り60年は全員の同意がないと一切利用できないという原則に戻る。
しかし、それ以前にネット配信の窓口すら規定できていないのだから、この契約書の賞味期限は(作られた2005年頃から)5年間もたなかったことになる。
この例ほど極端ではないにせよ、たとえば20年前に共同製作された映画の契約書をいま取りだした場合を考えてみよう。いや、勇気があれば実際に取りだしてみても良い。20年先の映像の利用ルールをすべて契約書で取り決めておくなどは不可能であり、それだけでは著作権共有のリスクに対処できないことがわかるはずだ。
■著作権共有リスクへの対処策
決して、過去の契約書をあげつらって責めているのではない。これまでの変化のスピードを考えれば、今から10年後のビジネスの状況ですら、完全に予測して契約を交わすことは土台無理だ。作品の著作権を共有すればリスクはどうしても内在する。
前回も述べたが、「作品に出資すること」と、「収益配分を受けること」と、「著作権を共有すること」は、お互いに関連はしても別個の問題である。しかし、日本ではなぜかそれは全て一体と考えられてしまっている。「収益配分を受けるためには作品に出資しなければならず、作品に出資する以上は著作権を共有する」という直線的な思考だ。
ここに問題の根がある。
著作権共有リスクの克服策になりそうな先例は、すでに存在している。『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』で見られたように、「他者の出資を仰がずに映像を自社製作する」という原点回帰も今後は増えるだろうが(*注) 、ここではそれ以外で幾つかの実例を見てみよう。
典型的な製作委員会方式(任意組合)の特徴と課題を復習しておけば、①委員会自体には法人格がないので権利義務の主体になれないこと、②メンバーの無限責任、③(多数決での業務執行が原則となるため)意思決定に手間取りやすいこと、そして、④著作権共有による利用の不安定さ、だろうか。対するメリットとしては、⑤手続が要らず立ち上げが比較的簡便なこと(=組成コストの低さ)と、⑥パススルー課税(=委員会自体は課税されず法人のような二重課税を避けられる)が挙げられよう。(なお、2005年に登場したLLP(有限責任事業組合)では、上記②の「無限責任」の点以外は、従来の任意組合の課題は特に解消されないので、独立しては触れない。)
(* 注) 銀行ローンや匿名組合のような純然たる資金提供者だけに頼るのも、自社製作のヴァリエーションといえる。
(1) SPCの利用
このうち、多くの課題には理論的に対処できるものに、SPC(特定目的会社)を利用した製作形態がある。
たとえば、テレビアニメ「かいけつゾロリ」や「バジリスク~甲賀忍法帖~」がSPCを利用した製作の例だ。共同製作の場合ならば、作品を製作し著作権を保有するための会社(株式会社など)を各社の出資で設立し、そこに全ての権利を持たせてしまうのである。
この形なら、新会社(SPC)の意思決定は原則として取締役などが担うことになるし、SPCが著作権を100%持つことで権利分散のリスクは減る。
また、権利が一元化されるので、ハリウッドのように映像資産の売却(カタログ譲渡)も成立させやすい(ただし、こうした流動性を完全に持たせるにはクリエイターなどとの契約問題も含めた対処が必要)。仮に各社の共同事業であることを対外的に示したいならば、この方式でも対外的に委員会の名称を残す方策はあるだろう。
欠点としては、会社設立をともなうため組成コストがやや高い、従来型委員会方式の長所といえるパススルー課税がおこないづらい、という問題がある。また、SPC自体が各社の出資で設立されている場合、株主である出資者間で路線対立が生ずれば、やはり作品利用はスタックする可能性がある。
SPCの形態としては株式会社に加え、2006年に導入された日本版LLC(合同会社)が利用される場面も増えそうである。LLCは海外の映像製作でもしばしば利用される形で、株式会社などと組合の中間的な形態ともいえ、映像製作のような特定プロジェクトには向く。
| 従来型の製作委員会 (≒任意組合) |
株式会社 | 日本版LLC (合同会社) |
|
|---|---|---|---|
| 法人格の有無 | × | ○ | ○ |
| 出資者の有限責任 | × | ○ | ○ |
| 業務執行 | 組合員の多数決が原則 | 取締役など | 社員の多数決が原則 |
| 設立の手間 (組成コスト) |
低い? | やや高い? | やや高い? |
| パススルー課税 | ○ | 原則× | 現在は× |
(2) 信託の利用
信託を利用した映像製作のスキームが脚光を浴びたことがある。ただし、この方法は組成コストが高いほか、信託方式を用いたジャパン・デジタル・コンテンツ信託やシネカノン(「パッチギ!LOVE&PEACE」などで利用)の挫折で、しばらくは関係者の心理的なハードルも高いかもしれない。また、次の機会に考えたい。
(3) 製作委員会方式での権利一元化
より単純に、現在の製作委員会契約の改善策として、著作権は一社に集めてしまい収益請求権化する方式や、買い戻し特約を置くのはどうか。
前者は、製作委員会として映像を共同製作した上で、特定の会社(幹事会社など)に著作権を全て譲渡してしまう発想である。その代わりに、出資者は作品からの収益配分請求権や、期間を定めた作品利用の窓口を取る。
音楽ビジネスでの原盤の共同製作は、実はこの形態が多い。二社で原盤を「共同製作」することはよくおこなわれるが、原盤完成と同時にしばしば原盤権(著作隣接権)はそのうち一社に集約され、利用はその代表社がおこなう。他方の会社は、「共同原盤を持つ」と名乗りそう表示もされるが、実際には利用による収益を折半するだけの存在だ。出資の見返りは収益配分なのである。
映画の場合には、単に配分だけでなく、放送やビデオグラム化などの窓口を取ることが目的で出資をする場合も多いので、出資者は収益配分に加えて、特定の利用の窓口になることも求めるだろう。しかし、これらはいずれも著作権は共有しなくてもできる。
著作権は一社に集めておいて、残りの出資者は収益配分や窓口の(期限付の)委託や許諾を得ることにすれば、権利分散のリスクはある程度減らすことができる。
仮に、上記の方法では著作権をとらない出資者にとって抵抗が強いのであれば、最初は著作権共有にしておく。その上で、5ないし10年経過後に、幹事会社がその時点の評価額で著作権を買い戻せるような特約を設けておく方法もあろう。
評価額というだけでは金額が容易に決まらないおそれがあるので、(直近3年間の収益のX%といった)何らかの評価の数式を最初に決めておいても良い。
この方法には一定の限界もあるし、税務会計上の検討を要するが、従来の製作委員会契約の微修正で対応できるという意味では、現実味がある。幹事会社にとって、共同製作のシナジーを生かしながら、10年後なりに映像が一定の条件で自社の完全な知的財産(ライブラリー)として戻って来るのは魅力ではなかろうか。映像資産の長期活用や流動性を考えれば、一考に値する選択肢だろう。
■キーワードは権利の一元化
以上、幾つかの選択肢を考えてみた。無論、それぞれのスキームに多様なリスクと検討事項がある。
出版の世界も映像の世界も、今後の権利ビジネスのキーワードは「マルチユース契約と権利一元化」だろう。それと収益配分は分けて考える。大もとの権利は一元化しながら、窓口は期間を区切って各社にゆだね、また、関係者に収益配分をして行く方向に舵を切るべきではなかろうか。
あわせて、こうした独占ライセンスや収益配分の取りきめを第三者に対して主張(対抗)できるような、保護法制も整えるべきだ。
確かに、日本型の製作委員会方式には、多様なプレーヤーが少ないコストで映像製作に加わり、作品の利用権を確保してシナジー効果を発揮できるという、優れた点がある。その強みを発揮するためにも、権利分散という「将来へのツケ」が作品に残る現行の方式には改善が必要だ。
世界に目をやれば、(本稿執筆中にもディズニーによる約43億ドルでのコミック最大手マーベルの買収、タイムワーナーによる約15億ドルでのMGM買収交渉が報道されるなど)作品の権利をめぐる争奪戦は熾烈を極める。10社や時にそれ以上の企業が作品に出資し権利共有する日本の方式は、国際的にも類例の少ない「ガラパゴス」であるともいえる。ひとつの作品の権利がバラバラに分散し、その利用が特定の人的関係に依存し過ぎる日本の映像資産では、そもそも作品の客観的な価値評価など出来るはずがない。買収や流動化が仮にあり得るとしても、金額はより情緒的・直感的に決まり、映像資産の活発な流通などはそれだけ難しいだろう。
とはいえ、「ガラパゴスが全て悪い」という考えには与しない。たとえば、世界的に技術標準の趨勢が決まったような分野で日本の独自方式を維持することはメリットが少なかろう。しかし、映像製作のビジネス方式が日本独自であったとしても、それだけなら悪いとばかりは言えない。要は、権利分散という最大の課題への対応である。
共同製作の長所を生かして優れた作品を生み出しながら、将来の利用や流動化を円滑にすることもできれば、日本型の映画製作方式が世界の人々にとって「黒船」になるかもしれないのだ。
以上
■ 弁護士 福井健策のコラム一覧
法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
※文章内容には適宜訂正や追加がおこなわれることがあります。