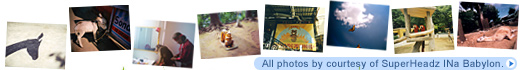2010年7月14日
「デジタルシネマ普及の鍵」
弁護士 松島恵美(骨董通り法律事務所 for the Arts)
■3Dコンテンツ時代の幕開け
昨年は映画の3D元年、今年2010年はリビングの3D元年といわれている。
昨年末に公開された「アバター」で3D映画が日本中に浸透し、その後、「タイタンの戦い」、現在は、「アリス・イン・ワンダーランド」、先週末から公開された「トイ・ストーリー3」が上映中、続いて「ヒックとドラゴン」、「バイオハザードIV」など、ビッグタイトルの3Dコンテンツが目白押しである。また、3Dテレビも各メーカーから発売されて、大きな話題を呼んでいる。
しかし、3D映画であってもすべての映画館で3D体験できるわけではなく、3D上映館でないと、その体験はできない。
3D映画の波が日本に押し寄せようと、3D上映ができる映画館が不足しているのが現実である。
一方、家庭における視聴環境は、3D対応ブルーレイプレーヤー、3D対応テレビなどが次々に発売され、3D時代に向かって着実に進歩している。映画公開から数ヵ月後に発売されるブルーレイを待てば、3D体験ができるとなると、観客の映画館離れにも拍車がかかりかねない。
そもそも、大きな流れとしての観客の映画館離れに歯止めをかけようと、ハリウッドではデジタル3Dコンテンツの普及が課題となり、3D映画を積極的に制作するようになった。しかし、上映できる映画館が不足しているのでは、本末転倒である。
■デジタルシネマ化を取巻く現状
3Dコンテンツの実現には、デジタル撮影とデジタル上映が欠かせない(なお、従来の映画を3D化する技術は、現在開発中のようである)。
デジタル撮影は、「スターウォーズ エピソード2/クローンの攻撃」において、ジョージ・ルーカスが世界に先立って長編映画の完全デジタル撮影をしたものの、公開当時の2002年には、デジタル上映が可能な映画館がアメリカにおいてさえ少なく、その魅力が十分発揮できなかったようだ。
デジタル撮影の利点としては、以下のものがあげられる。
- フィルムを使わないので現像しなくてもその場で撮影画像の確認ができる。
- コンピューターによる画像処理に適している。
- 撮影フィルムの現像や画像処理をするためのスキャンの手間とコストが省かれる。
- 画像データの劣化を避けられる。
- 連続した長時間撮影が可能である。
これらは、制作者側のコスト削減と画質の向上に大きく貢献する。また、DVDやブルー・レイなどのビデオグラム化の際のマスタリングも容易である。
また、デジタル上映の利点としては、以下のものがあげられる。
- デジタル媒体がフィルム媒体に比べて安価である。
- 映画1作品のための媒体の重量が軽い(2時間作品のためフィルムは6本必要であるが、デジタル媒体は1つで足りる)。
- 上映のための作品データの複製が安価である(フィルムは上映館の数だけ複製が必要であり、複製コストも高い)。
- 画像が劣化しない。
すなわち、多大な複製コスト・輸送コストがかかり、フィルム劣化による画質の劣化が発生するフィルムによる配給の問題点を解決する。
デジタルシネマ化は、2006年にハリウッドスタジオを中心にまとめられたDCI(Digital Cinema Initiative)の仕様が規格化され、製作・上映過程においてDCI規格を遵守することによって、普及が加速した。そして、デジタルシネマを普及させる切り札が、観客にデジタル映画の魅力を最も訴えることができる3Dコンテンツであった。
さらに、デジタル上映に必要なデジタルシネマシステムがあれば、同じ規格で撮影した、映画以外のコンサート・歌舞伎・バレエ・オペラなどの興行、集会、セミナーなどのコンテンツ〔Alternative ContentsまたはOther Digital Stuff(略称ODS)〕の上映が映画館で可能となり、映画館にとっては、客足の少ない時期・時間帯のスクリーンを有効活用することも可能となる。さらに、映写される広告も、同じ規格で制作すれば、客層に合わせてフレクシブルに工夫できる余地がある。
もっとも、デジタルシネマシステムの導入には多大なコストがかかる。デジタル上映に必要なサーバーとプロジェクターだけでも1スクリーンあたり数千万円といわれている。映画館が自前でデジタル上映システムを導入するには、大きな負担であることは間違いない。
■デジタルシネマシステムの導入・普及の鍵~VPFスキーム
欧米においては、映画館のデジタル上映システム導入を促進するために、VPF(バーチャル・プリント・フィー)スキームを採用したビジネスモデルの利用がさかんである。このスキームによって、アメリカでは、すでに1万スクリーン以上、欧州では1千スクリーン以上が、デジタルシネマシステムを導入したといわれている。
日本でも、2009年10月にソニーが初めてこのビジネスモデルを活用し、自社のデジタル上映システムの導入を促進させることを発表しているが、現在なお普及途上といえよう。
<VPFスキームとは>
それでは、VPFスキームとは、どのような仕組みなのであろうか。
まず、VPFサービサーといわれる事業者が、デジタルシネマシステムを自ら調達(購入または賃借)し、これを映画館に利用させる(前述のソニーはVPFサービサーの役割を担う)。
そして、映画館は、わずかな初期導入費用とともに、月々の利用料を支払うことで、初期投資を大幅に抑えながら、デジタルシネマシステムを導入できる。
しかし、ここで注目すべきは、デジタル上映普及によって恩恵を受ける者である。
観客が増えるであろう映画館はもちろんであるが、デジタル上映によって多大なプリント複製・輸送コストを節約できるのが、映画配給側である。
そこで、映画配給側から、フィルム上映からデジタル上映に切り替えることによって節約できる費用に相当する料金として契約上設定する金額(VPF)を、スクリーンへのデジタル作品のブッキングごとにVPFサービサーが徴収する。そして、これと映画館から徴収する利用料の合計からVPFサービサー自身の手数料控除後、デジタルシネマシステムの機材調達費の回収にあてるのである。
VPFが、バーチャル・プリント・フィー(直訳すると仮想プリント料)といわれる所以である。
映画配給側が、デジタルシネマを配給することによって、デジタルシネマシステムを利用するととらえ、システム利用料として徴収するのである。
<VPFスキームの課題>
映画配給側と映画館の間にVPFサービサーが入ることによって、デジタルシネマ普及を促進するビジネスだが、このビジネスが成立するためには、いくつかの課題がある。
- 映画配給側は、デジタルシネマが製作されても、一定数のデジタル上映館がないと、デジタル上映によるメリットを十分に享受できない。
- 映画館側は、一定数のデジタルコンテンツ(デジタルシネマ、Alternative Contentsなど)がないと、デジタルシネマシステムを導入するメリットを享受できない。
- VPFサービサーは、一定数の且つ継続的なデジタルコンテンツのブッキングがないと、VPFを徴収できず、デジタルシネマシステムの機材調達費用の回収ができない。
そこで、これらの課題を解決するために、VPFサービサーと映画配給側、VPFサービサーと映画館側の契約には、以下のような条件が盛り込まれることが多い(なお、契約に関する記載は、欧米のVPFサービサーが公表しているホームページ等の掲載資料を参考としている。実際の契約条項は、当事者間の交渉によって決定されることはいうまでもない)。
- 映画配給側がVPFの支払を開始する条件として、VPFサービサーが一定数の映画館と契約済みであること、且つ、一定数の他の映画配給会社が同様の契約を締結していること。
- VPFサービサーは、契約期間中に一定数のスクリーンにデジタル上映システムを導入すること(同時に、映画館側は、一定期間中に自身が運営する一定数のスクリーンにデジタル上映システムを導入すること)。
- 映画配給側は、各スクリーンについて、10年程度(またはデジタルシネマシステムの機材調達費用が回収されるまで)の期間、VPFを支払うこと。
- 映画配給側は、一定のデジタルシネマ配給率を維持すること (同時に、映画館側は、一定のデジタルシネマブッキング率を維持すること)。
以上の条件は、まさに卵が先か、鶏が先かの問題であり、映画配給側と映画館側が同時多発的にこのスキームに参入することにより、初めてVPFスキームが有効に稼動するのである。
しかしながら、同一事業者グループが映画配給側と映画館側を兼ねることが独禁法上禁止されている米国と違い、幸い、日本においては同一事業者グループが映画配給側と映画館側の両者に存在することが多く、また、映画配給側の系列シネマ・コンプレックスも多いため、この課題の解決は米国と比べれば難しくはないことが予想される。
このほかにも、デジタルシネマシステム導入・利用に関する契約には以下のような条件が盛り込まれる。
- デジタルシネマシステムは、DCI準拠とする。
- VPFサービサーは、映画館と別途契約のうえ、デジタルシネマシステムのメンテナンスを行う。
- デジタルコンテンツのブッキングは配給側と興行側で自由に決めることができる(VPFサービサーの介入はない)。
- 配給側には、VPFサービサーを通じて上映実績の情報が提供される。
- 3D上映システムはオプションとして提供される。
配給側にとっては、VPFスキームに参加することによって、これまで映画館の申告によってしか把握できなかった上映実績について、デジタルシネマシステムの稼動状況を把握するVPFサービサーを通じて、入手することができるのも一つのメリットとなる。
なお、すでに述べたとおり、デジタルシネマシステムは、Alternative Contentsや、デジタル広告などにも対応できるため、これらのコンテンツ提供者からも、VPFに相当する金額がデジタルシネマシステム利用料として徴収され、デジタルシネマシステム機材導入コストの回収(リクープ)にあてられる。
VPFスキームの導入において、その他検討すべき課題としては、以下の点が考えられる。
- DCI規格の改訂・変更への対応と費用負担
- 上映トラブルの際の危険負担(デジタルブッキング後、プリント上映を余儀なくされた場合のVPF支払の扱い)
- 新映画館・新スクリーンについてのデジタルシネマシステム導入とVPFの支払(映画配給側のVPF支払期間)
■日本における普及状況
現在、日本において映画館のスクリーン数は約3400、そのうち、デジタル上映館は約350スクリーン、うち3D対応スクリーンは300に迫るといわれている(いずれも2009.12末の統計)。
現時点でデジタル上映ができるスクリーンは、映画館が自前でデジタル上映システムを調達(購入またはリース)し、または、前述のVPFスキームを利用してソニーの機材を導入した場合が主であろう。
しかし、今回紹介したVPFスキームのVPFサービサーとして、今後、新規参入組があらわれるのも時間の問題と思われる。
また、先日、映画館へのデジタルコンテンツの納入方法として、ネットワークを通じてデジタル配信するシステムの実用化も発表された。
いよいよ日本もデジタルシネマの普及に向けて大きな動きが始まった段階といえよう。
以上
法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
※文章内容には適宜訂正や追加がおこなわれることがあります。